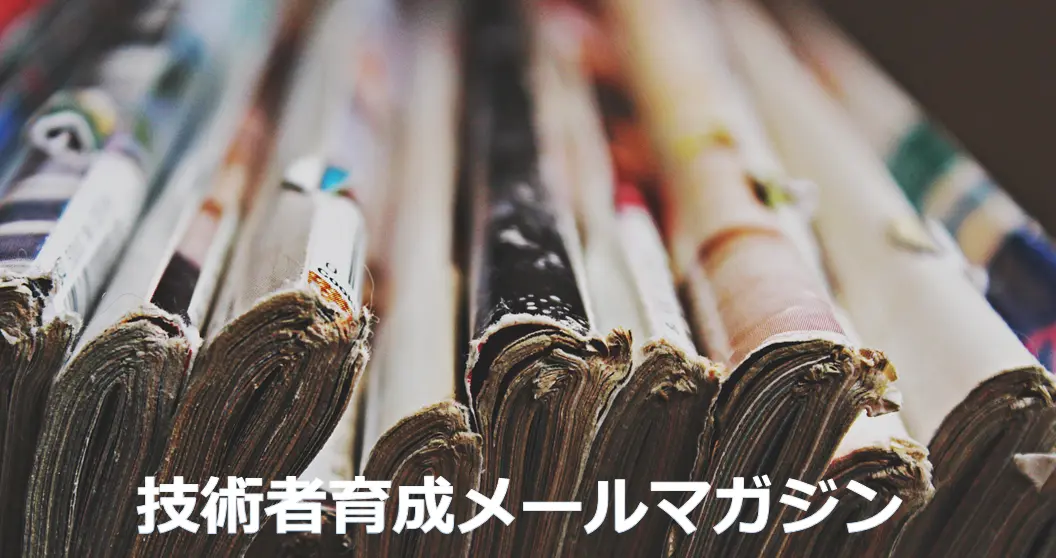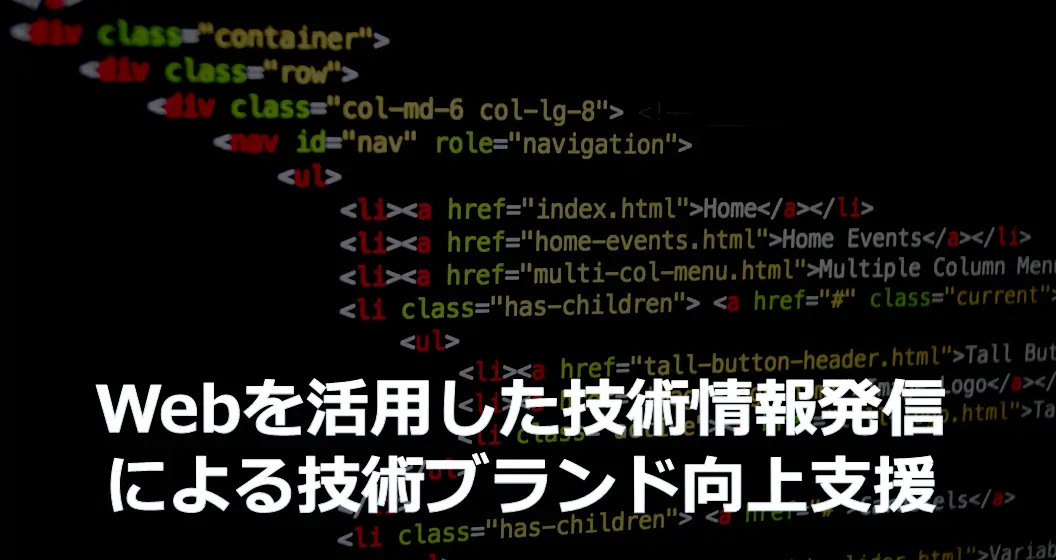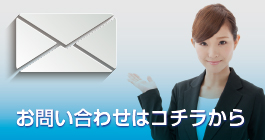顧客向けの開発業務なのに、若手技術者が顧客要望を横において走ってしまう
公開日: 2025年11月17日 | 最終更新日: 2025年11月16日
タグ: OJTの注意点, メールマガジンバックナンバー, 仕事の遅れる若手技術者, 内向き志向, 技術者の普遍的スキル, 技術評価計画
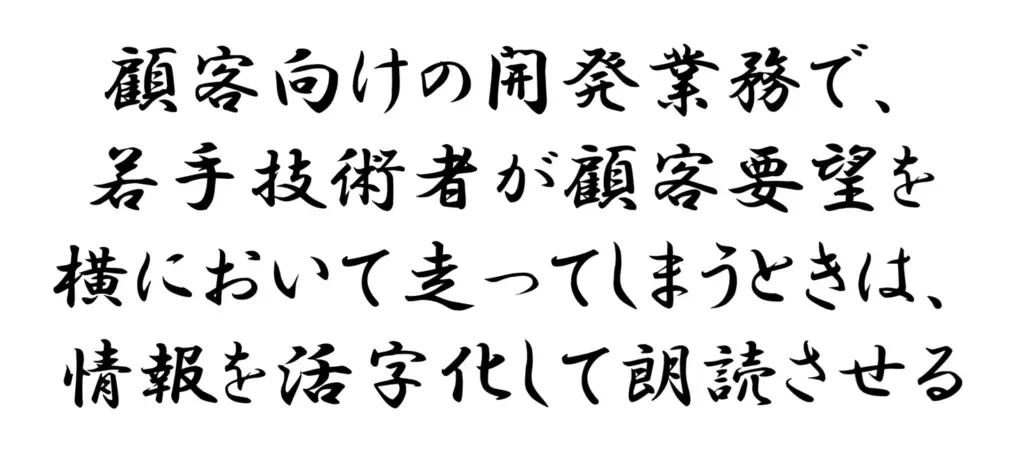
製造業企業の中には、顧客の要望に応じた開発を行うことを生業とする場合もあると思います。
このような企業は技術の基本を有し、委託した企業を技術的に支える重要な役割を果たします。
しかしながらこのような企業に属する若手技術者の中には自らの立ち位置を理解できず、
自分の思いに基づいて走り出してしまう方が一定数います。
今回はこのような若手技術者の対応を技術者育成の観点から考えます。
開発委託は決して珍しいことではない
メディア等で出てくる大手企業の中には自前で技術を開発し、
それを具現化するというケースもあります。
しかし多くの大手企業では、具体的な開発を他の企業に委託し、
それを取りまとめる役割に徹する手法を採用していると思います。
似たような話は、例えば以下の参考情報の記事内の取材の中でも触れられており、
大きな企業には”ものづくり”の実践経験豊富な百戦錬磨の技術者がいたが、
今はコストと納期管理が主となり、開発を受託する企業にものづくりのノウハウは蓄積されつつある、
という趣旨の記述がありました。
※参考情報
つくりびととの談(かたら)い(Wedge 2025年11月号)
業務の効率的な推進という流れが定着したといえるかもしれません。
開発委託を前進させるには複数の技術者や社外企業をけん引する力が必要
開発委託をしたことをきちんとまとめ、
それを管理、推進する力は企業にとって大変重要です。
特に技術者は複数の企業を適切にけん引し、
それぞれの力を引き出しながら研究開発を推進する力が求められており、
技術者の普遍的スキルの一つである企画力にも関連します。
他の技術者を自分の味方に引き入れ、しかるべき方向に進める誘導力が基本にあるためです。
※関連コラム
管理側に行く前の若手技術者のうちに多くの実践経験を積むのは大前提
ただ上述したような技術者としての取り組みは、
「若手技術者のうちに技術の現場を経験してきたからこそ力を発揮できる業務」
です。
若手技術者がいきなり管理だけをやるような仕事のやり方をしていると、
当該技術者は技術の基本のない管理者としてのスキルだけが高まり、
バランスの悪い人材となってしまう可能性もあります。
最近マスメディアで見られた以下のような記事も、
そのような人材の将来的な課題を突き付けていると感じます。
この記事の対象は総合職を想定している印象ですが、
技術者の方々も他人事ではないでしょう。
※参考情報
50代の早期退職、年収半減でも転職困難 「ゼネラリスト」偏重に課題も(日本経済新聞 2025年11月12日掲載)
何度も述べている通り、技術者育成の観点から言えば技術者は若いうちに実践経験を積みながら普遍的スキルを高め、評論家にならないよう我武者羅に目の前の技術業務に取り組むことが肝要です。
スキルマップやスキルアッププランといった話は、
泥臭い技術業務の実践経験を通じた現場での理不尽さや想定外の多さを体感した後で十分です。
※関連コラム
技術的な議論において、若手技術者が否定的な意見を述べるだけで提案が少ない
開発委託の主役は受託した自分たちではなく”顧客”
話を開発委託に戻します。
開発委託をされた企業に属する企業は、
その要望を満たすため開発という技術業務に取り組みます。
しかしこのような技術業務に取り組んでいるうちに、
いい意味で若手技術者を中心とした技術者が陥りがちな思考があります。
それは、
「これは自分たちの仕事である」
という考えです。
これ自体は当事者意識という意味で素晴らしいといえます。
しかし、自分たちの仕事という考えで”視野が狭小化”してしまうと様々な問題が生じます。
開発業務の主役である顧客の存在が薄れる
開発業務を通じて何が必要かを最も理解しているのは、
依頼元の顧客です。
これは不変の大前提です。
ここで仮に開発業務で問題が生じたとします。
想定していた結果が出ない、求められる要件を満たせない、
必要なデータや化合物が得られない、といったものは一例です。
これらの課題に直面した若手技術者は、自分の仕事であるという当事者意識の高さ故に、
「この課題は自分たちだけで解決しなければならない」
と”思い込む”ことがあります。
この時点で業務の主人公が”顧客から自分”に移ってしまっているのです。
こうして顧客の存在という、開発委託を基本とした技術業務の原点がずれ始めます。
顧客の要望が見えなくなる
上述の顧客の存在という原点がずれ始めた場合、若手技術者が良く起こす言動例を示します。
例えば開発業務を依頼した顧客から、
「○○の評価が終わった時点でご連絡をください」
という”要望”があったとします。
しかし、実際に評価を行っているうちに、
「○○の評価は終わった。しかし、その結果を見ると、もっとこうした方がうまくできるのではないか。いや、せっかくなのでここまでやってしまおう。」
という若手技術者自身の気持ちが抑えられずに、思ったところまで進めてしまう。
この時点で、顧客からの”○○の評価が終わった時点で連絡が欲しい”という、
「顧客の要望を無視してしまっている」
のです。
もしかすると若手技術者は、自分たちは言われたことだけをやるのではなく、
能動的に動けるということを示したいのかもしれません。
リーダーや管理職から若手技術者に裁量権が与えられ、
その管理下で自由にやっていいということであれば褒められるべき姿勢です。
しかし、顧客からの”要望”は別物です。
「良かれと思ってやったことも、顧客から見るとただの”暴走”」
になってしまうのです。
リーダーや管理職がこの暴走に気が付いて止められればいいですが、
若手技術者は色々言われたくないため、
見えないところで勝手に進める傾向にあります。
そうすると、顧客要望に基づいて動いていたはずの若手技術者たちの暴走は、
リーダーや管理職にとって寝耳に水となるでしょう。
暴走を恐れて様々な縛りをするのは不適切
このように言うと、若手技術者が暴走しないように様々な制限をつければいいと考えるリーダーや管理職の方もいるかと思います。
管理者である以上、ある程度の管理は必要です。
しかしあまりにも縛りをつけてしまうと、
若手技術者は”指示待ち”になるか、
その窮屈な環境に嫌気がさして離職してしまうでしょう。
※関連コラム
ではどのような対応で、暴走を抑えればいいのでしょうか。
縛るのではなく短時間のコミュニケーションを頻度よく取り暴走を防ぐことが重要
重要となるのは縛るという考えよりも、短時間コミュニケーションの頻度を上げることにあります。
例えば朝の時間を使って、進捗の管理と必要な指示事項を与える等、
短時間のコミュニケーションを頻度よく取り、
暴走の傾向をいち早く察知し、軌道修正を加えるといった対応が妥当です。
※関連コラム
顧客の要望を紙に印刷し、繰り返し朗読させる
この朝ミーティングでもう一つ行ってほしいのが、
「若手技術者の思考回路への顧客要望の徹底的な刷り込み」
です。
まずは顧客要望が出ていればそのデータを、
もしなければリーダーや管理職が口頭で若手技術者に伝え、
それを目の前で書かせたものを紙媒体で用意してください。
それを既述の朝ミーティングで繰り返し”朗読させる”ことを行ってください。
毎日である必要はありませんが、週に一度は声に出させるなど、
”繰り返すこと”が重要です。
顧客から要望が出ていた場合、それに該当する業務が継続している間は繰り返すというイメージです。
前出の顧客要望を無視してしまった例でいえば、
要望事項を口頭で朗読させた後、
「○○の評価が終わった時点で自分に知らせてほしい。内容を確認後、顧客に状況を報告する。」
という指示をリーダーや管理職から出します。
これを一度ではなく、朝ミーティングにおいて何度も伝え、
記憶に定着させることが重要です。
自分なりに工夫したことを否定しない
積極的な若手技術者の中には、
- ○○の評価が興味深いので、自分なりに他の評価を行いたいと考えた
- ○○の評価結果を自分なりに解釈してみた
といった”自分なりの工夫”をしたがる方もいます。
通常の研究開発であれば至極自然であり素晴らしい姿勢ですが、
顧客という主人公が居る開発委託の技術業務では、
上記のような寄り道で”遅延する”ことは避けなくてはいけません。
これをそのまま伝えしまうと、業務が面白くないと感じる若手技術者もいると思います。
モチベーション低下という意味でよくないことです。
「お前の考えや意見を聴きたいのではない。それによって遅れが出たらどうするのだ。」
といった否定的な言い方ではなく、
「自分なりに色々とトライをすることは良いことだと思う。
ただ今回の評価は顧客の依頼に基づいている業務であり、
まずは要求されたことを完結させることを最優先に動いてもらいたい。
それが終わった後、自分なりに考察をしながら結果を解釈する、別の評価をすること自体は是非やってもらいたい。
顧客への報告が終わった後でいいので、技術評価計画を作成して見せてもらえるか。」
というように、顧客要望に沿うことを最優先にしながらも、
技術的なトライをすることを後押しするバランスが、
リーダーや管理職に必要です。
※関連コラム
まとめ
開発委託に関する技術業務を若手技術者にも担当させることは、
期限が明確であるなど時間軸がしっかりしていることも多く、
また社外とのやり取りを通じて視野を広げる効果も期待できます。
技術者育成の観点でいえば、OJTに適した技術業務の一つです。
同時に、顧客の要望出発の開発業務を社内の開発業務と区別がつかずに暴走してしまう若手技術者も多く、リーダーや管理職はその対応に頭を悩ますことがあるかと思います。
ここで今回紹介したような顧客要望を紙で読めるようにし、
朝の時間を使って若手技術者にそれを繰り返し読ませることで、
当該要望を意識づけさせるというのは若手技術者の暴走を抑える特効薬となりえます。
仮に若手技術者が顧客要望と異なることをやってみたいと意見を言った場合、
それを否定せず、しかしまずは顧客要望に基づいた技術業務を完遂させるという、
優先順位を理解させる指示の出し方がポイントとなります。
ご参考になれば幸いです。
※関連連載
第24回 若手技術者が技術業務の進捗報告をしない 日刊工業新聞「機械設計」連載
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: