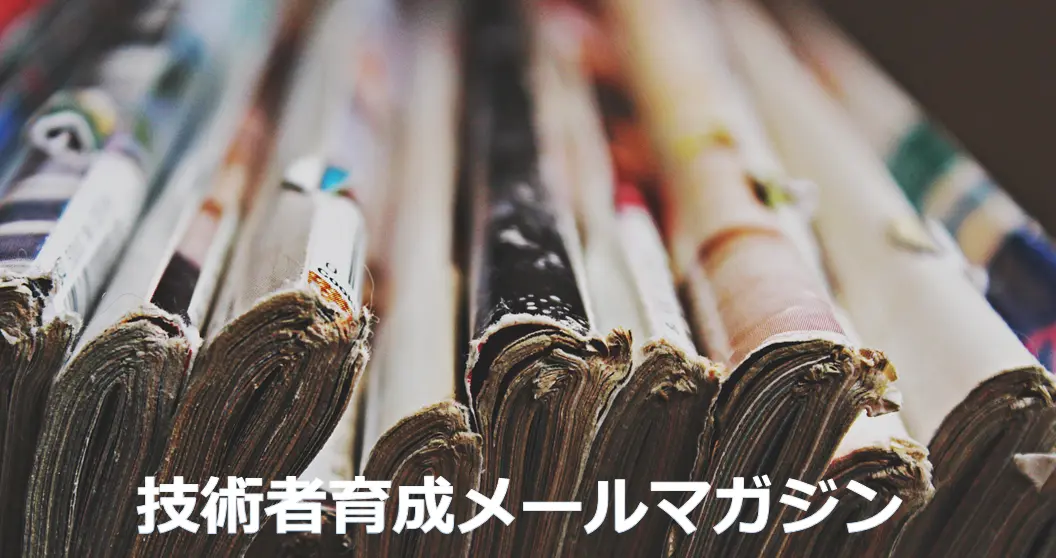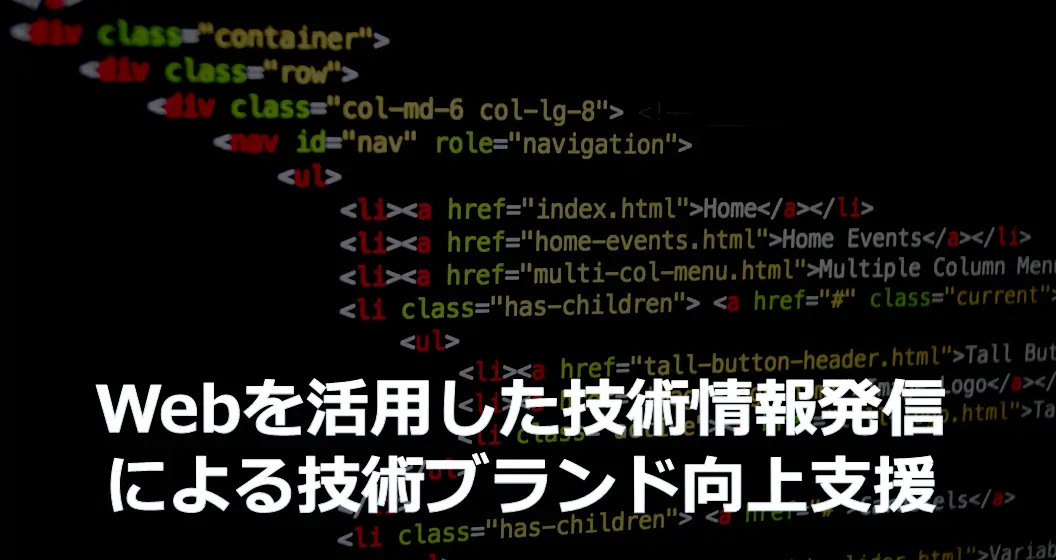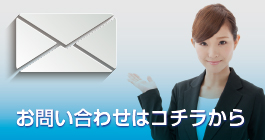若手技術者の技術評価結果の妥当性を再確認したい
公開日: 2025年10月20日 | 最終更新日: 2025年10月19日
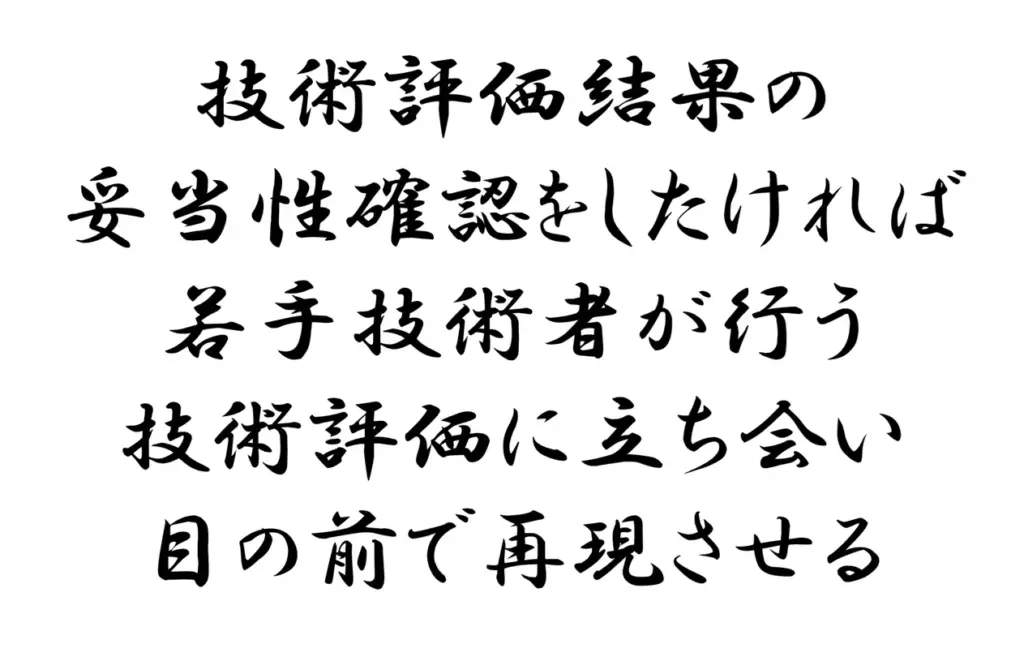
現場での技術評価を若手技術者に推進させることは、
組織としてリーダーや管理職の時間捻出につながることに加え、
当該技術業務を通じた若手技術者の経験蓄積に大変重要です。
しかし若手技術者の行った技術評価結果に対し、
リーダーや管理職がその妥当性を確認したいという場合もあると思います。
この”確認したい”という心理を若手技術者育成に活用することを考えます。
若手技術者の行った技術評価結果の妥当性を確認したい対象例
一言で妥当性を確認してみたいといっても、
リーダーや管理職の動機は様々です。
妥当性を再確認したいという動機づけになる対象として、代表的なものを述べます。
顧客に提出する/製品仕様判断に用いる正式データ
顧客に最終的に提出する、
製品開発の仕様を決定する技術的判断に用いるといった、
事業的、もしくは技術的に重要なデータが一例です。
これらのデータは間違えがあってはならないため、
その取り扱いには注意が必要となります。
得られたデータが仮に予想通りだったとしても、
今一度確認しよう、といったことが動機の代表例です。
想定と大きく異なるデータ
こちらはイメージしやすいかと思います。
想定されたものと大きく異なるデータが得られた場合、
- 正確に評価が行われているか
- 評価に用いた原料、設備、制御装置等に問題は無いか
- 評価の手順を間違えていないか
といった点を確認したいケースが当てはまります。
想定通りすぎるデータ
これは技術的に優れた知恵を有するリーダーや管理職でよくみられる思考パターンです。
評価の前から想定された通りのデータを得られたことは、
若手技術者にとって”嬉しい”と感じるケースもあるようです。
これは、自分がリーダーや管理職の期待に応えられた、
という承認欲求が満たされた状態にあるからです。
想定外のことが起こる方が、技術的な進歩の確率が高まる
しかしながら、技術的な観点でいえば”想定通り”に結果が得られることは、
それほど多くありません。
むしろ、想定外のことが起こった時こそ、
技術的に言えば重要な局面にあることが多いのです。
技術的に優れたリーダーや管理職は本観点を有していることが多く、
そのためあまりにも想定通りの結果が出た場合、
それを疑うのです。
想定通りのデータが欲しいという企業組織の欲求は、
最悪の場合、現場の技術者を”捏造”へと駆り立てます。
人が想定できることはたかが知れているという技術に真摯な姿勢こそ、
若手技術者は見習うべきであり、
同時にリーダーや管理職はその背中を示すべきでしょう。
※関連コラム
Web上の試験データを鵜呑みにせずにやってほしい技術的アプローチ
次に、実際に技術評価結果の妥当性を再確認する手法について述べます。
技術評価結果の妥当性を再確認したい場合の留意点
若手技術者が報告した技術評価結果の妥当性を再確認するにあたり、
忘れてはいけないことを述べます。
それが、
「若手技術者を信用していないという意味ではない」
ことを繰り返し伝えることです。
技術評価を行う実験や試験でミスの多い若手技術者であれば、
技術評価結果ではなく、それを行った若手技術者への信頼性の不足から、
当該結果の再確認をしたいと考えるかもしれません。
しかしながら、技術者育成を推進できる体制構築の大前提は、
育成される側(若手技術者)とする側(リーダーや管理職)の信頼関係。
ここに問題があるようであれば、
本大前提をクリアできるよう、まずは信頼関係の醸成から取り組む必要があります。
※関連コラム
業務を抱え込む若手技術者心理の背景と技術チームプレー理解への一歩
問題に直面した若手技術者が「 べき論 」をかざすだけで、動かない
技術評価の再現現場にリーダーや管理職が立ち会う
技術評価結果の妥当性を再確認する具体的な方法は、
「技術評価の再現現場にリーダーや管理職が立ち会う」
ことです。
より具体的な手順を述べます。
技術評価計画の作成と確認が前提
内容の質やレベルは問いませんが、
技術評価計画が存在するのは大前提です。
技術評価の計画有無は、業務の結果得られるデータなどの質に直結するため、
それ自体が無いということが技術者育成の観点でも悪影響が出ることに加え、
「技術業務を推進する体制に大きな問題がある」
と認識しなければなりません。
技術評価計画は、
- 1. 技術評価の目的
- 2. 技術評価で得たいアウトプット
- 3. 技術評価のマトリックス表
- 4. それぞれの技術評価概要
- 5. 評価計画概要
を網羅するものであり、これらが網羅されていれば技術評価結果の再現性の確度向上はもちろん、
技術報告書作成負荷の低減、そして技術の伝承にも大きな効果がでます。
技術評価計画の概要については、過去のコラムをご覧ください。
※関連コラム
リーダーや管理職は立ち合い前に技術評価計画で予習する
立ち会う前にリーダーや管理職は技術評価計画の概要を理解することが肝要です。
詳細を理解する必要はありません。
技術評価計画を眺め、技術評価結果の妥当性を再確認するにあたり、
どの工程がキーになるかを確認するのが目的だからです。
若手技術者に技術評価を目の前で再現してもらう
その後、業務を調整したうえで若手技術者に結果妥当性を再確認したい技術評価について、
目の前で再現してもらいます。
その際、リーダーや管理職は技術評価計画を確認できる状態にしておくといいでしょう。
目の前で若手技術者に技術評価を行ってもらいます。
すべての工程が難しいようだったら、
リーダーや管理職の判断で結果妥当性確認に必要な工程のみ再現してもらう、
というやり方でも問題ありません。
リーダーや管理職は評価の途中で口を出さず、最後までやらせる
技術評価の確認中、立ち会ったリーダーや管理職は若手技術者のやることに口を出してはいけません。
仮に間違ったことをやっていたとしても、
それをそのまま進めさせないと実際に何が行われたのかの評価にならないからです。
もし若手技術者から質問が出た場合は、
「まずは、前回行ったことと同じようにやってほしい」
とだけ伝えてください。
もちろん、怪我や事故につながる恐れのあることは、
その場で指摘してください。
このようにして目の前で行われた技術評価を通じ、
リーダーや管理職は技術評価の結果の妥当性を確認するための情報を得ることができます。
リーダーや管理職による立ち合いは技術者育成の効果も高い
行われている技術評価を実際に見ることで、
- 教育した通りに技術評価が行われていた
- 教えたことを念頭に工夫し、技術評価結果をより精度よく得られていた
- 教えたことを守っておらず、誤った手順を踏んでいた
- 技術評価結果に影響を与える不適切な工程が含まれていた
- 説明していたことと異なることを行っていた、説明に無い工程が存在した
といった、実際に見なければわからない情報を得ることができます。
よくできていたことは、若手技術者に伝える
リーダーや管理職が立ち会う状態で技術評価を行うことは、
若手技術者にとって緊張を伴うものです。
- ・自分は間違えたことをやっていないか
- ・自分のやっていることに指摘が入るのではないか
といった心理が働く可能性もあります。
まずは安心させる意味でも、きちんとできていたことはその旨を伝えることが肝要です。
できていないこと、間違えていることを指摘したいのがリーダーや管理職の心情だと思いますが、
否定ばかりされていると、今後も続くであろう立ち合いに対し、
若手技術者が心理的ハードルが構築することになります。
間違えていたこと、不適切な手順等は一通りの立ち合いが終わった後に行う
若手技術者の手順の中には、
間違えていたもの、不適切な手順等が含まれることも珍しくありません。
手順書をきちんと作成したとしても、
このようなミスや誤解等は生じるものです。
これらについてリーダーや管理職は立ち合い中にメモをしておき、
終わった後にまとめて若手技術者に伝えるようにしてください。
指摘する際は感情的にならず、なぜそれが問題かを丁寧に伝える
前出の間違えや不適切手順の指摘を行う場合、リーダーや管理職の中には
- ・何故手順書通りにやらないのだ
- ・何故教えたことを守らないのだ
といった心理により、指摘が叱責になってしまうこともあるでしょう。
特に危険を伴う問題や、何度も同じ指摘をしていた場合、
それは感情的になってでも必死に伝えるべきだと思いますが、指摘については
「感情を抑えつつ、何が問題かを丁寧に伝える」
ことが基本です。
技術評価の経験ある第三者の立ち合いは若手技術者にとっても気づきが多い
技術評価立ち合い時において、
ここまで述べてきたようなやり取りをリーダーや管理職と行うことは、
若手技術者に多くの気づきを与えるのが一般的です。
- ・何故技術評価にこのような手順を入れているのか理解できた
- ・技術評価の手順で、その結果の質と再現性を高めるための要点を理解できた
上記のような気づきが一つで得られれば、
若手技術者にとって大変貴重な経験となります。
技術評価という実務に直結したこのような経験の積み重ねは、
技術者の普遍的スキルの重要な部品である”知恵”の獲得につながります。
※関連コラム/連載
第6回 新人技術者の”知っている”ことが実務で使えない/工場マガジンラック(日刊工業新聞社)
まとめ
技術業務において技術評価はその基本を担うものの一つです。
そして結果として得られるのはデータであり、
そのデータの質と再現性の高さを高めることは、
当該業務を担う技術者の使命といっても過言ではありません。
この価値を維持するには、
結果が得られるまでの工程が妥当かを、
時に技術的な経験を有する第三者目線で確認することが重要です。
特に本技術評価を若手技術者が担当する場合、
経験を有するリーダーや管理職からの指摘は多くの気づきを与え、
しかもそれが技術評価という実務と直結していることから、
知っているだけの知識ではなく、
その知識を活用して実務推進する知恵を身につけるために大変効果的です。
リーダーや管理職は技術系社員としての誇りをもち、
技術的な妥当性を常に最上位概念として持ち、
どれだけ効率を重視した圧力があったとしてもそれに屈せず、
捏造を許さない、技術の本質の砦を守り抜く決意が重要だと考えます。
※関連コラム/連載
第2回 若手技術者が技術の本質を理解していない 日刊工業新聞「機械設計」連載
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: