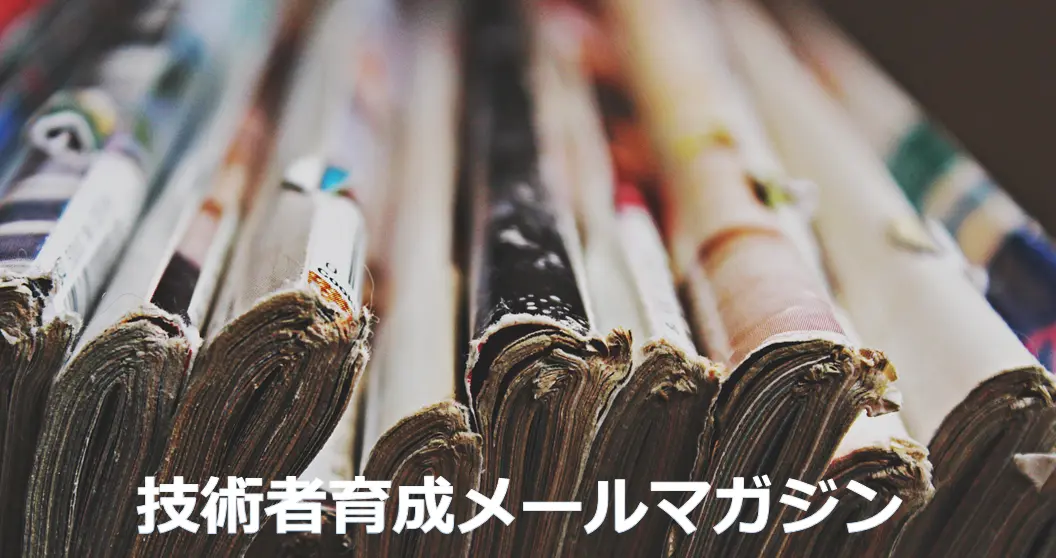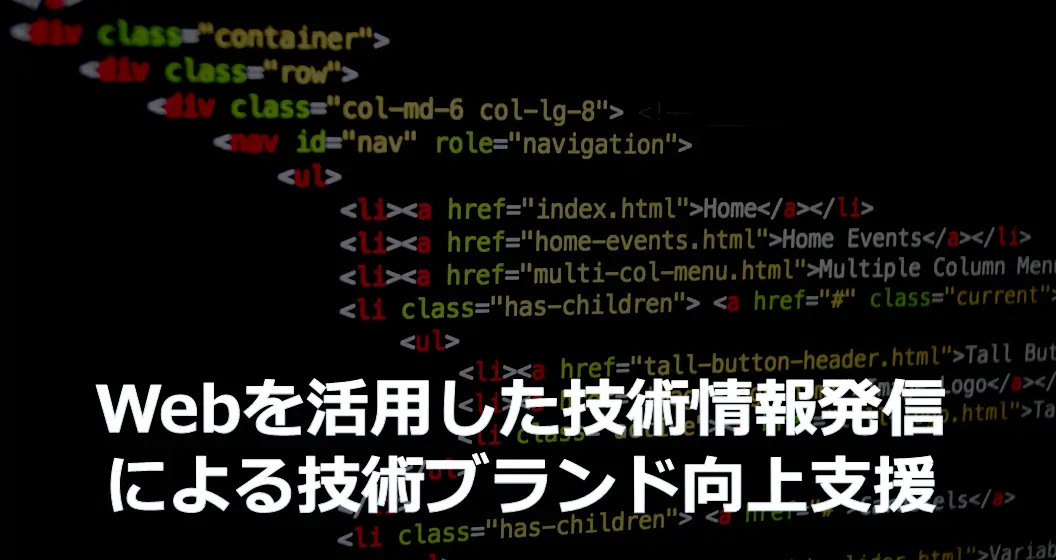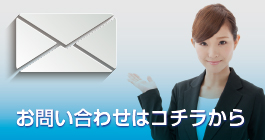Web上の試験データを鵜呑みにせずにやってほしい技術的アプローチ
公開日: 2025年6月30日 | 最終更新日: 2025年7月2日
今回は若手技術者が文献、専門書、特許、Web上の試験データを鵜呑みにしてしまうことについて、
技術者育成の観点での対応を考えます。
どのような試験データも絶対に真実とは限らない

情報化技術が進化した現代、Web上には真偽不明な情報が氾濫しています。
これは試験データのような技術情報も無関係ではありません。
また場合によっては特許はもちろん、
査読のついた文献でも意図的か否かによらず、
誤ったデータが掲載されていることも珍しくありません。
データの改ざんが見つかり、
掲載取り消しになった論文が複数あることをご存じな方もいるのではないでしょうか。
まず技術者は技術データに対して真摯であるべき、
という基本姿勢に立ち返った場合、
自分の手で取得したデータを除き、
その信ぴょう性を疑う慎重さが欲しいところです。
※関連コラム
疑いなく外部技術情報を受け入れてしまう若手技術者
外部の技術データに対して慎重になるのは、
自らが技術業務について最前線である程度の実務経験を積み、
”自分が取得していない”試験データ以外によって問題が生じた、
といった実体験を持った後です。
これに対して若手技術者が上述の経験を有することは少なく、
結果、既述の外部情報に基づいて入手した試験データを、
そのまま受け入れてしまうのは想像に難くありません。
加えて外部情報を活用することは、
試験(実験)の手間もかからず楽であるため、
目先だけ見ればまさに高効率です。
成長を急ぎたい若手技術者にとって効率は大変重要であるため、
手間をかけずに結果を得られるということ自体が魅力的ともいえるでしょう。
※参照コラム
技術的な議論 を避けてしまう技術者が技術的議論をするために何が必要かわからない
Webから入手できる試験データの例
国内外の様々な研究機関等は、
試験データをWeb上で公開しています。
これらの情報が技術の進歩に一役買っているのは間違いありません。
インターネットにより誰でも自由に情報を入手できるのは素晴らしいことだと思います。
ここではWeb上で閲覧可能なSUS304の材料試験データを例に、
リーダーや管理職がデータを鵜呑みにしないよう、
若手技術者に対してどのような指示を出すべきかについて、
適宜事例も示しながら述べてみたいと思います。
※参考情報
SUS304鋼の材料試験データ集 / 核燃料サイクル開発機構
若手技術者がこのデータに触れる一つのきっかけとして、
「SUS304の0.2%耐力に関する特性を調べてほしい」
というリーダーや管理職からの指示が一例であり、
以下はそれ以降の流れについて述べます。
一点ではなく複数の試験データが掲載された情報は貴重
今回例として用いた試験データの中身を見ていただくと、
同一水準で複数のデータが掲載されているのがわかります。
試験データの同等性を見るには、参照元も複数データで構成されていることが望ましいです。
同等性を判断するにあたり、ばらつきを考慮できるからです。
リーダーや管理職はできるだけピンポイントではなく、
複数の試験データが掲載されているものが望ましい旨、
若手技術者に伝えることが肝要です。
例として取り上げる試験データ
前出の参考情報の資料11ページ目(資料内ページ表示でp.9)の表内、
熱履歴と中性子線照射が無く、試験環境温度が20℃という試験片について、
0.2%耐力のデータを取得できている18個のデータを例として取り上げたいと思います。
数値を転載すると以下のようになります。
0.2%耐力(kg/mm2)
-
- 21.9
- 22.0
- 22.9
- 22.0
- 21.8
- 23.9
- 24.3
- 24.1
- 23.1
- 24.8
- 25.8
- 27.3
- 25.9
- 22.9
- 22.9
- 22.9
- 22.4
- 23.1
- 21.9
これらのデータの平均値は23.6、標準偏差は1.6(ともに単位はkg/mm2)です。
若手技術者は調べたデータをそのまま鵜呑みにする可能性
事例として示したデータについては出どころもはっきりしていることもあり、
「調査の結果、上記のような18個のデータをWeb上で発見しました。
平均値は23.6、標準偏差は1.6(ともに単位はkg/mm2)です。」
という報告を若手技術者はするかもしれません。
指示事項に対して若手技術者の対応は間違えていないので、
リーダーや管理職は目標を達成した、
ということをまず明確に若手技術者へ伝えてください。
若手技術者にデータが本当に妥当なのか一度確認してほしいと伝達
リーダーや管理職は若手技術者に試験データの確からしさに関する問題意識を持ってもらう意味で、
「Web上でのデータとはいえ、参照元もきちんとしているので数値として信頼に値すると考える。
一方で本当にこの数値が本当に妥当か否かについて、一度、自分で確認してもらえないか。」
という追加の指示をしてください。
試験機を持っている企業であれば社内で、
それが難しければ最寄りの公的研究機関の試験機を借用し、
「若手技術者に自分の手で設備を動かしてデータを取得させること」
がポイントです。
わかりきっているデータを取得するのは無駄ではないか、と主張する若手技術者も
これは私自身も経験のあることですが、若手技術者の中には
「そんな非効率なことをやる意味はあるのか」
と口に出すか出さないかは別として、そのように考える人もいます。
それ以前に、
「何故データがあるのにわざわざ取り直すのか目的がわからない」
といったことを言う若手技術者もいるでしょう。
このような場合、若手技術者には
「データが本当に正しいか否かは自分で一度確認をする癖をつけてほしい。
ダブルチェックを行うという観点で試験データの信頼性がより高まる。」
と伝えてあげてください。加えて、
「どれだけ信頼に値する試験データであったとしても、意図するかしないかは別として、
正しくない数値や想定外のばらつきを有するといったことが生じる可能性もある。
それは実際に自らの手足を動かさなければわからないことだ。」
という、技術者が理解すべき
「技術は真実」
という信念を理解させることが合わせて重要です。
このような基礎理念の教育は技術者育成で極めて重要であり、
早い段階で若手技術者に浸透させることが肝要です。
これに関連し、過去には技術者の心得としてご紹介したことがあります。
※関連コラム
同等性評価には統計学を使う
実際にデータを取得したら、定性的な評価ではなく定量的評価を実施させることが肝要です。
技術者ですので、同等性を定量的に判断する一手法として統計学を活用すべきでしょう。
より具体的にはt検定が良いと思います。
例えば、実際に若手技術者がSUS304の0.2%耐力に関するデータを自分で取得し、
以下のような結果を得たとします。
0.2%耐力(kg/mm2)
- 24.9
- 23.0
- 20.7
- 23.8
- 21.9
このデータが、参考情報から得られたデータと同等であるかを評価することを念頭に、
以下、検定の手順概要を述べます。
t検定を使えるのはデータの集団が確率密度関数の一つである正規分布に合致しなければならない
いきなりExcelにデータを入力して同等性を判断しようとする方もいますが、
数学的には正しくありません。
技術者として理解すべきは、”正規分布”であることがt検定を行うにあたっての前提になっていることでしょう。
材料試験データの正規分布の確率密度関数に対する適合度検定には、
Anderson Darling 検定が望ましいとされています。
これは、データの端部(評価する数値データの最も大きいものや小さいもの)の検定精度が高いことが理由にあります。
詳細は割愛しますが、参考情報から入手した18個のデータに関する適合度検定のp値は0.054、
若手技術者が取得した事例として示した5個のデータは同0.928でした。
どちらもp値は0.05を上回っており、
個別データの分布が正規分布の確率密度関数と顕著な差が無い、
という帰無仮説を採用できるという判断となります。
ここまで来て初めてt検定を行うことができます。
適合度検定について以下の連載で詳細を述べています。
※関連連載
「 機械設計 」連載 第二十二回 取得したFRP 静的材料データは本当に正規分布として扱っていいのか
分散の同等性をF検定で評価
参考情報で取得した18個のデータと若手技術者が取得した5個のデータについて、
それぞれの母集団が有する分散が等しいかどうかはF検定で評価します。
こちらも詳細は割愛しますが、p値は約0.39(>0.05(有意水準))であり分散は同等と判断されました。
等分散を想定したt検定で同等性を判断
F検定の結果から、2つの母集団(参考情報の試験データグループと若手技術者が取得したデータグループ)のばらつきは同等ということが分かりました。
よって等分散を想定して前述の2つの母集団についてt検定を行いました。
その結果、p値は約0.40となりました。
t検定は二つの母集団の平均に有意差があるかを検定するものですが、
p値が0.05より大きかったことから2つの母集団の間に有意差は無い、
という帰無仮説は棄却されず採用できます。
よって、参考情報のデータと若手技術者が取得したSUS306に関する、
0.2%耐力のデータの分散は同等であるということが言えました(より正確には、同等であるという仮説は採用できる)。
このような一連の手順については、過去のコラムでも取り上げています。
※関連コラム
実際に試験データを取得させた後に聴いてほしいこと
外部情報より入手した試験データと、
若手技術者自身が入手した同データの同等性を判断することについて、
事例も示しながらご紹介しました。
リーダーや管理職はさらに一歩踏み込んで若手技術者に問いかけてほしいことがあります。
それが、
「実際に試験データ取得を行うにあたり、何か気が付いたこと、感じたことはあったか」
ということです。
数値データはもちろんですが、
その数値データを取得する一連の工程について注意深く観察し、
実際に手足を動かした人ならではの視点で技術的なポイントをつかむことが、
技術者にとって大変重要な視点です。
破壊の前に表面に線状模様が発生した(リューダース線)、
ひずみゲージを貼る際、CN(接着剤)を塗り過ぎてしまった、
SS線図が材料によって違いがあった、
といったものが一例です。
このような観点が技術報告書でいうと考察を深めるのに重要であるうえ、
若手技術者に実際の試験(実験)を行うことは、
多くの技術的な気づきを得ることにつながることを体感させることができます。
本コラムに関連する一般的な人材育成と技術者育成の違い
入手情報の妥当性をきちんと検証する、
というのはコンプライアンスの観点からも様々な研修が存在します。
特にSNSを中心とした情報媒体では信頼性に疑問符のつくものも多く、
安易に鵜呑みにしてはいけない、といった注意喚起は、
日常業務の中でも触れる機会が多いかもしれません。
これに対し技術者育成においては”数値”をその対象とすることに加え、
統計学を活用することを重視します。
技術者の普遍的スキルの一つである”グローバル技術言語力”を鍛錬し、
その基本にある数学力を高める視点で統計学に関する知見を深めることを目指します。
本コラムに関連する具体的な技術者育成支援の例
技術者育成コンサルティングとして対応します。
模擬データを用いた正規分布適合度検定、F検定、t検定について、
Excelのデータ分析だけでなく、実際に手計算をベースにデータ分析を行い、
どのような計算を経て検定を行っているのかの理解を深めていただきます。
そのうえで実際に技術データの同等性判断が必要となる場面で、
各種データ分析を行っていただくことを繰り返しながら、
若手技術者の方々が統計学を実業務で自由に使える状態になることを狙います。
まとめ
Web等の外部から取得した試験データは必ずしも正しくない。
合理性や効率に溺れることなく、
技術者は常に外部入手データの妥当性に疑問を持つ慎重さが必要です。
特に今回ご紹介したような自分で同じ試験データを取得することは、
試験中の事象観察をさせるという意味でも若手技術者育成に大変効果的です。
いい意味で疑り深い若手技術者は、
技術データに対して真摯に向き合い、
常に客観的な評価を行うことができる専門家へと成長していくでしょう。
このような技術者こそが、
結果として企業の技術的な発展を実現する源泉となります。
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: