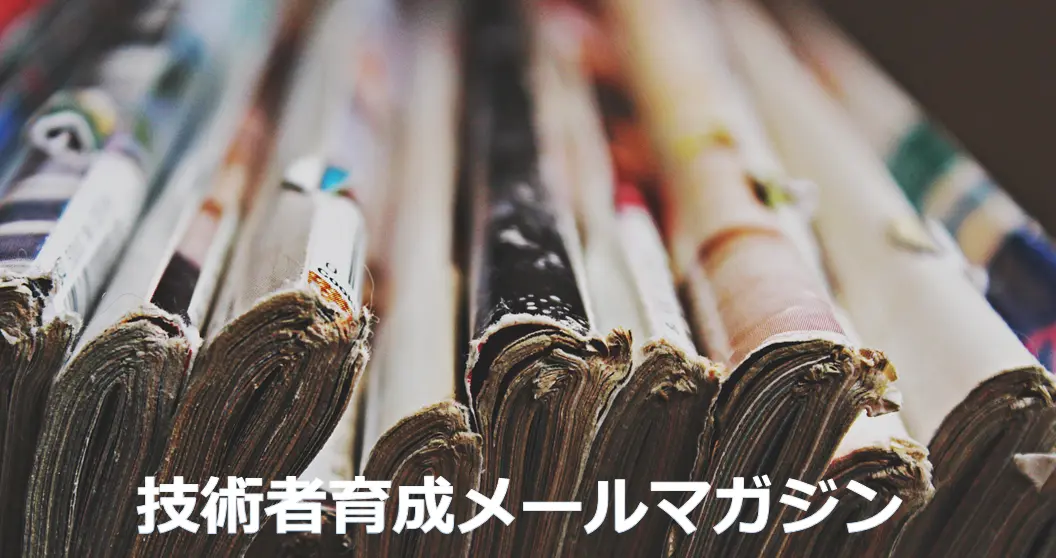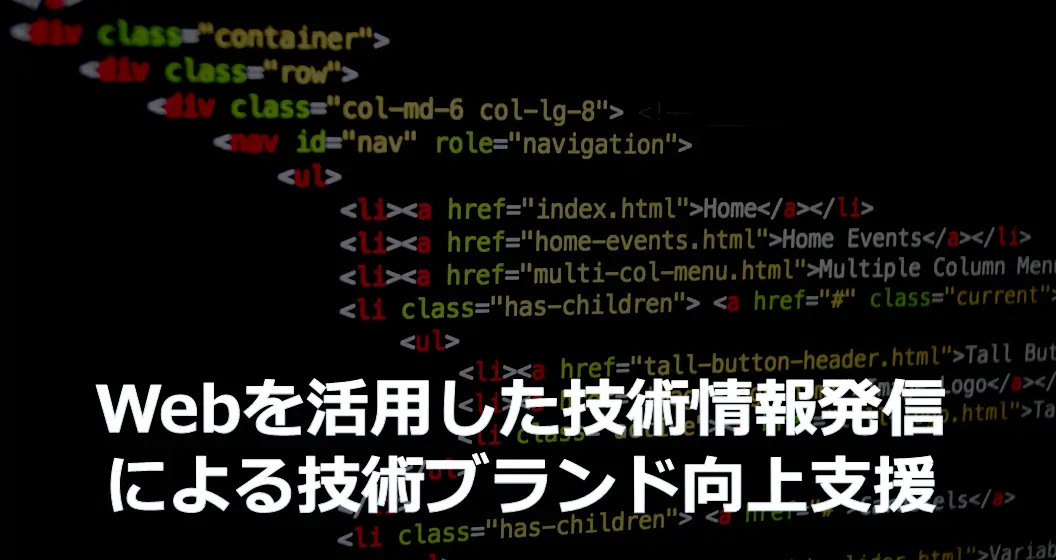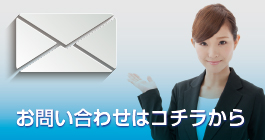研究開発を担当する若手技術者がPCの前に座ってばかりいる
公開日: 2025年5月5日 | 最終更新日: 2025年5月3日
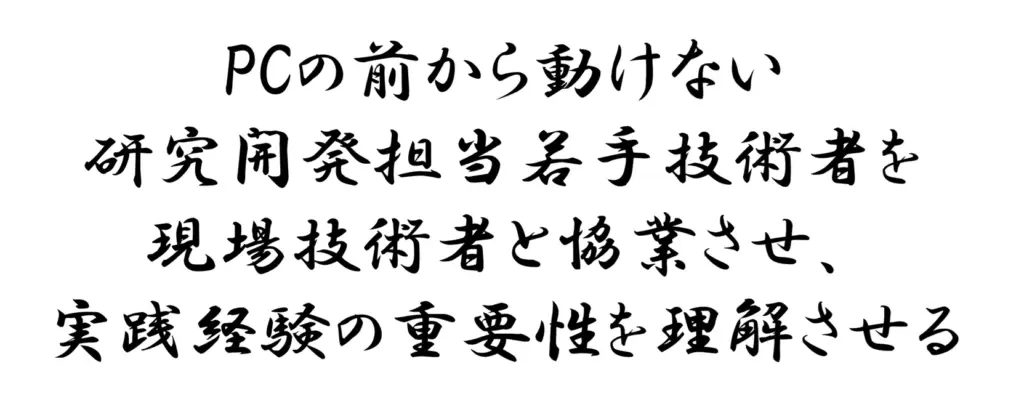
今回は研究開発を担当する若手技術者が現場に行かず、PCの前に座ってばかりいるという状況を改善し、技術者育成につなげるアプローチを考えます。
研究開発の技術者に対する一般的なイメージは定まらない
研究開発を担う技術者についてのイメージは、一般的にはあまり定まっていないと感じています。
関連するものとして、以下のような技術者(エンジニア含む)はある程度のイメージが一般的に浸透していると感じます。
- ・町工場の技術者→下町の中小、零細企業で旋盤加工や板金加工を行う技術者
- ・エンジニア→主にITエンジニアを指し、PCの前に座って仕様書を作成するSEや、その仕様書に基づいてプログラムを組むプログラマー
では、研究開発を担当する技術者というとどのようなイメージでしょうか。
試験管を振っている化学系、計測機器を前に各種機械試験を行う機械系、
培養などを行う生物系など、かなり多様です。
このような業界による違いもあって、
研究開発を担う技術者について一般的に”これ”というイメージを作ることが難しいのかもしれません。
いきなり暴走する or 調べる/考えることに時間を費やしてしまう若手技術者
実務経験の不足する若手技術者が、
研究開発を主業務とするケースを考えます。
そしてリーダーや管理職が何かしらの技術業務に関する指示を出したことを想定してください。
この場合、若手技術者の初動は大きく分けて2通りになります。
何も考えずにいきなり走り出す
業務指示に対し、理解したという旨の返答をし、
ためらいなくすぐに動き始めるのが一つのパターンです。
コミュニケーション力が高く、またフットワークの軽さからリーダーや管理職として仕事を任せやすい、と感じることも多いようです。
ごく簡単な業務であれば特に問題は起こりませんが、
技術業務のうち、ある程度手順を組み立てなければならない場合、
いくつかの問題が生じます。
ここでは問題のうち、代表的なものを一つご紹介します。
求めた結果が出てこない
業務指示の時点で、何が欲しいということを明確に伝えていたとしても、
それと異なるものが出てくるというのが一例です。
例えば化学系の企業を一例として、他社製品の分析を行い、
自社製品との違いを可能性を含めて調べ、
その結果を教えてほしい、という指示を出したとします。
しかし出てきたのは、
他社製品のカタログと自社製品のカタログを単にコピーして貼り付けたプレゼンテーション、
ということもあります。
プレゼンする内容はあくまでカタログ上の比較で、
そこには技術的な知見が含まれていません。
リーダーや管理職は、例えば化学構造でいえばFT-IRやNMR、
場合によっては元素分析のXPS等の分析を組み合わせ、
どこに違いがあるのかを客観的に比較の上で示してほしい、
と考えていたはずです。
一方で若手技術者は、例えば学校などで学んだプレゼンテーション技術に注力し、
さらにリーダーや管理職が何を求めていたのかを確認することの意識が不足したことで、
的を外れた結果を示すことになったといえます。
調べる/考え込むを続け、全く前進しない
調べること、考えることが重要と信じる若手技術者に見られる応答です。
学業的に言うと優秀といわれる部類に入る若手技術者に多いかもしれません。
指示を細かく伝えればそれに基づいて丁寧に進めることができ、
また自己完結しようと業務に取り組む当事者意識を持っているため、
途中で投げ出すといった雑さもありません。
しかしこのタイプの若手技術者にも課題があります。
自己完結しようとしすぎて前進がない
自己調査を行うといったことはもちろん重要ではありますが、もっと重要なのは
「リーダーや管理職が求めるものを正確に理解し、そのために必要なことを前進しながら明らかにしていく」
という思考錯誤を通じた実践経験です。
前進しないことには何も始まらないのです。
PCの前で検索をする、生成AIからの返答を見るといったことを繰り返していては、
リーダーや管理職から見ると進捗ゼロの状態が続いていることと変わりません。
スタートダッシュ型と立ち止まり型はどちらも問題だが、後者の若手技術者の方が多い傾向にある
前出の2例はどちらも偏りが出ているという意味で、
若手技術者の状況改善に向け、
リーダーや管理職は何かしらの対策を打たなければなりません。
ただ、私が様々な技術者を指導してきた経験から言うと、
どちらかというといきなり走り始めるタイプよりも、
なかなか動かない若手技術者の方が多いと感じます。
大学の研究室生活の中で自己完結で研究テーマを進めることを求められたことが、
その背景の一つにあるのかもしれません。
技術者育成の観点からは自己完結したがる特性のすべてを否定はできませんが、
「PCの前に座っている」
と外から見えることは、特に若手技術者のうちは望ましいことではありません。
その理由は2点あります。
どれだけ調べても、どれだけ考えても、一つの失敗を含む技術業務の実践経験には及ばない
1点目は実践経験の重要さです。
若手技術者の成長につながるものとして、調べること、考えることは一要素ではあります。
しかし、どれだけ調べても、考えても、本当の意味の成長にはならないのです。
それは、
「自分の手足を使って実行に移さないと知識が”知恵”にならない」
からです。
知識は知っているという状態です。
そして、知恵というのは知識を活かしながら、
実践的な行動まで結び付けるために必要なことを頭の中で画像化し、
その画像に基づいて実行することができるものです。
知恵を獲得するには、当事者意識を持ちながら実践経験を積むしかありません。
その経験の中で失敗が含まれているとよりいいでしょう。
あのような失敗は二度としたくないという強い意識こそが、
知識を用いた試行錯誤の経験を知恵に換える原動力となります。
※関連コラム/連載
若手技術者が成果を出すための 技術的経験蓄積 に向けた動きの最優先事項が何かわからない
第6回 新人技術者の“知っている”ことが実務で使えない 日刊工業新聞「機械設計」連載
一人で完結しようとせず、実行力のある技術者と連携する
2点目が自己完結にこだわらず、周りと連携する必要性に対する理解です。
若手技術者の多くは専門性至上主義を有していることもあり、
「自分で仕事を完遂したという達成感への飢え」
があります。
この心理はすべてが悪いわけではありませんが、
若手技術者一人ができる業務範囲や業務推進スキルはそれ相応でしかありません。
とはいえ、その事実を若手技術者が認めることは難しいでしょう。
自尊心が低く、認めるだけの余裕が無いためです。
ここで若手技術者が気が付くべきは、
「実行力のある技術者と連携する」
という考え方です。
自分一人で抱えず、できない部分を相手に依頼し、
お互いに連携しながら前進する”選択肢”に気が付くことが重要です。
若手技術者が実践経験を獲得し、
実行力のある技術者と連携させるため、
リーダーや管理職はどのような対応を取るべきでしょうか。
現場作業を行う技術者と交流を持たせる
結論からいうと、
「若手技術者と現場作業を行う技術者との間で交流を持たせる」
ことです。
研究開発を担う若手技術者は、機会が無いと現場の技術者と関わることが少ない場合もあります。
現場の技術者との協業は後述する通り知恵のイメージを獲得する効果が期待できるため、
リーダーや管理職はその機会創出の取り組みを進めるべきです。
現場作業を行う技術者は実践経験の積み方の良き手本となる
生産現場や試作設備で現場作業にあたる技術者は、
多くの実践経験を持っています。
このような技術者は実践経験を積むことの重要性を理解し、
そして多くの知恵を有しています。
若手技術者がそのような技術者と一緒に仕事をするだけで、
多くの気づきが得られるに違いありません。
若手技術者がPCの前に座るよりも、前線に出て手足を動かすことで得られる情報の多さに気が付くことができれば、それは将来的に知恵を獲得する第一歩を踏み出したことと同等といえるでしょう。
現場の技術者と若手技術者の協業を実現させるため技術業務を企画する
現場の技術者は多忙です。
そこに若手技術者が突然現れても、
相手にしてもらえないでしょう。
ここでリーダーや管理職による”地ならし”が必要となります。
具体的には、
「現場の技術者と研究開発を担う若手技術者が、”一緒”に現場作業を行う技術業務を設定する」
です。
ポイントをいくつか述べます。
技術業務はあまり大きなものを選ばず、当該業務の目的と目標到達点を明確化したうえで企画化する
現場の技術者にとって、若手技術者との協業は追加の工数になります。
そのため、研究開発を担う若手技術者を送り込むリーダーや管理職は、
若手技術者がぶれなく技術業務を完遂できるよう、
事前準備をすることが求められます。
技術業務そのものは、あまり大がかりにする必要はありません。
例えば、量産設備を使ったデータの取得が一例です。
量産機を使って、新開発した材料を製造するにあたり、
現行製品と比べて過大な圧力がかからないか、
温度異常が生じないか、といった点を確認する、
といったものがその一つです。
この場合、実際に若手技術者が現場技術者と会話をする前に、
- ・何故、このデータを取る必要があるのか
- ・データを取得することで到達したい目標は何か
を明確化することが必須です。
上記の2点を明確に盛り込んだ書類をリーダーや管理職が主導し、
若手技術者に作成させ、それを支援します。
本書類は技術評価計画に該当します。
※関連コラム
一連の流れはまさに技術者の普遍的スキルの一つである、
企画力を活かした業務となります。
どのように企画を進めるかについては、
過去にコラムや連載で触れたことがあります。
※関連コラム
第12回 技術テーマ立案に不可欠な技術者の「企画力」鍛錬の勘所 日刊工業新聞「機械設計」連載
リーダーや管理職が若手技術者を連れて現場技術者との顔合わせの機会を構築する
実際に現場の技術者に何かしらの業務を依頼するにあたり、
いきなり若手技術者が企画を持ち込むというわけにはいかないでしょう。
既述の通り、現場の技術者は定常的に推進すべき業務を抱えているためです。
よって、リーダーや管理職は企画ができた段階で、
現場の技術者を管理する管理職に相談を持ち掛けるのが一般的です。
「このような技術業務を行うにあたり、現場の技術者の力を借りたい」
という打診です。
許可が下りた後は、若手技術者を引き連れて現場技術者と顔合わせをし、
実際に行う業務を企画書をベースに若手技術者に説明させ、
リーダーや管理職は適宜補足をするという打ち合わせを行います。
このような段取りを通じ、現場の技術者が若手技術者を受け入れる準備を整えます。
現場の技術者との協業の後、若手技術者にヒアリングを行う
業務終了後、リーダーや管理職は若手技術者から技術業務の報告を受けることに加え、
「現場の技術者との協業を通じ、何を感じたか」
という点を中心にヒアリングを行ってください。
その中で、
「実際に技術業務を実践することで得たもの」
をうまく引き出せれば、一連の取り組みが若手技術者の知恵獲得に向けた、
技術者育成の効果を得られたと判断できます。
技術業務の企画、現場の技術者と若手技術者の協業、
若手技術者へのヒアリングは一回だけでなく、
複数回繰り返すことが肝要です。
これにより、若手技術者は現場の技術者と自然に協業できる雰囲気が醸成されていきます。
まとめ
調べるだけで前に進まない若手技術者には、
技術業務の実践経験を通じた知恵獲得の重要性を理解させることが肝要です。
その際、技術業務実践のプロともいえる現場の技術者との協業を後押しすることは、
知恵に関する理解を深めると同時に、
一人ではなく複数の技術者と連携することの重要性を体感させる意味でも、
若手技術者に多くの気づきを与えるきっかけになると期待できます。
技術業務の企画立案支援と現場との調整を行い、
現場の技術者と若手技術者が顔を合わせる機会を設定するという、
人脈と経験を有することの強みでリーダーや管理職は若手技術者をけん引してあげてください。
このような取り組みが、将来的な若手技術者の成長の糧になるに違いありません。
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: