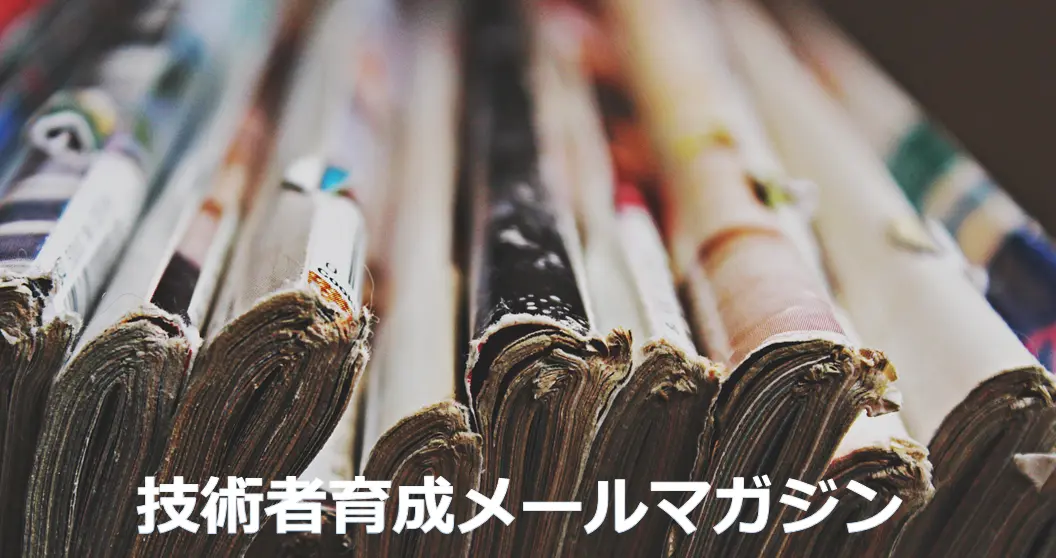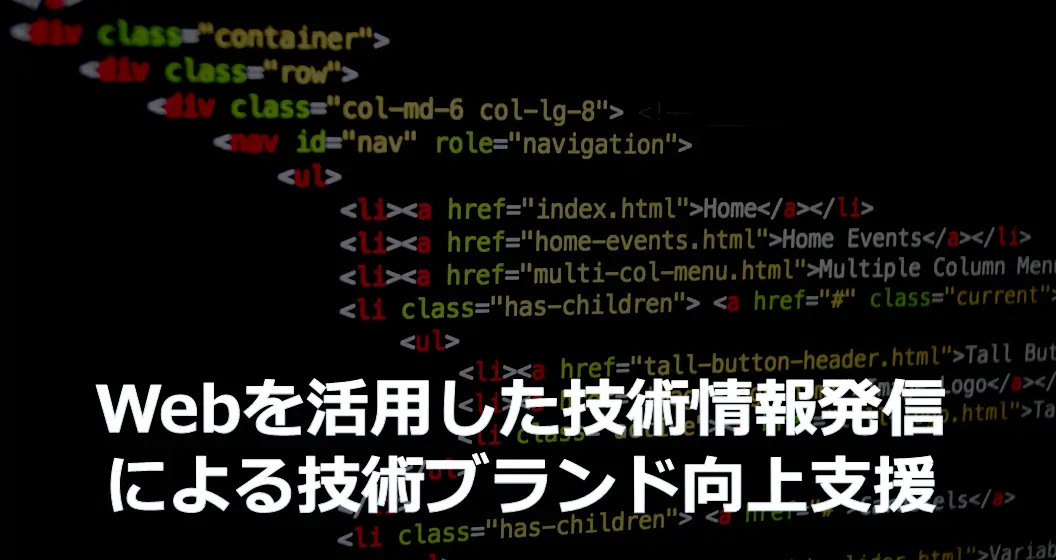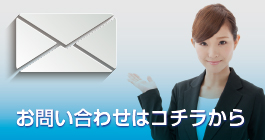伝統と先端の両立を狙う進学高校での教育を若手技術者育成の類似点
公開日: 2025年9月8日 | 最終更新日: 2025年9月8日
タグ: できる技術者をさらに伸ばす, メールマガジンバックナンバー, 専門知識, 技術者の上司とは, 技術者の普遍的スキル, 技術者人材育成, 若手技術者の指導者, 高校
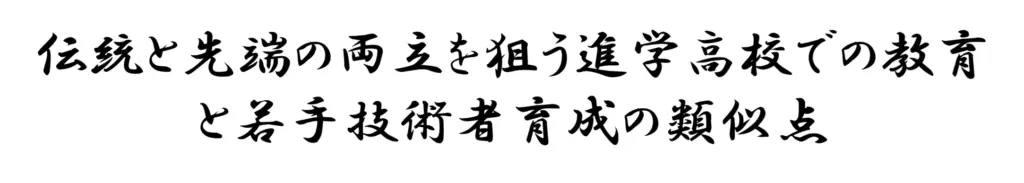
創立100年を超える屈指の公立進学校(高等学校)の授業を拝見する機会を頂きました。
Webや生成AI、伝聞ではなく、自らの目で見てみたいという願いがかなった形です。
今回は特別号として、伝統と先端の両立を狙う進学高校教育の技術者育成への応用の可能性について述べたいと思います。
高校教育の見学のきっかけから入り、
そこで見た技術者育成の類似点について述べます。
高校教育への興味を持ったきっかけ
これまで様々な形で技術者育成について取り組んできました。
指導に対する濃淡はありますが、
大きく成長した技術者から成長に時間はかかるものの着実に成長する技術者、
そして残念ながら成長があまり認められず離脱してしまう技術者まで、
様々な方がいました。
中長期で支援する企業を中心に最終的にはある程度個々人に合わせた支援を行うものの、
視点を自分自身の技術者としての経験も踏まえて現場に寄せながら、
可能な限り具体的な技術者育成の取り組みを伝えても、
思った以上に行動ができず、応答が小さい若手技術者が一定数いると感じていました。
技術者育成と学校教育の共通点に興味を持った
ここで私が持ったのが、
「技術者育成と学校教育に共通点は何かないか」
という疑問でした。
何故ならば学校教育の現場では、
今当社を通じて私がやり取りする社会人ではなく、
社会人経験がなく、人格形成も途中の児童、生徒です。
どのような技術者もそのような教育を経て会社に入っているはずであり、
その現場を見ることで
「こうすると成長に導く内容がより伝わる」
といった糸口をつかめるのではないかと考えたのです。
先生方は成長途中の多様な人間を相手にしているはずで、
それは技術者育成という一種の教育に携わる者から言うと大変高度なものです。
そのような教育現場と企業の技術者育成の現場での共通点を見いだせれば、
それは一つの”本質”であり、当社としても理解することで技術者育成の精度向上につながり、
同時に技術者育成に興味をお持ちの方々にも知っていただく必要があると考えました。
なお、私自身は大学の非常勤講師は10年以上やっていますが、
それ以外にも小学校の特別授業をするなど、
教育現場から学ぶことは継続しています。
※関連コラム
より専門的な教育を行う高校の教育現場を知ることは専門教育が含まれる技術者育成と近い
今回は小学校から学年を上げ、高等学校(以下、高校)での教育現場を見させていただきました。
主たる理由は、
「技術者育成は大なり小なり技術専門的な教育の側面もあり、
より高度な専門教育を行う高校の現状を知りたい」
ことにありました。
専門的な教育の色が出始める高校での教育は、
技術者としての道を歩み始める第一歩の位置といえます。
今回は縁あって歴史が長く、かつ屈指の進学実績を誇る公立高校の教育現場を拝見する機会をもらいました。
複数のクラスを見ましたが、理系クラスだけでなく文系クラス、
さらには文理が分かれる前の学年のクラスもその対象でした。
授業の概要
今回見ることができたのは、数学、物理、英語、古典の4つの科目でした。
科目や担当の先生による違いもありましたが、
その学校の教育方針のためか共通している部分もありました。
本共通点の要点は、
- 成長に関する天井と壁の撤廃
- 議論の徹底
- 試行錯誤
- 実験(実証)を主とした理論の裏付け
- 指導者の自己研鑽
の5点です。
それぞれについて概要と技術者育成との類似点を述べます。
なお、以下では数学と物理に関する内容を主としますが、
他の科目と共通する部分が多かったことも追記しておきます。
成長に関する天井と壁の撤廃
通常の授業は先生が説明をし、それを生徒が聴くというスタイルだと思います。
多くの授業で共通していたのは、
「予習(準備)が前提」
ということでした。
準備なき授業は授業ではない、
という姿勢を強く感じたと言い換えることができます。
宿題はいきなり前で答えを貼り出し、理解している生徒は先に進ませる
ある授業では宿題が出ていたようで、
先生はいきなりその答えを前に貼り、
「既に解が出ている者は前に出て答え合わせをしなさい」
と発言をしました。
すると当たり前のように既にできている生徒は前に出て自らの答えと比較する、
後ろの席の子は見にくいためスマホで答えを撮影した後、
自分の席に戻って答え合わせをしていました。
ここで感じたのは、
「既に内容を理解し、前に進める生徒はどんどん進ませる」
という”できる者をさらに伸ばす”という姿勢でした。
今回そのような質問は出ていませんでしたが、
恐らくさらに先に行けるような生徒は、
「今回の内容理解を深める、他の応用問題を出してください」
と言ったのではないかと想像します。
準備できていない生徒に挽回する機会を与え、置いていかない
できる生徒をどんどん引き上げる一方、
準備できていない生徒や躓いている生徒を置いていくということもしませんでした。
例えば前出の授業では答えを貼りだした上で、
「今回の問題を解けなかったものはこちらを見てくれ」
という形で板書しながら、回答にたどり着くのに必要な内容の解説をしていました。
分からない生徒はそちらを見ながら問題に挑戦していました。
別の授業では、
「予習をできなかった人は、今から1分上げるので内容を読んでください」
という形で、厳しい時間制限はあるものの挽回するチャンスを与えていました。
遅れそうな生徒を置いていくということはせず、
しかし挽回にはある程度のプレッシャーをかけるということをうまく行っているように見えました。
”成長に関する天井と壁の撤廃”に関する技術者育成との類似点
技術者育成の本質ともいえる部分で一つ類似点を見出しました。
それが、
「模範となる技術者を優先的に伸ばす」
ことです。
技術者育成は”できる技術者”や”成長の早い技術者”を抜擢し、
その技術者を目指すべき一つの形にすることが大変重要です。
このようにして成長した技術者は、
「技術者育成の新たな模範として他の技術者の成長を促す」
という役割を果たすのです。
当社のように外部から指導する場合の鉄則であると同時に、
社内で推進するとしても”能動的”に成長する流れを作るには不可欠な戦略といえます。
技術者育成は上から教えるだけでなく、
見本となる人材を育て、それを波及させるという流れの構築が大変重要となります。
技術者の成長には天井を設けず、
徹底して伸ばし、その成長を周りに波及させるのは、
見学した高校の授業でも生徒同士が教えあう姿を見て技術者育成と同じと感じました。
追記すべきこととして、リーダーや管理職は若手技術者が自らを超える、
または理解できない領域に到達することを恐れてはいけません。
自分が常に上にいなければならないとリーダーや管理職が考えるのであれば、
それ自体が現場の技術者の成長を低下させる重しとなります。
※関連コラム
技術力は高いがまとめる力、伝える力が弱い技術者をどう生かせばいいかわからない
議論の徹底
見学した高校の授業において、
科目に関わらず行っていたのが、
「問題について周りの生徒と議論する」
ことでした。
答えを解説して終わり、ではなく、
「答えを導き出す経緯、自分のできたところと、クラスメートのできたところ、
逆にそれぞれができていなかったこと」
を生徒同士で確認させていました。
自らの考えたことを他の人と議論する。
このようなアクションを通じ、
授業内容の理解を深め、
お互いをお互いにフォローする形を作っていると感じました。
”議論の徹底”に関する技術者育成との類似点
技術者育成において、
「技術的議論は不可欠」
というのが私の信条です。さらに言えば私の中では常識の中の常識です。
技術業務に限らず、業務全体について効率化の流れは当然かと思いますが、
「技術者を育成したいのであれば、技術議論に効率という考え方は絶対に入れない」
ことの徹底が不可欠です。
技術的な内容を突き詰めたいという軸から外れていないのであれば、
時間制限を設けず、時間が無いのであれば他に時間を設定して議論すべきです。
技術者は技術的な議論を通じ、
- ・自らの考えや結果に対する解釈に誤りは無いか
- ・逆に周りとの違いを踏まえ、本当に自分が間違えているのか、実は回りが違うのではないか
という思考的労力が、”技術者としての成長の源泉”です。
議論ができない技術者は必ず伸び悩みます。
そして、それを良しとしないリーダーや管理職がいる技術チームは必ず地盤沈下を起こすのです。
技術的な議論に慣れていないと、
突発的に生じた技術的課題や技術ニーズに応えるための技術的基礎が無く、
かつ当該理論を通じた周りとの協業ができないため、
対応しきれずに右往左往してしまうからです。
今回見た授業でとても印象的なのが、
先生方が生徒同士で教え合うだけでなく、
議論することを促す姿勢でした。
これは私が技術者育成で重視するそのものであり、
高校教育でも共通していることに嬉しさを感じました。
議論の誘発は教科書に誘導されたものではない
ここで一つ追記すべきことがあります。
教科書に議論するよう書かれているのではなく、
先生が問題を考え、それの答えを導き出すにあたっての経過を中心に議論を促している点です。
昨今の教科書が誘導する”主体的学び”とは別物です。
教科書に書かれている時点で、それは”受け身”であり、主体的学びではありません。
教科書の理解を進めながらも、
さらにその奥にある部分に興味を持つよう問題を設定し、
生徒同士で議論させるという先生の姿勢は、
技術者が実験や試験で得られた現象が何なのかを突き詰めるため技術者同士で議論する、
技術者育成御本質と極めて似ていると感じました。
これを実現させるためにも、
リーダーや管理職にも技術的議論を受け入れる基本姿勢が必要です。
若手技術者から相談を受けた際、
技術的議論に向けた理解について自らの手間を惜しんで資料を作らせるというのは、
当該議論を抑制してしまう悪習慣の一つといえます。
リーダーや管理職は避けなければならない技術的議論と対極にある対応です。
※関連コラム
試行錯誤
授業中で何度か先生から出ていた発言が、
- ・あくまで回答に示したのは一例なので、他の解き方があるかを考えること
- ・実験で見られた現象を、どうすれば説明できるか自分なりに整理すること
といった趣旨のものでした。
共通するのは”試行錯誤”でしょう。
効率よく答えを出すのではなく、途中の思考を厚くし、
- ・代替手段の探求
- ・現象の解釈法の検討
を促しているといえます。
”試行錯誤”に関する技術者育成との類似点
技術者育成において、若手技術者のうちに試行錯誤することの重要性は何度も述べています。
うまくいった経験よりも、
思ったようにうまくいかずに失敗する、痛い目を見る、
しかしそれをあきらめずに試行錯誤しながら乗り越える、
または乗り越えようと全力を尽くすことこそが、
技術者育成において最も効率的なOJTです。
実験や試験を行って終わりではなく、
事実(技術報告書内の”実験・試験”と”結果”)を正確に記述できるという前提は有りますが、
技術報告書の考察項で”試行錯誤”して具体的な推測の実証法を提案させ、
それを実際にその成否を仮に無駄だとリーダーや管理職が思っても、
手を出さずに一度やらせるのが一例です。
※関連コラム
実験(実証)を主とした理論の裏付け
これは昨今の授業では当たり前になっていますが、
動画を活用した授業も見られました。
次に行う実験に向けての授業だったため、
動画を使用し、どのような現象をとらえる実験かを説明していました。
そして興味深かったのが、
「実験内容に関連する重要理論に言及した学術論文を共有する」
という取り組みでした。
実際にどのような内容の論文なのかは見ることはできませんでしたが、
教科書だけに収まらず、論文を使って理論を理解させようという姿勢に感銘を受けました。
”実験(実証)を主とした理論の裏付け”に関する技術者育成との類似点
技術者の普遍的スキルとしても紹介している通り、
技術者にとって技術的理論は絶対不可欠です。
感覚論、定性的内容ばかりに依存するのであれば、
そもそも技術という名前の付く職種である必要はありません。
技術者が技術的理論を手放すことは最強の武器を捨てることと同意です。
実験や試験で得られた結果が想定外だった時、
それを単なる実験失敗と見るのか、
起こった事象を説明できる何かしらの技術的理論は無いのかを考えるのでは、
技術者としての成長スピードに雲泥の差が出るであろうことは、誰の目にも明らかです。
市場問題の原因究明にも同じことが言えるでしょう。
技術理論の大切さを理解する取り組みとして、
技術者育成では数学を重視しています。
技術者育成は多様な技術領域をカバーするため、
多くの業界に共通する理論は多くありません。
しかし数学だけはほぼすべての業界に共通する技術領域であり、
それ故、技術者の普遍的スキルとして数学力を土台としたグローバル技術言語力を提唱しています。
技術理論に対する真摯な姿勢は、
感覚論や定性的議論から脱し、
技術者が技術という強みを持って成長するのに不可欠です。
※関連コラム/連載
Web上の試験データを鵜呑みにせずにやってほしい技術的アプローチ
第18回 若手技術者が数値データの相対比較ができない 日刊工業新聞「機械設計」連載
指導者の自己研鑽
授業を行うのは高校の先生でしたが、
学会での近年動向を述べる等、
学術界の状況を追っている故の発言が複数見られました。
マスメディアの情報ではなく、明らかに学術業界での話でした。
私自身も複数の学会に入り、また参加していますが、
昨今の学会での流れを踏まえても比較的新しい情報を取っていると感じました。
例えば授業中に、実験で得られる結果を使ってどのようにグラフを描写するかについて、
その記載方法や結果の見せ方について、
「最近の学会ではこのような描写方法が好まれる傾向にあるので、
そちらに合わせてまとめてみましょう」
といったかなり具体的な例を用いた指導を行っていました。
また生成AIの活用について、
それ自体の使用は問題なく、かつ”推奨できる”という話の後、
「生成AIで得られた結果を考察に書くのだけはやめましょう。
昨今、学会の先生方とも話していますが、生成AIの作成する考察の方がうまくまとまっており、
人がきちんと描いた考察の方が感情が入るなどしてバランスが悪いこともあるくらいで、
区別がつかないというよりも、人の書いた考察評価を低くしてしまう恐れがあります。」
との説明がありました。そのうえで、
「当然、生成AIが正しいかどうかの確認を行うのは当然ですが、
いずれにしても今回のレポートでは生成AIがうまい答えを出す可能性のある考察の評価配分を下げる予定です。
きちんと考察を書いた生徒の評価を下げてしまうリスクは取りたくないからです。」
とのことでした。
間違いなく先生方も勉強し、
生徒には最新の情報も踏まえ、
学問的に成長するには何が必要かをきちんと伝えている印象でした。
※関連コラム
”指導者の自己研鑽”に関する技術者育成との類似点
リーダーや管理職の自己研鑽と結びつけるとわかりやすいかもしれません。
技術者育成は、その対象は若手技術者を中心とした現場の技術者達です。
当然、彼ら彼女らの成長を促すことを最優先としますが、
見落とされがちなのが、
「育成対象の技術者は、自らのことを棚においてどのような指導者かをよく見ている。」
という事実でしょう。
- ・ 現場の技術者には厳しい要求をする一方で、当該技術者の担当する技術業務のフォローをしない。
- ・ 指導内容に常に武勇伝を中心とした昔話が追加され、しかも同じ話ばかりで聴いている方は辟易している。
- ・ 外部の技術情報にうとく、現場の技術者が述べる新しい技術情報に興味を示さない。
上記のような言動は、成長が止まってしまっているリーダーや管理職の一例です。
このような言動をするリーダーや管理職が技術者育成に取り組んだとしても、
「成長をしようとしない上司のもとでは自分も成長できないだろう」
という若手技術者の不安が成長したいという意欲に勝り、
結果として技術者育成はうまく機能しないことが多いのです。
リーダーや管理職が技術者育成に関わるにあたっては様々な研鑽項目がありますが、
まずは技術報告書や議事録の添削から始めるというのが一案です。
人の文章を添削することは、結果的に添削者側のスキルを上げるため、
現場の技術者を育成しようとする姿勢さえ維持できていれば、
必然的に添削者も成長します。
そして熱心に育成に取り組むという姿勢こそが、
若手技術者との間に信頼関係を構築するきっかけになります。
※関連コラム
最後に
今回は特別号として、
伝統と先端の両立を狙う進学高校での教育を若手技術者育成に応用できるかについて、
技術者育成との類似点に触れながらご紹介しました。
技術者育成を紐解いていくと、
必ず学校教育に行きつく部分があります。
私自身も今回の高校の授業見学での気づきもありましたが、
まだまだ技術者育成についてわからない部分もあります。
引き続き、企業での教育だけでなく学校教育の生の情報を入手しながら、
技術者育成理論の強化を進めていきたいと思います。
※関連コラム
これからの技術者に必須の思考型教育とは
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: