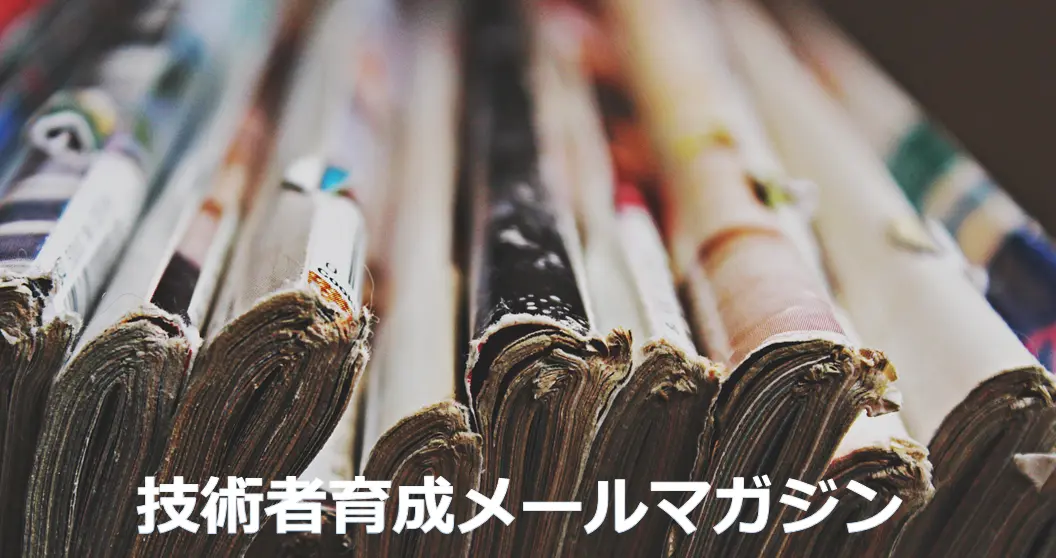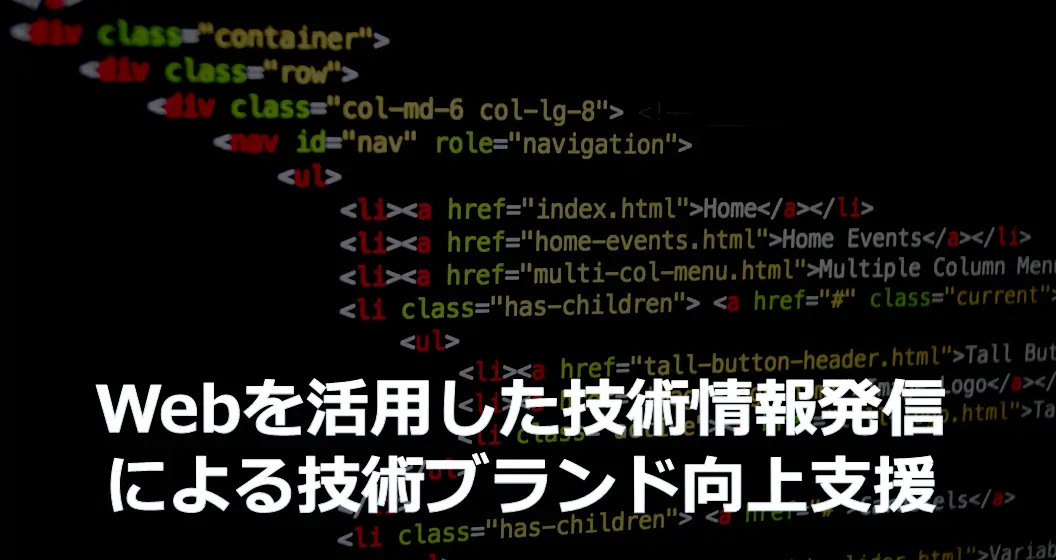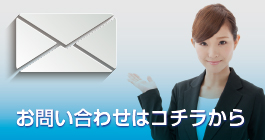Web調査と生成AIを組み合わせた技術情報は若手技術者の成長には直結しない
公開日: 2025年8月27日 | 最終更新日: 2025年8月27日
タグ: OJTの注意点, イノベーションと企画力, メールマガジンバックナンバー, 技術者人材育成
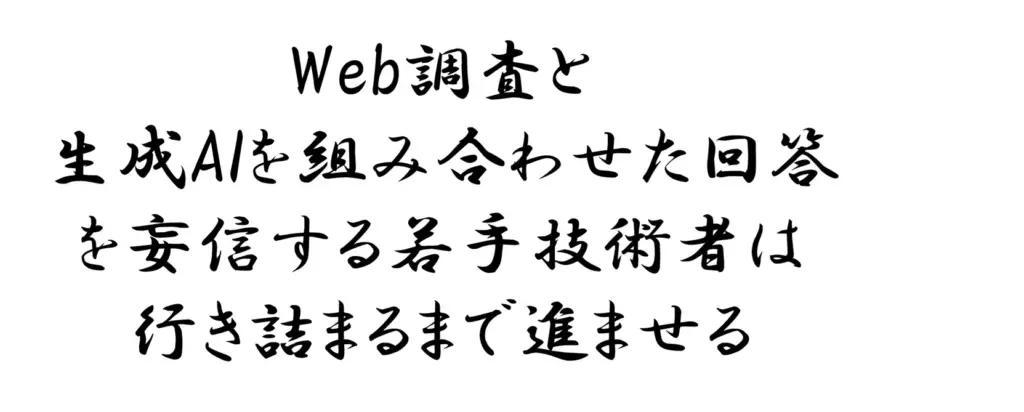
Webによる技術情報の入手性に加え、最近は生成AIも進化したため、
経験の浅い若手技術者であってもあまり苦なく技術資料の作成や議論の足掛かりができるようになりました。
この状況は決して負の側面ばかりではありませんが、
技術者育成でいうとマイナスの印象の方が強い、
というのが私の見解です。
今回はWeb調査や生成AIの回答をベースに、
技術専門に関する質疑を望む若手技術者の育成について考えます。
若手技術者の専門性至上主義の表現が近年変わりつつある
若手技術者を含む多くの技術者が専門性至上主義を有している、
という状況は昔からあることです。
しかし近年、特に生成AIが本格普及してから当該主義の表現方法が大きく変わってきたと感じます。
技術文書読解力と技術選定力の不足を補う生成AI
Web調査しかできない頃は、それらの情報から適切な技術情報を抜き取り、
相応にまとめるには各情報を読み解く技術文書読解力と、
どの技術が必要かという技術選定力が必要でした。
そのためこの辺りの力量を試す問いかけを行うことで、
簡単に仮面が剥がれました。
しかし生成AIによってこの状況が大きく変化したと感じています。
質問を投げかけるとそれに対して回答するだけでなく、
必要な技術情報を調査の上で、
さらにそれを分かりやすくまとめることまでできるようになったためです。
結果として、
「ある程度の技術的な知見を有し、
そして何より相応の技術的実務経験がある”風の”回答を導き出せる」
ようになったのです。
これは若手技術者だけではありませんが、
近年、技術者全般に感じていることです。
技術的に価値のある知恵のレベルにあるか否かの判断には判断する側のスキルが必要になった
前述のような状況になった結果、
例えば何かしら技術的な議論を行うにあたり、
若手技術者が本当に理解して発言をしているのか、
それともWeb調査と生成AIを組み合わせた結果を言っているだけなのかを見分けるのが難しくなりました。
後述の通り、判断する側が技術的な実務経験を有しているのであれば見分けることはさほど難しくありませんが、
異業種協業を念頭に他の技術領域に関連した議論となると、
必ずしも判断する側となるリーダーや管理職に必要な知恵や経験があるとは限りません。
若手技術者や該当する専門性の無い技術者が専門性至上主義を発揮しやすい時代となった
ここまで述べてきたような経緯により、
実務経験がそもそも少ない若手技術者や、
該当する技術領域に専門性を有していない技術者が、
専門性至上主義を発揮しやすい時代になったとも言えます。
自尊心の低い若手技術者にとっては一見すると良い時代かもしれません。
ただ残念ながらそれだけで本当の意味での技術者としての成長と、
その先にある成果を得ることは難しいでしょう。
その理由をいくつか述べます。
身分不相応な技術専門的な知見は様々な問題につながる
当たり前といえば当たり前ですが、
本来技術業務の実務経験を積み、
失敗を繰り返しながら得るべき、
「実践力を伴う”知恵”が無い状態」
で、
「入力しただけ得られる技術情報を適切に取り扱う」
ことは、
「絶対に不可能」
です。
製造業における技術専門性は既に何度も述べている通り”知恵”が最重要であり、
本人しか知りえないような唯一無二の成功と失敗の経験、
その中での試行錯誤という技術者の歩みがその基礎にあります。
知恵こそが技術情報を技術業務に実践するために不可欠なものです。
技術情報の取り扱い方法もわからない若手技術者が、
当該情報をベースに専門性至上主義実現に向け、
乱用することは様々な矛盾が生じるでしょう。
以下のようなものは代表例です。
実現不可能なアプローチ
生成AIには実務経験はありません。
理屈の上で不可能なことをあたかも可能であるように述べることもあります。
原理原則に則っているか否かも分からない若手技術者では、
実現不可能な手法を堂々と提案することもあるでしょう。
本来の趣旨からずれたべき論への執着
研究開発を中心に、技術業務では今目の前にある様々な技術課題を解決、または改善するための技術情報が求められます。
これに対してWeb情報を基本に生成AIが作成する情報は、
一般論であることが多く、実際の要望に基づいたものでないことも多いのです。
しかし知恵を有さない若手技術者は生成AIがすべてという妄信に近い状態に陥ることも多く、
それ故にAIによって生成されがちな技術情報、つまり”べき論”に執着することもあります。
技術実務推進において若手技術者のべき論への執着は、
百害あって一利なしといっても過言ではありません。
Web情報とそれに関連する生成AIの活用は若手技術者中心に今以上に浸透していく流れは変わらない
良い悪いという話ではなく、
生成AIは様々な形で浸透していくことは間違いないでしょう。
ここまで述べてきたような状況や課題の発生は、
遠い未来の話ではなく、今そこにある話だといえます。
よって、リーダーや管理職はこの流れを前提として若手技術者の育成に取り組まなければなりません。
どのようなアプローチが必要なのでしょうか。
基本的なやり方は”行き詰まる”までやらせる
結論から言うと、
「”行き詰まる”まで若手技術者にやらせてみる」
のが最も効果的です。
例えば、何かしらの技術に関する調査を若手技術者に行わせ、
それに対してもっともらしい回答を用意してきたとします。
その労をねぎらいつつ、
「では、その入手した技術情報が妥当であるということを、
自ら、もしくは委託業務による実験や試験を通じた実データで示してほしい」
と言ってください。
若手技術者に入手した情報の活用法が分からないことを自覚させる
このリーダーや管理職からの指示に対し、若手技術者の多くが感じるのは以下のことでしょう。
「どうすればいいかわからない」
これが、
「もっともらしい情報を持っていても自分では活用できない」
という状態です。
技術情報を有意義に活用するには、知っているだけではだめで、
その使い方まで知らなくてはいけない。
これが知識と知恵の違いです。
知識を高めても知恵が無ければ、机上の空論に過ぎないのです。
本経験により、
「Web情報と生成AIを組み合わせたもっともらしい情報では、
本当の意味での技術者としての技術実務推進力には役立たない」
という実感を若手技術者も持つことができるでしょう。
若手技術者育成に向けた軌道修正は、
このような実体験が前提となります。
※関連コラム/連載
第6回 新人技術者の“知っている”ことが実務で使えない 日刊工業新聞「機械設計」連載
まとめ
専門性至上主義を抱える一方で自尊心が低いことに苦しむ若手技術者にとって、
Web情報と生成AIを組み合わせ、技術専門家”風”の記述ができるようになるのは、
承認欲求を満たすという意味で心地よく感じるかもしれません。
その気持ちには向上心の要素も含まれるため全否定はできませんが、
技術者育成の観点から言うと本質からずれてしまっています。
ただ、これを頭ごなしに若手技術者に指摘しても、
なかなか納得しないでしょう。
リーダーや管理職は指摘や指導という観点から、
「行き詰まりを体感させる」
ことによって技術者育成に必要な心構えという準備を、
若手技術者に促すことが肝要です。
※関連コラム
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: