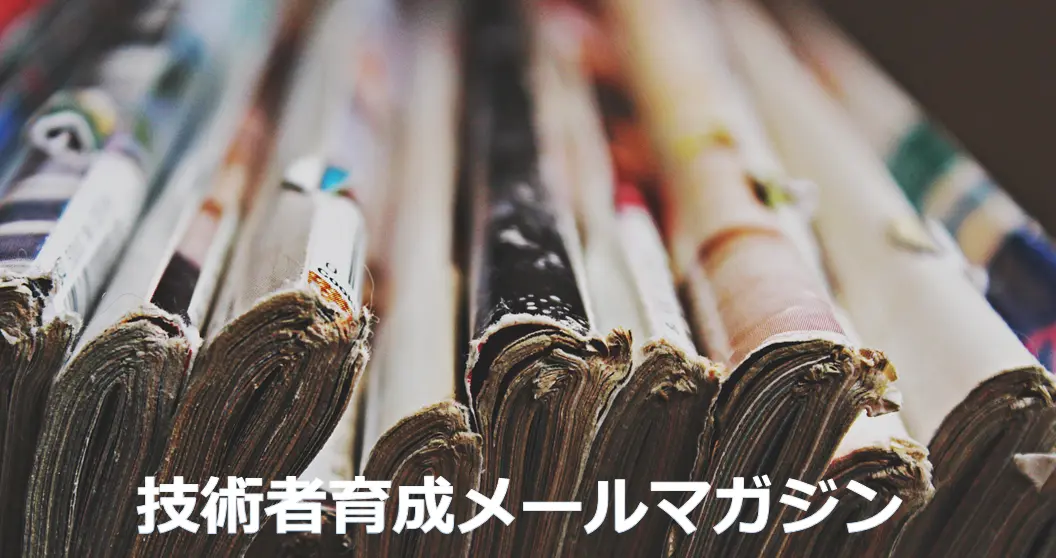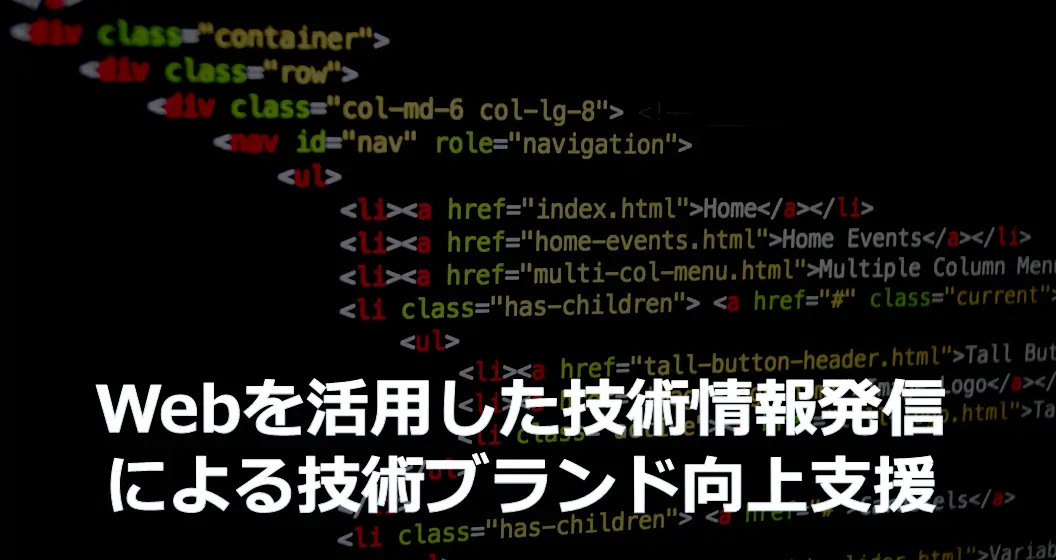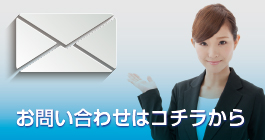学術業界と産業界の共通課題を踏まえた若手技術者育成による企業技術力向上の取り組み
公開日: 2025年8月11日 | 最終更新日: 2025年8月13日
タグ: マネジメント, メールマガジンバックナンバー, 技術者の自主性と実行力を育むために, 技術者人材育成, 要素技術醸成, 雑用
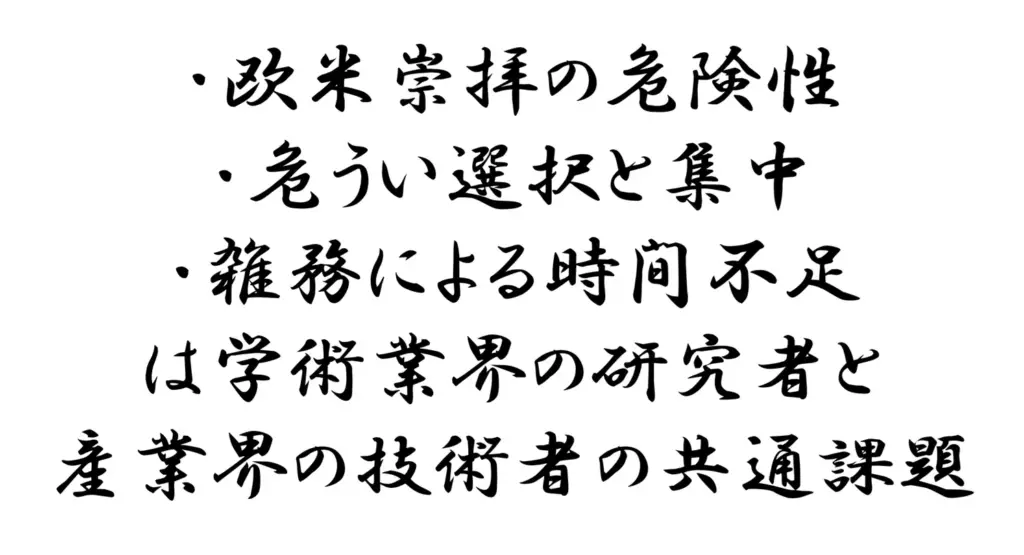
技術者を有する企業の技術力を高めるには、
新技術の創出や既存技術の発展が不可欠です。
早い段階でそれを実現するため、
若手技術者にどのような対応をすべきかについて、
今回は学術業界の知見も参考に、技術者育成の観点から考えます。
話題となった日本の研究者の現状に対する考察論文は技術者の現況にもつながる
私の所属する応用物理学会誌の記事を眺めていた際、興味深いものを見つけました。
それは、五十嵐杏南氏の以下の論文に関する記事でした。
Anna Ikarashi, Japanese research is no longer world class — here’s why, Nature, 2023, 623, 14-16
この論文では取材によって見えてきた日本の学術業界における課題を中心に記載されているようです。
いくつかのサイトで当該論文に関する見解が述べられるなど、
関心の高さがうかがわれます。
上記の論文は読めていませんが、記事中では当該論文の執筆者の見解が述べられていました。
以下のサイトで内容を読むことができます。
五十嵐杏南, 最近の展望「Japanese research is no longer world class」について, 応用物理学会, 2025 年 94 巻 8 号 p. 422-424
執筆者はライターの方なので、
客観的な視点で述べられています。
加えてここで述べられている内容は、冒頭述べた新技術の創出や既存技術の発展を目指す企業にもつながる部分もあると感じています。
私が記事中で注目したのは、
- ・欧米崇拝の危険性
- ・危うい選択と集中
- ・雑務による時間不足
の3点です。
それぞれについて、学術業界と産業界の共通課題に触れます。
欧米崇拝の考えから脱することは民間企業において特に重要
私自身は学術業界の現況について詳細は分かりませんが、
例えば記事中の中でも述べられていた学術論文の被引用数を軸としたImpact factor(引用影響度)、
大学のランキングといったものの多くは、
欧米のルールがその基本にあるとの理解です。
前出の記事中でもImpact factor、
すなわち欧米主体で決まった基準を考慮した議論が展開されています。
Impact Factorに関連する”被引用数”の上位10%に出てくる学術論文数で見た際、
日本人執筆(という意味だと解釈しています)の論文が減っているのではなく、
他国の執筆者(という解釈)の当該数が増えているため、
相対的に日本人執筆の論文数が減少しているのであって、
日本の研究力が低下したと一概には言えないのではないか、
といった興味深い内容となっています。
Impact factorの概要と課題
このImpact factorについて例えば以下の参考情報によると、
1957年に学術論文の目次速報であるCurrent Contentsを発表した、
アメリカのEugene Garfieldが1972年にScienceで発表されたImpact factorを用いて、
学術論文を比較したことが始まりと言われています。
自分自身も複数の学術論文を掲載させていますが、
確かにImpact factorは参考にしました。
ただこれには以下のような課題もあり、
さらに自誌引用で数値を高めるといった、
Impact factorを高めることが”目的”となっているケースもあることが、
参考情報にも記載されています。
<Impact factorに関する課題:引用ここから>
1. 引用数の多い論文ほど被引用数が多い.
2. 基礎研究や実験科学と比較して,応用や開発研究のほうが引用数,被引用数ともに多い.
3. 他分野からよく引用される分野がある一方で,他分野をよく引用するが他分野からは引用されない分野がある.
4. 論文公表後すぐに引用される分野と,引用されるまでに時間がかかる分野がある.
5. 長く引用される分野と,短期間しか引用されない分野がある.
6. 原著論文よりもレビュー論文のほうが被引用数が多い.
7. 専門誌よりも総合誌のほうが被引用数が多い.
8. 単著よりも多数の研究者による共著のほうが,また,国内共著よりも国際共著のほうが被引用数が増える.
9. プレプリントの公開期間が長いほど被引用数が増える.
<Impact factorに関する課題:引用ここまで>
※参考情報
逸村裕 他, インパクトファクターの功罪, 化学, 2013, Vol.68, No.12
上記の参考情報にはGoogle Scholar Metricsのh-indexにも触れられていますが、
いずれにしても欧米が主導して導入が進められてきた指標であることが分かります。
さらに言うと、そもそも主たる学術論文は英語で記載される、
というのもその言語になじみの薄い国にとっては不利であるのも事実ではないでしょうか。
これを民間の技術に置き換えると、
そもそも何故欧米のルールに基づいたものを基軸としなければならないのか、
という疑問がわくはずです。
別の例でいうと経済指標であるGDPも類似の要素が含まれており、
日本が得意とする中古品売買に関する指標が入っていません。
2023年段階で3兆円をこえている経済の動きがGDPに入っていないのは、
数字だけ見ると日本としては当該経済指標は不利になるという見方もできます。
※参考情報
リユース市場とは?動向と将来性を専門紙が解説(2025年版)/リユース経済新聞
日本の民間企業は他国企業の土俵に乗るだけでなく、自らの得意な舞台を用意する思考が必要
学術業界におけるImpact factor(または論文の被引用数)といった指標で議論が進むことを引き合いに、欧米追従型の考えの課題を述べました。
これを技術系の企業に置き換えます。
民間企業が技術力で勝負しようとするのであれば、
他国企業が作った土俵に向かうだけでなく、
自国企業で得意な舞台を作り、そこに他国企業を引き込む戦略が必要である、
というのが私の考えです。
まずは民間企業でも陥りがちな欧米崇拝、
例えばAIへの盲目的な追従といった流れになっていないか、
という振り返りが必要でしょう。
危険な選択と集中
冒頭で参照した応用物理学会の記事によると、
学術業界では「政策主導型」と呼ばれる研究領域に集中的に資金が投入されているとのことです。
これも民間企業と似た雰囲気を感じます。
業界のトレンドをターゲットに見据え、
「補助金や助成金の出やすい技術テーマ」
に取り組む一方、
「自社技術を活用する、異業種技術と組み合わせる」
といった、自社技術の本質を顧みない。
このような状態を見聞きした、
もしくは自社がその状態に陥っていると感じたことは無いでしょうか。
これを選択と集中というもっともらしい言葉で、
結果的に技術テーマに偏りがあると、
新技術の創出や既存技術の発展は困難となります。
研究開発を適切に推進するためには決め打ちの試行ではなく、
現場技術者がやってみたいことを実行させる自由度が重要です。
雑務によって時間が足りなくなる研究者は技術者とも類似
学術業界の研究者を悩ませるものの一つが時間の不足とのこと。
産学連携をはじめとした業務範囲が広くなる一方、
日本ではテクニシャンや専門事務員が担う仕事を、
研究PJや研究室の主催者が行うのが現状とのことです。
この状況は民間企業の技術者にも当てはまることで、
特に現場の最前線を担う中堅技術者に加え、
リーダーや管理職が拘束されがちな事務作業や打ち合わせの時間がそれに該当します。
事務作業は可能な範囲で自動化する、
打ち合わせについては話す内容を事前に決める、使用する書面を準備する、
そもそも不要な打ち合わせを削減する、といった考えが必要です。
※関連コラム/連載
第16回 技術テーマ推進に必須の月例ミーティングで用いる実績報告書の構成と書き方 日刊工業新聞「機械設計」連載
効率化”だけ”を考えることは技術力低下につながる
一方で何に対しても効率化という考えを当てはめるのは間違えです。
例えば技術者は研究開発のような試行錯誤が必要な業務に効率の考え方を取り入れてはいけません。
時に無駄と思われることを実験で試し、
そして粘り強く技術的な事実を突き詰め、
結果に対して考察をする。
新技術創出や既存技術の発展は、
このような粘り強さによってのみ実現します。
次にこれらの学術業界と共通の課題を踏まえ、
本題である新技術の創出や既存技術の発展に向け、
若手技術者をどのように育成していくかについて考えます。
技術テーマ立案は外の情報を調べる前に自社技術の強みを徹底的に分析する
まずは欧米崇拝の危険性に関連するものです。
技術テーマを立案しようとした場合、
まずは市場調査や技術トレンド調査を依頼の上でアイデア探しをさせる、
というのが企業の一般的なアプローチの一つかもしれません。
これは定石ともいるものですが、技術という観点でいうと必ずしも正しいとは言えません。
何故ならば、
「自社技術の強み」
という観点が皆無だからです。
市場や技術トレンド調査は技術テーマとして妥当な情報を提供できるか
市場調査は市場規模といった金銭情報がベースであり、
そこから技術的な要素を抽出するのは容易ではありません。
技術トレンド調査は多くの場合、欧米が戦略として進める内容の影響を強く受けており、
結果的に欧米追従の技術テーマへと向かうでしょう。
これらの調査自体を否定することはしませんが、
情報の一助になったとしても新技術創出や既存技術の発展にはつながりにくいと、
私は考えています。
一にも二にも自社技術の強みを理解する
技術者を抱える企業は、大なり小なり強みとなる自社技術を有しています。
それはある程度の時間をかけて積み重ねられてきたことであり、
各企業の歴史でもあります。
特に独自技術を持っている場合、それは代替できないため、
それ自体が新技術の要素となる可能性を秘めています。
その一方で、多くの企業において自社技術の強みを理解していることは少ないのです。
主たる理由は、
「自社技術はその企業内では常識だから」
です。
前出の調査結果を求める以前に、
そもそも技術の宝は手元にあることに気が付かない企業が多いといえます。
もっともらしいトレンドに流されるのではなく、
まずは自社技術の強みを徹底分析できる冷静さが、
新技術創出や既存技術発展に必要なのです。
若手技術者にも技術テーマ立案の一助として自社技術の強みを伝える
若手技術者が個人的にやってみたいというテーマを提案してきたときは、
後述の通り自由にやらせてあげてほしいと思います。
同時に自社技術の強みを理解することは、
若手技術者がより妥当な技術テーマを立案する参考になるのも事実です。
各企業には自社技術の強みを活かす人と物、
そして技術報告書などの記録があるからです。
このような自社技術の強みの分析に若手技術者を関わらせることは、
技術者育成の観点でいえば、”自社理解”そのものといえます。
前出の自社技術の分析には、
是非若手技術者も関わらせてあげてください。
若手技術者を中堅技術者の時間捻出に貢献させながら仕事を覚えさせる
学術業界の研究者同様、
中堅技術者、リーダー、管理職は事務作業、
並びに打ち合わせに時間をとられる傾向にあることを述べました。
中堅技術者は経験と若さを有する大変重要な存在であり、
新技術創出と既存技術発展に向け最前線で活躍することが期待されます。
技術者育成の観点でいうと、若手技術者の育成は本点を念頭に置いて設計することが望ましいと考えます。
打ち合わせの圧縮や削減については、
既述の関連コラムと連載をご参照ください。
ここでは若手技術者育成と関連の強い事務作業を中心に述べます。
若手技術者の多くが”雑用”と考える事務作業も重要な業務
専門性至上主義を掲げる若手技術者にとって、
事務作業の多くは”雑用”にしか映らないでしょう。
「自分はこんなことをやるために入社したつもりはない」
という趣旨の発言をするか否かは別として、
心のどこかでそう思っている時点で事務作業を雑用と認識していると考えられます。
事務作業は単なる雑用ではない
しかし企業における仕事において、事務作業は単なる雑用ではなく、
日々の仕事を回すために必要な”業務”です。
事務作業をできるようになることは仕事の流れを理解することにつながり、
それが若手技術者の社内での視野を広げるきっかけにもなります。
技術者育成の観点で、職場における視野の拡大は大変重要です。
本点を若手技術者に説明することが、
リーダーや管理職に求められます。
仕事を主観的に分別するような若手技術者は成長が遅れ、
結果として組織のお荷物になるのです。
事務作業は雑用ではなく必要な業務であることを説明の上、
今まで中堅技術者が担ってきた事務作業を若手技術者にあてがうよう、
リーダーや管理職は業務を調整してください。
※関連コラム/連載
第2回 普遍的スキルの鍛錬を阻害する技術者の癖 日刊工業新聞「機械設計」連載
第3回 若手技術者の育成の第一歩に何をすればいいのかわからない/工場マガジンラック 日刊工業新聞社
中堅技術者の時間捻出への貢献を評価する
若手技術者がいきなり研究開発の前線を担うだけの力量を有することは皆無であり、
しかし給与をもらっている以上、組織に貢献することが求められます。
ここで若手技術者が中堅技術者の担う事務作業を担うことで、
中堅技術者の業務負担を低減させることができるのは、
「組織にとって大きな貢献」
と評価すべきです。
このような評価を管理職からきちんと伝えることは、
事務作業を行う若手技術者のモチベーション向上にもつながります。
少額予算でいいので若手技術者に技術テーマを推進する自由度を与える
次に危うい選択と集中に関する内容を考えます。
前出の参考情報でも触れられている通り、
学術業界だと政策主導型の研究領域に予算が集中するといった課題があるとのこと。
同じ理由で企業が補助金の取りやすいトレンドテーマを追う一方で、
現場の技術者には予算も裁量権も与えない、
といったやり方では優秀な技術者から企業を離れていくでしょう。
少額予算でいいので若手技術者のうちから裁量権を持って技術テーマを進める経験を積ませる
資金が潤沢にある場合、
様々な技術テーマに対して予算をつけ、
それらを技術者に推進させるということはそれほど困難ではありません。
ただ多くの企業にとって、形になるか否かわからない技術テーマにかけられる予算には限りがあります。
株主が居れば、まさに既述の通りトレンドテーマに資金を集中するよう要求するでしょう。
株価と利益の上昇を最優先に考える株主であれば当然ともいえる主張ですが、
必ずしも技術的に正しいわけではありません。
また、企業の財務状況によってはそもそも研究開発使える予算に制限が付くはずです。
これらの状況であってもできることは、
「少額予算を複数組む」
ことです。
そして少額予算を組んだら、
「研究開発に取り組んでみたいと立候補する若手技術者に自由に技術テーマに取り組ませる」
ことをやってください。
若手技術者が能動的に動くことが大前提
上記の通り、
「自分でやってみたいと主張する」
ことが大前提であることは強調しておきます。
リーダーや管理職は
「やってみたい技術テーマがあったら遠慮なく提案してほしい」
と周知するところまでが仕事です。
自分がやってみたいという技術テーマを進めることは好奇心を高め、試行錯誤に対する耐性を高める
技術テーマを進める、といっても若手技術者はどのように行えばいいのかわからないでしょう。
ここでリーダーや管理職が準備すべきは、
「技術テーマ企画立案の業務フロー構築」
です。
技術テーマ企画業務に関する各種書類を準備の上で、
その作成法を丁寧に指導し、
やったことのない若手技術者でも当該業務推進を後押しすることが肝要です。
技術テーマ企画は難しくないという印象を若手技術者に与えることは、
新しい技術を議論する心理的安全性を高めることにもつながります。
※関連コラム/連載
第12回 技術テーマ立案に不可欠な技術者の「企画力」鍛錬の勘所 日刊工業新聞「機械設計」連載
新技術創出や既存技術発展に向けて技術テーマを推進する経験を通じ、
若手技術者は様々な壁にぶつかるでしょう。
その壁を乗り越えるために試行錯誤することが、
技術者として重要な”忍耐力”を鍛えることにつながります。
本コラムに関連する一般的な人材育成と技術者育成の違い
今回取り上げたテーマに類似した一般的な人材育成の取り組みとして、
新しいアイデアを創出する企画に関する研修等があると考えます。
このような研修ではアイデア出しという観点を基軸に置いており、
費用対効果や社会トレンドを踏まえたデータの分析法といった指導が行われると考えます。
事業的観点を入れて議論を進めることが多く、
企業組織として重要なスキルであるといえます。
それに対し技術者育成において重要視するのは、
雑用と考えられる業務への貢献と、
自らがやってみたいという技術テーマを少額予算でも自己裁量で推進することによる、
試行錯誤の経験です。
この経験を踏まずに、新技術創出や既存技術の発展に貢献できる人材になることは困難でしょう。
若手技術者はその多くが事務作業をはじめとした定常業務を雑用として負の印象を持っていますが、
そもそも若手技術者のうちは技術テーマ等で貢献することは極めて困難であり、
むしろ彼ら、彼女らが”雑用”と考える仕事を、
最前線で研究開発に取り組む中堅技術者の代わりに担うことによる、
組織貢献の重要性を理解させることを重視しています。
これは業務に関する若手技術者の視野拡大にもつながります。
同時に少額予算であっても自己裁量で技術テーマを企画立案し、
実際に前進させることで研究開発で必須の試行錯誤の経験を積ませると同時に、
技術者としての成長実感を持たせることによるモチベーションの維持と向上を目指します。
本コラムに関連する具体的な技術者育成支援の例
技術者育成コンサルティングとして対応します。
まず行うことは自社技術の理解です。
各企業が”常識”と考える技術の特徴や強みを徹底的にヒアリングし、
どこに強みがあるかを分析の上でお伝えします。
同時に技術テーマの企画に関する業務フローの有無を確認の上、
ある場合は改善の必要有無を含めた提言、
無ければ一般的な技術テーマ企画の業務フローと、
そこで用いる書類の初案をご提案します。
人数が少数であれば個人面談も行いながら、
技術テーマ立案に向けた方向性の気づきを与える、
といった個別フォローも可能です。
管理職には必要な予算確保について調整いただく一方で、
若手技術者が進める技術テーマには結果や成果を求めるのではなく、
その過程で生じる試行錯誤の重要性を伝えることについてご説明します。
同時に事務作業を中心とした定常業務を中堅技術者から若手技術者に移行することを支援し、
中堅技術者の時間捻出と、当該技術者の技術テーマ立案に向けた指導を合わせて行います。
まとめ
新技術の創出や既存技術の発展は企業の技術力向上に不可欠です。
これを前進させるにあたっては、
欧米崇拝思考を基本とした技術トレンド迎合の考えから、
自社技術の強みを基軸とした考え方にかじを切らなければなりません。
同時に事務作業を中心とした定常業務から、
研究開発を最前線で担う中堅技術者を開放する必要があります。
ここに若手技術者育成の観点を取り入れながら、
少額予算ながら自己裁量で自由に技術テーマを進める土壌と、
若手技術者が雑用と捉えがちな定常業務を中堅技術者から引き取ることで、
仕事の流れを理解させるという取り組みがポイントとなります。
雑用と捉える可能性がある仕事を行うことはモチベーションが下がりがちですが、
裁量権を持って技術テーマを進められるという経験により、
知的好奇心を満たし、向上心に火をつけ、
そして試行錯誤を通じた忍耐力を高めることを狙います。
このような鍛錬を繰り返すことで、
若手技術者は技術トレンドに流されず、
かつ自社技術を理解したうえでその強みを活かす技術テーマの立案ができるようになっていきます。
若手技術者を育成し、新技術創出と既存技術向上を実現する組織づくりをした、
リーダーや管理職の方々にとって参考になれば幸いです。
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: