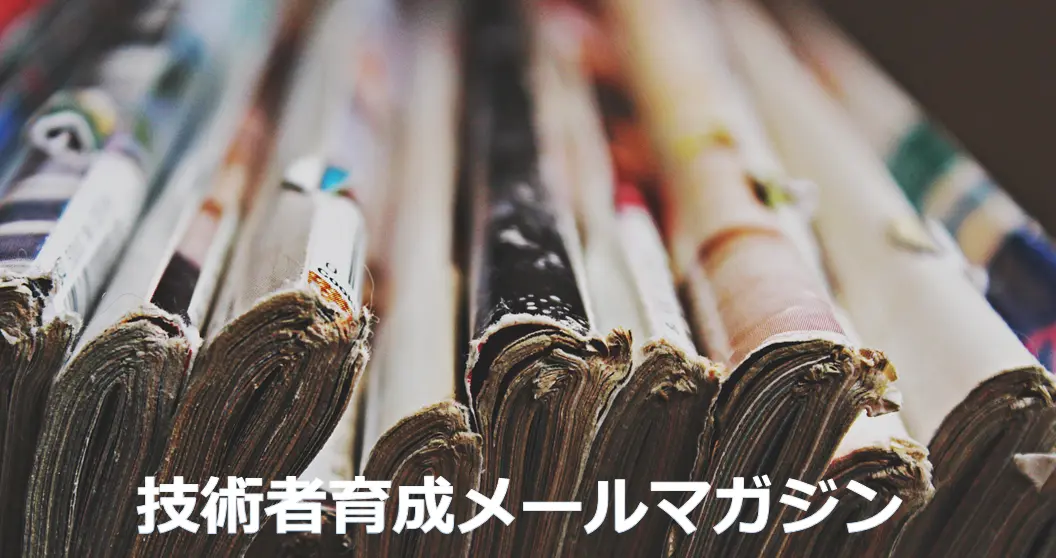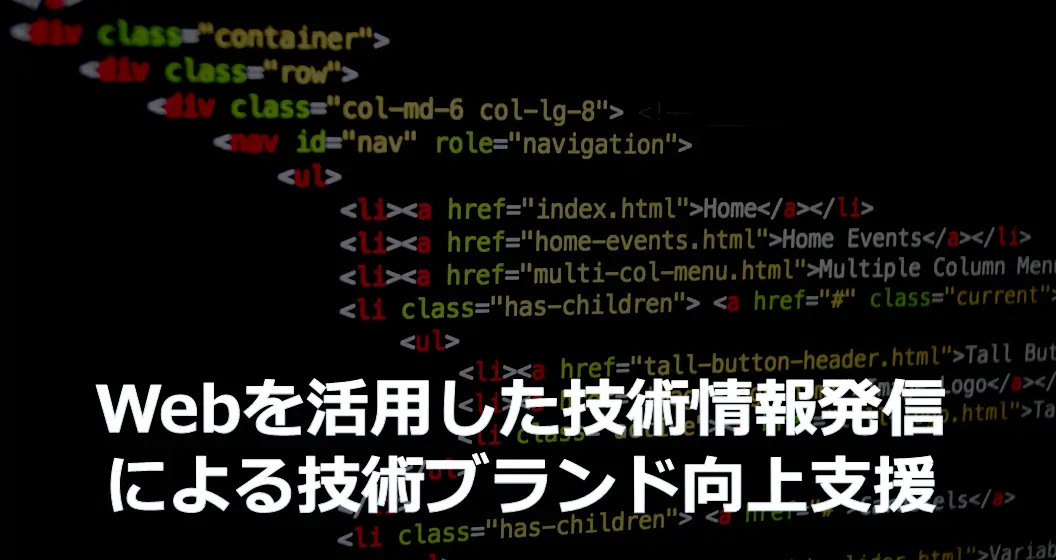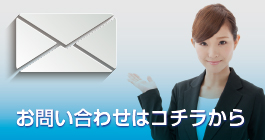2025年度 大学での講義と学生応答の振り返り
公開日: 2025年11月3日 | 最終更新日: 2025年11月2日
タグ: メールマガジンバックナンバー, 大学, 技術報告書, 技術者の普遍的スキル, 技術者人材育成, 採用, 非常勤講師
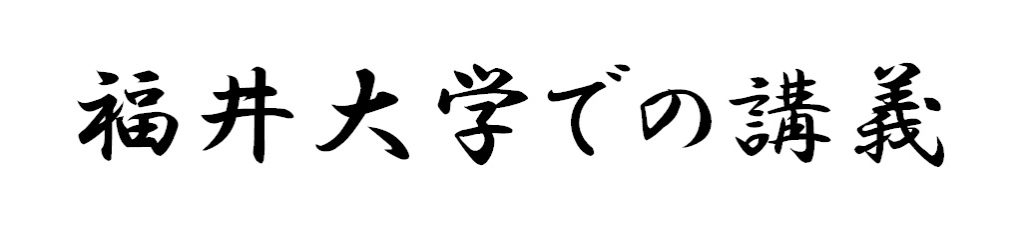
国立大学法人 福井大学のフロントランナーという2025年度の授業に登壇しました。
今回は本講義の概要と学生の応答、それを踏まえて企業が技術者(技術職)を受け入れるにあたって考えるべきことについて述べます。
5年ぶりの対面授業実現
私自身は福井大学の非常勤講師は11年目ですが、
ここ数年はコロナの影響もあってオンラインが続いていました。
今年は念願かなって久々の対面での授業となりました。
福井大学は工学部設立100周年を迎えたとのことで、
内装を新しくした講義室ができているなど、
数年行かなかった間に建物の変化が見られました。
ただ学校の雰囲気にはそれほど大きな違いは感じませんでした。
対象は主に理系学生
一部国際関係の学部の学生もいますが、
主には工学部の3年、もしくは4年生が受講対象です。
フロントランナーという授業はオムニバス形式ですので、
私だけでなく、複数の先生方(主に民間企業の方)が手分けをして担っています。
大学としては技術系の仕事をしている方々からの外部刺激を学生に伝え、
学生生活に張りを持たせる、日々の授業内容の将来に向けた活用を意識させる、
といったことを狙っていると理解しています。
通常、講義内容は勤務する企業の紹介が多い
これは担当されている先生方から聞いている話ですが、
主にフロントランナーで話をされる方々は、
勤務されている企業の有する技術紹介が主とのこと。
どのような技術を有する企業が居るかを学生のうちに知ることは、
民間企業に就職する予定の場合、大変参考になると思います。
技術者育成の観点から講義を企画
私の専門であるFRPを中心とした話は企業向けしか想定しておらず、
学生向けにすることはありません。
そもそも限られた学生しか理解できない内容は、
せっかく様々な領域の工学系の学生に集まってもらっているのに、
無駄とまでは言いませんが、勿体ないと思います。
そのため例年、大学での講義では技術者育成の観点から、
将来民間企業で技術者として働く場合、
どのようなスキルが必要かを伝えることを意識しています。
今回から技術者の普遍的スキルの解説を導入
まだ発展途上の部分もありますが、
技術者育成として重要なスキルのうち技術業界不問の、
「技術者の普遍的スキル」
が製造業企業に勤務する技術者にとって不可欠なものとして定義しています。
※関連連載
第1回 技術者の普遍的スキルとは何か 日刊工業新聞「機械設計」連載
これまで学生向けには本観点での話をしたことがありませんでしたが、
今年から初めて技術者の普遍的スキルの解説を加えました。
後述の通り、私自身の考え方として、
「大学はあくまで学術界の専門機関であり、産業界に歩み寄る必要はない
と考えています。
ただし、民間企業への就職を考える学生も一定数以上いることを踏まえ、
そのような方々にちょっとした予習をしてもらう立ち位置で話をしています。
簡単な技術報告書の作成演習を実施
講義は聴いているだけでは面白くないだろうという私の考えもあり、
今回は技術者の普遍的スキルの鍛錬に最も効果的な手法の一つである、
技術報告書の作成演習も取り入れました。
これは民間企業の新人、若手研修や民間企業のセミナーでも導入している内容の一部でもあります。
次に今回の講義を行う中で感じた学生の応答について振り返ります。
学生の姿勢に顕著な違いは見られなかった
学生相手に話をすると顧問先企業等でよく聞かれるのが、
「最近の学生はどうですか」
という趣旨のものです。
私が接する学生の数も100人を少し超える程度であるうえ、
それほど頻度も多くないため獲得情報には限りがあることを踏まえると、
本当の意味で最近の学生を知れるわけではありません。
ただ、同じ条件でここ10年間見てきた中でいうと、
あまり違いは見られなかったというのが個人的な印象です。
それぞれの年で何となくの傾向による違いは有りますが、
今年感じた違いは例年感じた誤差の範囲を超えていませんでした。
強いて言えば、ここ数年の学生に比べてやや積極的な学生が増えた印象です。
裏を返すとここ数年、少し元気のない学生が多かったと感じていたため、
元に戻ってきたのかもしれません。
当然ながらオンラインか対面かの違いもあるかと思います。
質問に対して自分の意見を的確に言える学生が増えてきた
これは今回感じたことですが、
答えの無い質問をしたときに自分なりの考えをきちんと述べる学生が増えた気がします。
もしかすると義務教育において、
自分の意見を言うという練習を繰り返してきたことが一因かもしれません。
淡白な回答をする学生も一定数いますが、
「何故そう思う?」
と突っ込むと、きちんと自分の意見を時間差なく言う学生も多かったです。
話が止まってしまう学生の場合、近くにいた友人がこう言ったらどうだ、
こういうことではないか、と助け船(かどうかわかりませんが)を出すケースも、
今まであまり見られなかった傾向です。
自分にマイクを向けてくれ、という意思表示だった可能性もあります。
講義をする側としては積極参加しようとする姿勢と前向きに受け止めました。
筆記用具を持たない学生がいた
これは時代の流れかもしれません。
技術者の普遍的スキルの向上には手書きの鍛錬も重要のため、
講義では手書きの演習を出しました。
ところが筆記用具を持っておらず、やむを得ずスマホで取り組む学生もいました。
最初は何か調べごとや内職をしているのかと思ったのですが、
小さい画面で一生懸命記入していました。
頑張っている姿勢は良いと思ったので、講義中にフォローしました。
持っていないなら持っていないなりにスマホでやってみる、
という姿勢だったので大きな問題ではないとの認識ですが、
”授業に筆記用具を持ってこない”という選択肢を持つ時点で、
デジタルデバイスの浸透を感じました。
一方で筆記用具を持っていない、またはわからないから手を付けないという学生も少数いたことは残念でしたが、このような学生は10年前から毎年少数いるとの認識です。
個人的にはこのような姿勢の学生が、
どのような将来を歩むことになるのかは興味があります。
演習は時間もかかるが質も上がっている
これも今年明確に見られた傾向です。
技術者の普遍的スキル向上には、スピード感を持った集中した取り組みも重要であるため、
今回の講義でも、ある程度の目安時間を設定して課題に取り組んでもらいました。
できた人から手をあげてください、というやり方で見ているので、
およそのスピード感は把握できます。
例年の傾向を言うと、表現の良し悪しはありますが
「スピード感はあるが、内容が雑」
という学生が比較的多かったと感じています。
スピード感が大事ならば、とりあえず適当にでもやって手をあげればいいだろう、
という考えでしょう。
それに対して今年は、
「時間はかかるが、内容の質も高い」
という傾向にありました。
これは恐らくここ10年で最も強く感じた違いです。
課題を出してもなかなか進みが悪いので、
大丈夫かなと思ってみていましたが、
「時間をかけてでもきちんとしたものを出したい」
という考え方の学生が今年は多かったのかもしれません。
5分程度でできてほしい課題に多くの学生が10分近く、またはそれ以上かかっていましたが、
でき自体はよかったです。
時間当たりのプレッシャーは技術者育成効率向上に不可欠ですが、
当該育成でいきなりこの手法を使いすぎると、
強いストレスを感じる世代が増えつつあるかもしれません。
当然、アウトプットの質も重要なので、現段階では一概に良い悪いは判断できていません。
技術者の普遍的スキルの一つである技術文章作成力について、やや改善の傾向を感じた
今年行った技術者の普遍的スキルに関する講義においては主に技術文章作成力を評価しましたが、
総じて言えるのは”改善の傾向にある”ということです。
これが今年限りなのか、それとも本当に改善の傾向として示されているのかは、
来年度を見てみないと何とも言えません。
しかしながら、少なくともここ10年を見た限りでいうと、
今年の学生の技術文章作成力はやや高いと感じました。
本基礎力を学生のうちに身につけておくと、
民間企業に就職する場合、
入ってから様々な成果を出しやすくなると期待できます。
ただし、前述の通りスピード感に欠けるという課題があるのを忘れてはいけません。
働き方改革が進みつつある現代では、
当該スキルに基づく推進効率が低い間は厳しい状況が続くかもしれません。
短い時間に仕事をやりきるということが難しいからです。
最後に大学での講義に関連した私見を述べたいと思います。
大学は技術者を育成する場所ではなく、学術向けの研究者を育成する機関である原則は変わらない
これは何度か述べているところですが、
大学というのはどこまで行っても学術界で活躍すべき研究者を育成する機関であり、
民間企業向けの技術者を育成する場所ではありません。
ここの原則だけは、学生にも先生方にも忘れてほしくないと思います。
今回の講義で技術者の普遍的スキルを紹介したのも、
学術界でも”ある程度役に立つ”と考えた故です。
学生の方にはあえてそのような話はしませんでしたが、
今回伝えた技術者の普遍的スキルを活かして、
上記の事実に早い段階で気が付いてもらうことを期待しています。
※関連コラム
受け入れる企業は適宜フォローしながらも早い段階で任せてスピード感を身につけさせる姿勢が必要
これは若手技術者育成の基本でもありますが、
新人として入社した若手技術者には、
早い段階で実務経験を積ませることが重要と感じます。
実務経験を若いうちに多く経験することこそが、
「技術業務速度向上に最も効果がある」
からです。
ある程度納期の厳しい短期の仕事を任せつつ、
しかし定期的なコミュニケーションを取りながら適切にフォローすることで、
その成長を促すことが若手技術者戦力化の近道です。
今年の学生を見る限り、学生の時点でもある程度の基本はできていますので、
あとは学術界ではなく産業界に入ってきた人に、
様々な経験をさせる”勇気”が受け入れ企業側に必要です。
新人技術者はスピード感に欠けるものの、
質を高める意識を強く持っていることを理解してあげることが、
結果的に技術者育成の効率向上に好影響を与えるものと考えます。
※関連コラム
将来研究開発を担う若手技術者の育成には中長期の研究は適さない
最後に
大学生に向けた授業でいつも感じるのは、
若い方というのは本当に柔軟で純粋だということです。
一見すると大人びて見えますが、
何かを教え、それを納得した時に見せるその目は、
少年少女のそれとあまり変わりません。
本当にいい目をしていました。
最初は睡眠時間確保のつもりでやってきたようですが、
次々マイクを持たされて発言を求められるので、
開始15分もすれば100名超の学生の誰も寝ておらず、
一生懸命聴いてくれていました。
こういう切り替えの早さも若い方の良いところです。
このような若い方は技術者の普遍的スキルの一つである、
異業種技術への好奇心も強い場合が多く、
企業にとって大変重要な役回りを果たす可能性も十分にあります。
学生の方々は授業やアルバイト、サークルはもちろん、
学術界に行くとしても、民間企業に就職するとしても大変貴重な経験となる研究室生活に、
自分の時間と熱量を注いでほしいです。
受け入れる企業はやる気に満ちた若手技術者が早い段階で経験値を積めるよう、
任せられる短期業務とその推進時に提供するフォローの準備を進めることが重要です。
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: