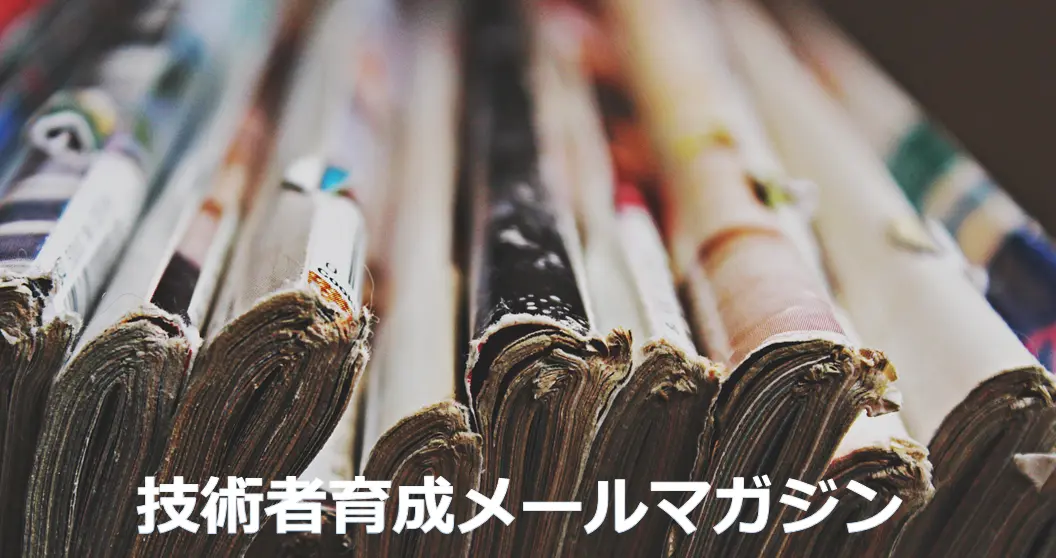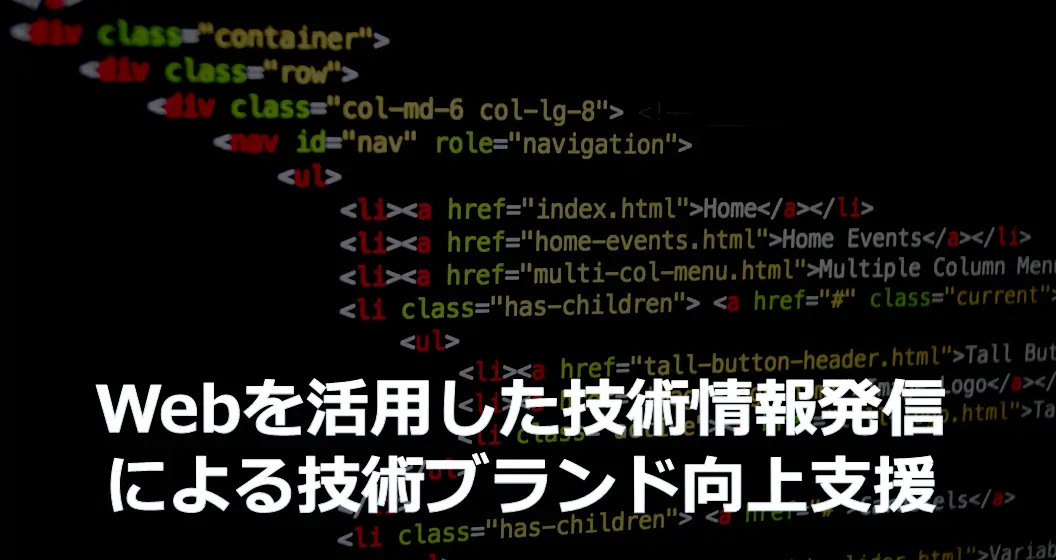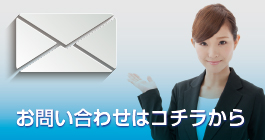博士の学位を有する新人技術者の育成を何から始めるべきか
公開日: 2025年9月22日 | 最終更新日: 2025年9月22日
タグ: OJTの注意点, できる技術者をさらに伸ばす, メールマガジンバックナンバー, 博士人材, 技術者人材育成, 採用, 要素技術醸成
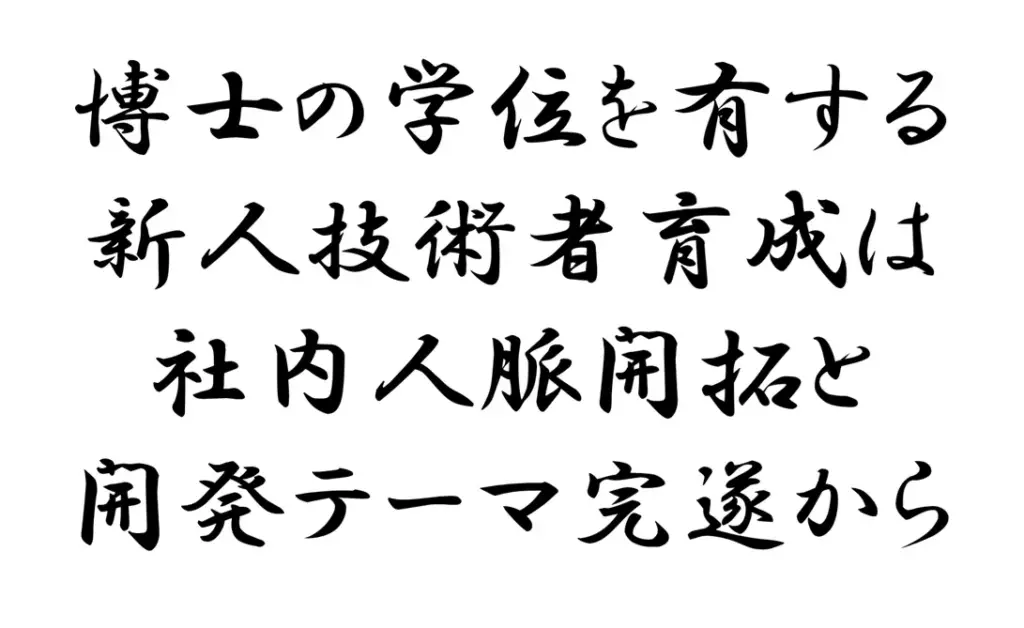
博士の学位を有する技術者(研究者)の採用について関心が企業でも高まりつつあります。
一方で実際に採用したものの、当該社員を企業の戦力として機能させるためには、
受け入れ側の準備も不可欠です。
今回は博士の学位を有する新人技術者の育成を何から始めるべきかについて考えます。
博士の学位の意味を今一度考える
本題に行く前に、今一度”博士”という学位について考えたいと思います。
博士課程の定義
このような言葉を考えるときは、行政の情報が最も確度が高いと考えました。
文部科学省では博士の学位を修める”博士課程”を以下のように定義しています。
「研究者として自立して研究活動を行うに足る,又は高度の専門性が求められる社会の多様な方面で活躍し得る高度の研究能力とその基礎となる豊かな学識を養う。」
※参照情報
個人的には前半の定義(自立して研究活動を行う)はその通りかと思います。
後半は不要ではないかというのが私の考えです。
博士の学位を有する人物に求められるのは、”学術界”における徹底した本質の追及であり、
”社会の多様な方面”といった抽象的な表現で拡大解釈をさせるようなものは、
定義をあいまいにしてしまう恐れがあるからです。
博士に求められるのは自律的かつ能動的に本質を突き詰める粘り強さ
何度か述べている通り大学というのは産業界向けの人材ではなく、
”学術界”で活躍する専門家を養成する機関です。
理学や工学の本質を突き詰めることが大学や大学院という高等教育機関が存在する本質であると私は考えます。
すなわちそこでは
「科学的な発見や理論の発展に貢献できるような人材」
を養成することが使命であり、そして、そうあるべきだというのが個人的な意見です。
効率、トレンド、ましてや売り上げといった言葉に影響されず、
自らが興味を持った領域を突き詰めることこそが博士という学位を有する人物が行うべきだと考えます。
ここの大前提をずれないようにすることは、
博士を持った技術者を育成するにあたっても重要です。
博士の学位有無に関わらず、受け入れ企業側が”何をしてもらいたいか”の職務明文化できるのが前提
博士の学位の位置づけをご理解いただいた上で本題に入っていきます。
当該学位を持っていても、企業で働きたいという方は当然いるでしょう。
昨今は以下の通り博士の学位を有する人材の活用を政府も後押ししていることもあり、
採用に前向きな企業も一定数あるものと考えます。
※関連情報
しかし博士の学位を有する人材の採用が”目的”になってはいけません。
重要なのは、
「受け入れ企業側がそのような人材に”何をしてもらいたいか”の職務明文化をできる」
ことです。
職務明文化は民間企業があまり得意でないことが多い
これは一朝一夕で解決できる課題ではありませんが、
仮に博士の学位を有する人材を技術者として採用しようとする場合、
「抽象的な表現に終始する」
ことが多いはずです。
例えば以下のような文言が入った求人を出している企業は、
職務明文化に難がある状態といえるでしょう。
(複数の博士の学位を有する求人情報をベースに抜粋しています)
経歴や専門性に応じ….
職を希望してくる人物に応じて変化することを示唆しており、言い換えれば求める人物像の専門性が明確にできていない。
能動的ではなく、受動的採用とも見られてしまう。
○○業務(活動)全体に関する….
全体という単語を使っていることは、範囲をできる限り広げたい意図がある。
想定する職務に不明瞭な部分が多いことが示唆される。
XXXX / YYYY / ZZZZ 等の業務を担っていただきます….
職務明文化のように見えるが、ありえそうなことを箇条書きにしており、勤務する技術者にどのような働きをしてもらいたいかのイメージができていない。
職務明文化のポイント
どのようにして職務を明文化すればいいのかについては、
ジョブ型業務を念頭に置くとわかりやすいでしょう。
以下の要点を網羅することが肝要です。
- ・具体的に何をしてもらいたいのか
- ・成果と認めるものは何か
- ・それをいつからいつまでやるのか
これを意識しながら、対応させたい業務は何かを具体的に記述し、
拡大解釈を許容しない内容とすることが肝要です。
詳細については以下のコラムをご参照ください。
※関連コラム
上記の通り、職務明文化が博士の学位を有する技術者採用の前提にあることを認識いただくことが第一歩かもしれません。
採用段階が終わったとして、次に本題である、
「博士の学位を有する新人技術者の育成を何から始めるべきかわからない」
について述べたいと思います。
企業の社員として働くという最低ラインを守らせる教育は不可欠
冒頭の博士課程の定義のところでも述べましたが、博士の学位を有する人物像に求められるものとして
「自立(自律の意味もあり)」
が含まれています。
大学院の研究室生活ではこの”自立”が重視されることが一般的です。
修士課程であってもある程度自分でテーマを企画することはありますが、
博士課程は通常自分でテーマ設定をしたうえで、
そのテーマを通じて何かしらの科学的発展につながる発見について、
博士論文作成はもちろんですが、学会発表に加え、査読付きの学術論文として掲載させるところまで、
指導教官と議論を繰り返しながらも自立してやりきることが求められます。
そのため、博士の学位を有する新人技術者は一般的な技術者以上に、
「専門性至上主義へのこだわり故、自己完結にこだわる」
可能性があります。
実際にやりきったという実体験があるという意味では、
一般的な技術者以上に自己完結に執着するかもしれません。
これら博士課程で養われる感覚を研ぎ澄ました故、
企業の社員として働くための思考に欠けている一面もあるといえるかもしれません。
リーダーや管理職は博士の学位を有する新人技術者の社内ネットワークを広げる手助けを
自立精神を発揮し、自分で結果を出そうと奮闘する博士の学位を有する新人技術者の存在は珍しくないでしょう。
しかしながら個人レベルでの研究で成果として認められることは企業では極めて稀であり、
担当する研究開発テーマを企業の実績までスケールアップさせるには、
社内であっても様々な人物の協力が不可欠です。
よってリーダーや管理職は、
「企業では研究開発業務であっても役割分担がある程度存在し、
他の社員の協力を得ないと前に進まない仕事が多い」
ことを伝え、そのうえでOJTの中で様々な社員に紹介する、
という取り組みが重要になります。
詳細については以下の関連コラムをご参照ください。
※参照コラム
最初は中長期の研究テーマよりも短期で完結する開発テーマを複数完遂させることで、博士の学位を有する新人技術者の視野を広げる
前述の通り、博士の学位を有する新人技術者を採用するにあたっては、
職務明文化が不可欠であり、すなわちそれは取り組んでもらいたい中長期の研究テーマが存在するはずです。
本来ならばすぐにでも研究テーマに取り組ませたいところですが、
長い目線で当該技術者を戦力にするのであれば、
一度は納期の厳しい開発テーマに取り組ませるべきだと私は考えます。
企業に就職した以上、そこは大学や研究機関とは異なる環境です。
そして私の経験では、厳しい開発業務を経験した技術者ほど、
その後、技術業務推進スキルが高まる傾向にあると認識しています。
既述の過去のコラムである”若手技術者の定着化に向けジョブ型人事を導入したい”を参考に、
開発テーマを設定し、担当者に博士の学位を有する新人技術者を入れるのが一案です。
開発テーマはあまり長いものではなく、短期で完結するものが望ましいです。
可能であれば1テーマだけでなく、複数の開発テーマを完遂させる経験を積ませ、
時間軸を意識した企業ならではの技術業務推進の基本ルールを学ばせることが肝要です。
本コラムに関連する具体的な技術者育成支援の例
今回ご紹介したような内容を企業に対して業務支援する場合、
技術者育成コンサルティングとして対応します。
採用前であれば、職務明文化を目指した打ち合わせの実施と、
その明文化を伴走型で行います。
企業担当者が明文化した職務を当社側で確認する、
というやり取りを複数回繰り返すイメージです。
採用後は候補となる開発テーマを複数挙げていただき、
目的、成果物、期間が明確になっているものを抽出します。
抽出されたテーマは各社の有するフォーマット、
またはそれが無ければ技術業務推進に関する企画書の導入と作成の指導を行い、
開発テーマの設計と新人技術者への伝え方に関する指導・支援を行います。
開発テーマ推進開始後は定期、不定期に進捗管理に関するミーティングを開催していただき、
順調に推進できているようであれば技術報告書の導入に進み、
課題があるようであれば遅延につながっている課題の解決に向けた指示の出し方などについて、
リーダーや管理職層の方々とすり合わせの上、
指示の出し方について合意形成を図ります。
そのうえで、博士の学位を有する新人技術者と不定期に個別面談を行い、
指示事項がきちんと伝わっているか、業務推進に向けた姿勢や対応に問題は無いかを、
丁寧にヒアリングの上で、必要な助言やフォローアップを行います。
まとめ
博士の学位を有する技術者を活用することは、
企業の技術競争力を高めるのに効果的であると考えます。
ただし、そこには受け入れ企業側がその人材に何をしてもらいたいかを整理する、
”職務明文化”ができるという前提が付きます。
どちらかというと受け入れ側の力量が足りているかが重要ということです。
そして、博士課程の本質を考えれば当該過程で学位を修めた新人技術者が産業界の即戦力になることは考えにくく、入社して1、2年の間は社内ネットワークの拡大と複数の短期開発テーマ完遂という、技術者育成において戦力化の基本となる取り組みを行うことが不可欠です。
博士学位保持者の効率的な育成の第一歩の取り組みのご参考になれば幸いです。
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: