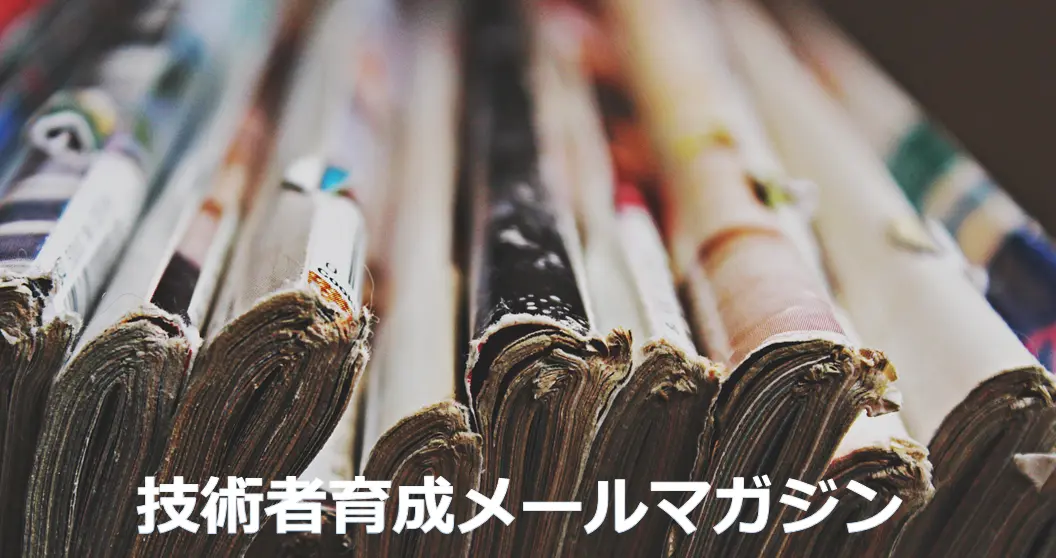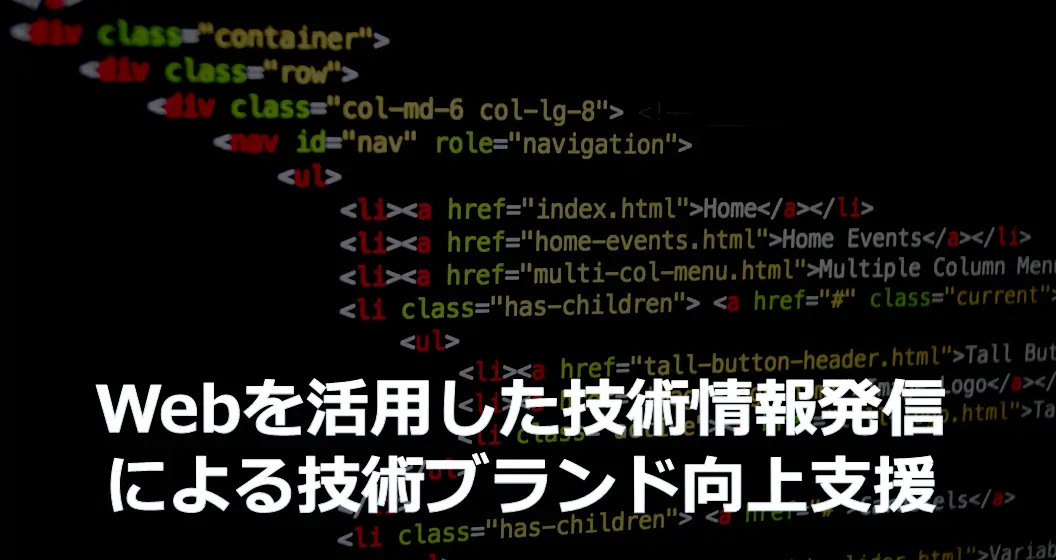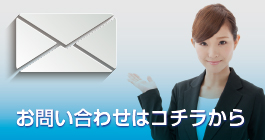技術チーム戦略立案とその伝え方の第一歩
公開日: 2025年7月14日 | 最終更新日: 2025年7月14日
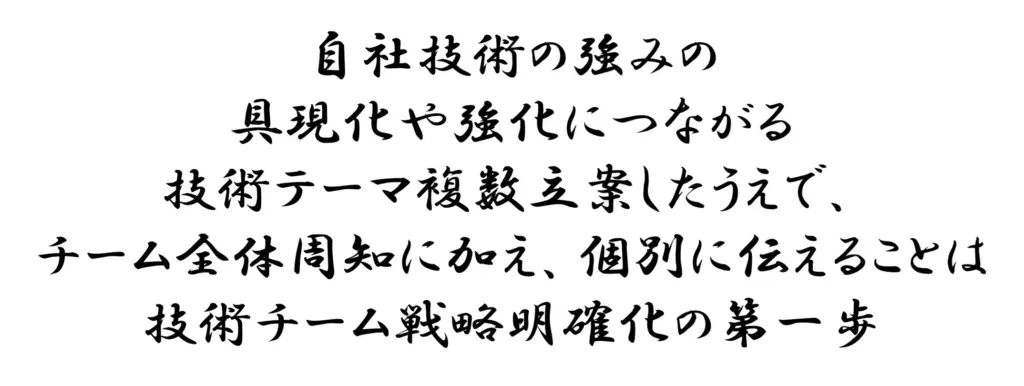
今回は若手技術者も理解できる技術チーム戦略立案とその伝え方について考えます。
多くの企業組織ではプレキャスト型の思考で支配されている
まず”戦略”を考えるにあたり、前提として理解すべきことがあります。
それは多くの製造業企業において、
「目指すべき姿を先に示す”プレキャスト型”が絶対正義」
という事実です。
プレキャスト型というのは、
「ゴールが明確であり、そこのゴールに向かう道の側道に街灯で明かりが照らされている状態こそ”絶対正義”」
という思考パターンであると私は考えています。
ポストキャスト型はまずやってみて、その結果に応じて戦略を随時最適化する
追加としてプレキャスト型と対極にある”ポストキャスト型”の考え方についても触れておきます。
ポストキャスト型はまずやってみて、
その結果を見ながら戦略を随時修正、変更をしていく手法です。
従来にない新しいものを創出するのは、
プレキャスト型よりもポストキャスト型の方が確率は高まるというのが私見です。
ただ、前述の街灯もない暗闇を進むのは正常化バイアスに支配されがちな多くの技術者にとって不安であり、やらない理由を探し、”正論”や”べき論”でその動きが止められることが多いはずです。
恐らく多くの企業で見られる場面だと思います。
マスメディアでよく報道されるような、
「保守的日本」
の典型的な形ともいえるでしょう。
仮に元技術者が経営陣(取締役含め)にいたとしても、
オーナーや株主の前では無力であることを考えれば、
やむを得ない部分も多いといえます。
ポストキャスト型が認められるのはワンマン社長や創業者社長が、
自らの経営責任という名のもと実行できるパターンに限られることが多いかと思います。
では、プレキャスト型の戦略を理解するため、生成AIの力を少し借りたいと思います。
企業組織の戦略立案に関する生成AIの答え
今回用いたのはGemini(2.5 Flash)です。
何故生成AIを用いたかというと、
ここで出てくる答えは多くの人が”正しい(だろう)”と考える答えが得られると思ったからです。
以下、私の問いかけとGeminiの回答を転載します。
生成AIの回答については、すべてを盛り込んでいて分量が多いので、
詳細をご理解いただく必要はありません。
大まかな方向性を感じていただければ十分です。
<問いかけ内容>
企業での組織戦略を考えるにあたり、重要なことは何ですか
<生成AIの回答/Geminiの回答(2025/7/13):ここから>
企業で組織戦略を考える上で、重要となる要素は多岐にわたります。ここでは、特に重要な点を体系的にまとめて解説します。
1. 明確なビジョン・ミッション・バリュー(MVV)の確立と浸透
ビジョン(Vision): 企業が目指す長期的な理想像や将来の姿を明確に描くこと。
ミッション(Mission): 企業の存在意義や果たすべき使命、社会に提供する価値を明確にすること。
バリュー(Value): ビジョンとミッションを達成するための社員の行動規範や価値観を定めること。
これらのMVVが明確に定義され、組織全体に深く浸透していることが極めて重要です。MVVは組織戦略の羅針盤となり、社員一人ひとりの判断や行動の基準となります。これにより、組織に一体感が生まれ、共通の目標に向かって進むことができます。
2. 環境分析と現状把握
外部環境分析(PEST分析、5フォース分析など): 政治・経済・社会・技術の変化、競合他社の動向、顧客ニーズの変化など、自社を取り巻く外部環境を深く分析し、機会(Opportunity)と脅威(Threat)を特定します。
内部環境分析(VRIO分析、バリューチェーン分析など): 自社の強み(Strength)と弱み(Weakness)、保有するリソース(人材、技術、資金など)や能力を客観的に評価します。
SWOT分析: 外部環境の機会と脅威、内部環境の強みと弱みを組み合わせることで、戦略的な方向性を導き出します。
組織の現状把握: 組織内の課題、従業員のエンゲージメント、既存の業務プロセス、コミュニケーション状況などを正確に把握します。サーベイやヒアリングも有効です。
これらの分析を通じて、自社がどのような状況にあり、どこに課題があるのかを客観的に理解することが、効果的な組織戦略を策定する上で不可欠です。
3. 戦略の策定と整合性
目標設定: 分析結果に基づき、具体的な数値目標を含んだ組織全体の目標を設定します。長期的なビジョンと整合性を持ちつつ、短期的な達成目標も明確にします。
戦略オプションの検討と選択: 目標達成のためにどのようなアプローチが可能か複数の選択肢を検討し、自社の強みや外部環境の変化に対応できる最適な戦略を選択します。
「組織は戦略に従う」の原則: 一般的に、企業としての経営戦略(事業戦略)が先にあり、それを実行するために最適な組織体制や人材配置、システムなどを構築するという考え方が重要視されます。戦略と組織が密接に連携し、整合性が取れていることが成功の鍵です。
機能戦略への落とし込み: 組織戦略を、人事戦略、マーケティング戦略、研究開発戦略など、各機能部門の具体的な戦略に落とし込み、連携させることが重要です。
4. 実行計画とマネジメント
計画とリソース配分: 策定した戦略を実行するための具体的なアクションプランを立案し、必要な人材、予算、時間などのリソースを適切に配分します。
リーダーシップの強化: 組織戦略の実行を推進するリーダーシップが不可欠です。特にミドルマネジメント層は、戦略と現場をつなぐ重要な役割を担うため、その教育と育成が重要です。
コミュニケーションと浸透: 策定した組織戦略を、トップダウンだけでなく、ボトムアップの意見も取り入れながら、全社員に理解・浸透させるための仕組みづくりが必要です。説明会、ワークショップ、社内報などを活用します。
権限委譲と責任の明確化: 各部門や個人に適切な権限を委譲し、それぞれの役割と責任を明確にすることで、自律的な行動と意思決定を促します。
人事制度との連携: 組織戦略に沿った評価制度、報酬制度、育成制度などを整備することで、社員のモチベーションを高め、戦略の実行を促進します。
5. 評価と継続的な改善(PDCAサイクル)
モニタリングと評価: 策定した戦略が計画通りに進捗しているか、目標達成に貢献しているかを定期的にモニタリングし、評価します。KPI(重要業績評価指標)などを活用します。
フィードバックと修正: 評価結果に基づき、戦略や実行計画の課題を特定し、必要に応じて修正・改善を行います。環境変化に柔軟に対応し、戦略を常に進化させていく姿勢が重要です。
組織戦略を考える上で役立つフレームワーク
マッキンゼーの7S: Strategy(戦略)、Structure(組織構造)、System(システム)、Skill(スキル)、Staff(人材)、Style(経営スタイル)、Shared Value(共通の価値観)の7つの要素の相互関係を分析し、組織全体の整合性を図るためのフレームワークです。OKR(Objectives and Key Results): 組織全体の目標(Objectives)とそれを達成するための主要な成果指標(Key Results)を設定し、組織と個人の目標を連携させる目標管理手法です。
SWOT分析: 上記の通り、強み、弱み、機会、脅威を分析する基本的なフレームワークです。
これらの要素を総合的に考慮し、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくことが、企業が持続的に成長するための組織戦略を考える上で最も重要となります。
<生成AIの回答/Geminiの回答(2025/7/13):ここまで>
長文での転載となりましたが、
上記の回答を眺めていただきどのように感じたでしょうか。
以下、この内容も踏まえ私見を述べます。
企業全体として考えるべきこととチームレベルで考えるべきことを分ける
組織戦略という単語を意図的に使ったこともあり、
企業戦略と組織戦略が一体化している印象です。
例えば、
1. 明確なビジョン・ミッション・バリュー(MVV)の確立と浸透
については、どちらかというと企業戦略です。
補足として、ここはミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の順番の方が正しいようです。
(生成AI固有の間違えと推測します)
技術チームはこの企業戦略をベースにチーム戦略を考えます。
一方で項目2から5はどちらかというとチーム戦略に近い内容用です。
特に
3. 戦略の策定と整合性
にあった、
「長期的なビジョンと整合性を持ちつつ、短期的な達成目標も明確にします。」
という部分が技術チームレベルで立案すべき戦略との理解です。
プレキャスト型の典型
今回生成AIから得られた回答は、盛りだくさんでありつつも、
個人的にはきちんと要点を網羅していると感じました。
そして前述のMVVは、結論から言ってしまうとプレ/ポストキャスト型どちらでも必要なことです。
そのため、企業組織としてMVVを決定することについては、
技術チーム戦略立案の大前提といえます。
一方でプレキャスト型に縛られていると感じる部分も多々あります。
一番は
2. 環境分析と現状把握
という部分です。
予め情報を入手してリスクを低減したい、
という気持ちが前面に出ています。
4. 実行計画とマネジメント、5. 評価と継続的な改善(PDCAサイクル)についても、
計画が最重要視されていることが分かります。
日常業務では計画は重要ですが、
戦略立案の時点で計画を明確化したいと感じる考えは、
プレキャスト型典型といえます。
例えば戦略についてPDCAはポストキャスト型でいえばDCAでいいと思います。
Dだけでもいい、といった割り切りがポストキャストでは求められます。
ポストキャスト型は期間を決めて試行錯誤する自由空間が必要
プレキャスト型に対してポストキャスト型でも期間は決めていいと思いますが、
自由に試行錯誤する空間が必要です。
予算と期間が指定されたら、
MVVを念頭にまずは色々とやってみるのです。
その中から、
「これを戦略として掲げよう」
というのが、ポストキャスト型の考え方です。
MVVという軸からぶれてはいけませんが、自由に試行錯誤することで、
地に足の着いた戦略を考えようというのが基本にあります。
この試行錯誤の基本に置きたいのが、
以降で述べる”自社技術の強み”です。
ここまでの話を踏まえ、技術チームの戦略立案と伝え方の話に入っていきたいと思います。
研究開発を担う技術チームの戦略立案はポストキャスト型が圧倒的に有利
前提を研究開発を担う技術チームとします。
このような場合、技術チーム戦略立案においてはポストキャスト型を採用することを強く推奨します。
その理由を述べます。
技術業界動向や他社動向を踏まえて、という枕詞が付く戦略は手垢がついている
研究開発を担う技術チーム戦略立案において、
- ・技術業界動向
- ・競合他社動向
を踏まえて、考えるべきという思考をされているのであれば、
その時点でポストキャスト型です。後追いの要素が強いからです。
そしてこのような”動向”という単語が出てきている時点で、
他も似たようなことをやっている可能性が高く、
「新しい技術の創出や既存技術の発展」
を主業務とする研究開発の戦略であるにも関わらず、
あえてレッドオーシャンに飛び込むという矛盾が生じているのです。
生成AIやWeb検索といった調べれば出てくるような情報は、
世界中の競合他社の目に触れていることを前提にすべきでしょう。
「周りはよく見えていないけど、まずはやってみる。
実行によってしか見えないものがあるはずだ。」
そのような思考が研究開発を担う技術チーム戦略を考える方々に求められる姿勢といえるでしょう。
ポストキャスト型をベースにするというのが、
当該チーム戦略立案の前提といえます。
自社技術の強みを抽出する
ポストキャスト型思考という前提が整ったうえで、
少しずつ具体的な話に入っていきます。
最初にやるべきは、
「自社技術の強みの抽出」
です。
研究開発を担う技術チーム戦略立案の基本は、自社技術の強みを理解することから始まります。
新しいことの創出は今まで培った技術的な強みを土台とすることで競争力が出る
研究開発のような、未知の領域に踏み込むにあたり重要なのは、
「自社技術の強みを土台とする」
ことです。
例えば機械学習や自動化技術などを含むDXが注目されていますが、
このような昨今話題の技術を導入してそれらが活きるのも、
「自社技術の強みとの相乗効果が出る場合に限る」
のです。例えばDXは業務インフラの一部に過ぎないのです。
これまで蓄積してきた自社技術を無視して、妥当な技術チーム戦略立案は不可能でしょう。
自社技術の抽出に向けた手順と留意点を以下に述べます。
自社技術の強みは自社が一番気が付かない
まさに灯台下暗しです。
自社では当たり前すぎて常識となって技術が、
第三者的に見ると差別化できるものだった、
ということは決して珍しいことではありません。
この自社技術の強みの抽出が大変難しいものであるため、
できれば他部署の技術者や、
場合によっては社外から第三者目線を導入するといったアプローチが必要です。
自社技術の強みの抽出のためには立場と年齢を超えた”個別聴取”によるキーワードの羅列が第一歩
具体的に自社技術の強みを抽出したいのであれば、
立場や年齢を超えたキーワードの羅列が第一歩です。
この場合、技術チームのような形で集まらず、
リーダーや管理職が技術者一人ひとりにヒアリングすることが肝要です。
ヒアリングするにあたって、
リーダーや管理職は一切口を出さず、
ひたすら吐き出させるようにしてください。
抽出が終わったら、一覧にして再度個別の意見を聴き、自社技術の強みとして感じたものを一つに絞ってもらう
一通りのヒアリングが終わったら、それを一覧にします。
この一覧データを再度チームに属する技術者に個別に見せ、
「どのような観点が自社技術の強みにつながるか、
そしてその理由は何か」
を再度聴きとってください。
この場合の強みについては複数ではなく、
できれば最も強みと感じる内容を1つに絞らせるよう、
リーダーや管理職は聴き手として技術者の話をまとめてください。
抽出された自社技術の強みの具現化や強化に向けて技術テーマを立案
自社技術の強みの絞り込みが終わったら、技術テーマの立案に向けて動きます。
以下、ポイントを述べます。
各技術者が自社技術の強みと感じたものを技術テーマとして立案させる
各技術者が自社技術として選んだ自社技術の強みについて、
「それを具現化や強化するための技術テーマを立案してほしい」
とリーダーや管理職は指示を出してください。
発言者本人が自社技術の強みとして感じたことなので、
何かしらのイメージを持っている可能性が高い上、
自らの発言から始まった内容であることから当事者意識を持ちやすい、
ということが背景にあります。
若手技術者の場合、いきなりテーマの企画化は難しいかもしれません。
技術テーマ企画に向けた教育を行いつつ、
リーダーや管理職が技術テーマ企画化に向けた支援を行ってください。
技術テーマ企画化に関しては過去のコラムや連載でも取り上げたことがあります。
※関連コラム
第15回 企画力を応用した技術テーマ企画書の書き方 日刊工業新聞「機械設計」連載
第12回 技術テーマ立案に不可欠な技術者の「企画力」鍛錬の勘所 日刊工業新聞「機械設計」連載
技術テーマは最長1年程度で、仮にリーダーや管理職から見て無駄と思ってもやらせることがポイント
技術テーマについての留意点を加筆しておきます。
ここでの技術テーマは自社技術の強みを確認、理解、検証するのが目的であるため、
仮にわかりきっていることなので無駄だとリーダーや管理職が感じたとしても、
否定せず承認してください。
期限は最長1年程度で、できれば数カ月以内に終わるスケールであることが肝要です。
技術テーマが出そろったら、それを技術チーム全体で周知
自社技術の強みの具現化や強化に向けた技術テーマが出そろったら、
それを技術チームミーティングで全員に共有してください。
技術テーマの大小はあると思いますが、
リーダーや管理職から発表される時点で、
それは技術チームの決定事項として伝えてください。
これが、若手技術者も理解しやすい
「技術チームの戦略」
になります。より正確には、
「技術チーム戦略の前段階」
ですが、何をやるべきかという目の前の技術業務の明確化という意味で、
若手技術者にとって大変わかりやすい戦略として受け止められます。
若手技術者が求める戦略は抽象的な表現よりも具体的な技術テーマ
今回ご紹介したような技術テーマは具体的なものになります。
俯瞰的に技術チームを見ることのできない若手技術者にとって、
冒頭紹介したようなMVVは抽象的であり、
具体的に何をすべきかわかりにくいと感じるはずです。
それよりも技術チームの求める具体的な技術テーマを示してもらった方が、
技術チームとして若手技術者を含む技術者たちに何をしたいのかが明確になるのです。
追って若手技術者には個別に技術テーマ一覧を伝える
技術チーム全体でのミーティングでは、
若手技術者は仮に意見や質問があっても”発言しにくい”かもしれません。
そこで、リーダーや管理職は個別に若手技術者に対して、
改めて自社技術の強みに関する技術テーマの一覧を見せ、
説明をしてください。
ここでの説明と会話を通じ、若手技術者が自社技術の強みの具現化や強化に向け、
チームが何をするのか理解できるようになります。
自社技術の強みの具現化や強化に向けた動きを繰り返す中で、技術チーム戦略が見えてくる
今回ご紹介したのは自社技術の強みの具現化と強化に向けた動きについて、
技術チームが統一された動きをするための”初期段階”といえます。
本丸である技術チーム戦略は、ここまで述べてきたような自社技術の強みに関する取り組みを繰り返す中で見えてくるものです。
一周しただけでは何もわからず、
再度同じような取り組みをする必要が出るかもしれません。
このような一見遠回りに見える自社技術の強みの理解に向けたテーマの推進こそが、
「自社はどの技術で勝つのか」
をあぶりだす最適な手法の一つだと考えます。
ポストキャスト型の取り組みであるため、
見えにくいといった側面もありますが、
技術チーム戦略を考えるにあたり、
「技術テーマの推進という実際の結果」
という”よりどころ”があるからこそ、
不必要なリスクヘッジをしようという恐怖心を抑えることができるといえます。
まとめ
研究開発の技術チーム戦略は、
自社技術の強みの具現化とその強化に向けた、
”実際のテーマ推進”という”実体験”が無いと、
抽象的な表現にとどまってしまい、結局分かりにくいものとなります。
特に研究開発はポストキャスト型のように、
ある程度見えない世界に飛び込んでいく勇気が不可欠です。
これが無いと、新しい技術の創出は困難になります。
まずは技術チームに属する各技術者に自社技術の強みを抽出させたうえで、
その当事者に技術テーマを立案させます。
リーダーや管理職はこの一覧を技術者個人並びに若手技術者にも個別に共有し、
理解を深めさせます。
ここで重要なのは戦略を聴く側の若手技術者に当事者意識を持たせること。
そのためには若手技術者が自社技術の強みと感じた内容について、
その本人に技術テーマを立案させる必要があります。
技術チーム戦略立案が何故自社技術の強みに関する技術テーマと関係あるのか、
と感じるかもしれませんが、
このような自社技術の強みを技術テーマ推進という実務を通じて理解していなければ、
本当の意味での技術チーム戦略立案まで到達できないのです。
一見無駄に見えるかもしれませんが、
本当に無駄かは一度やってみなければならない。
そのようなことを少しでも感じていただけたのであれば、
今回の内容をご理解いただけたといえます。
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: