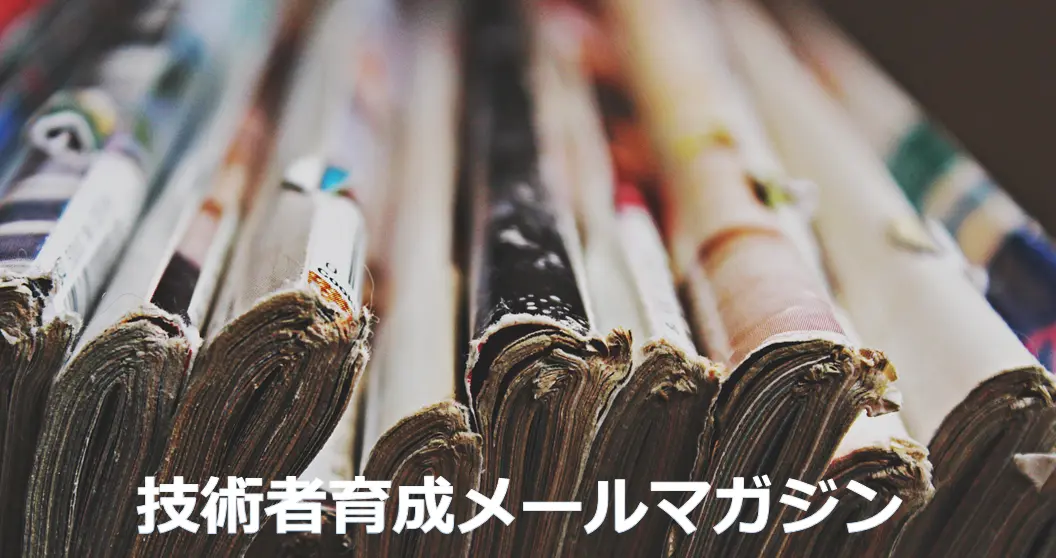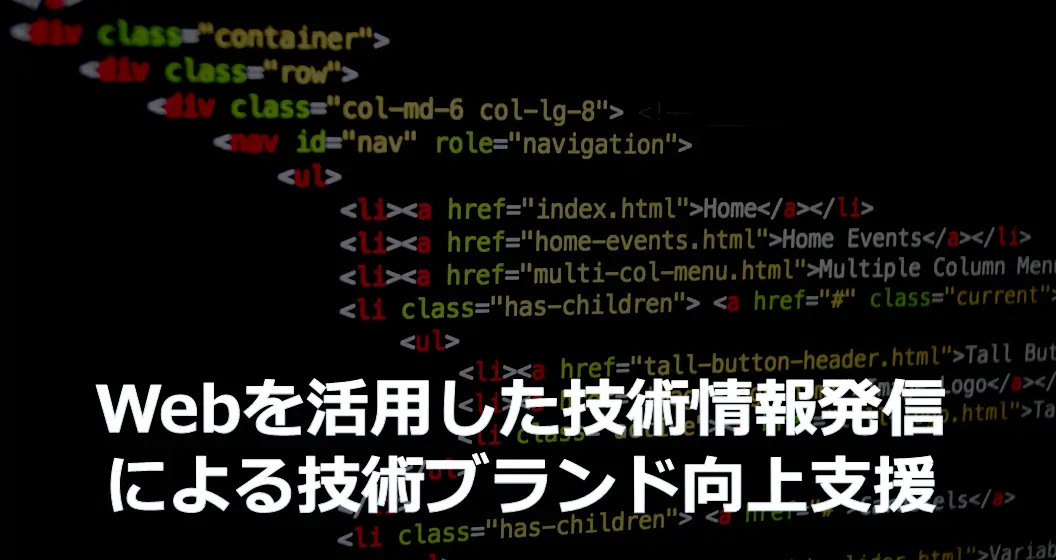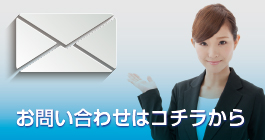研究開発の実験や試験の安定化につながる手順書の効率的な準備法
公開日: 2025年7月28日 | 最終更新日: 2025年7月28日
タグ: OJTの注意点, メールマガジンバックナンバー, 技術の伝承, 技術報告書, 技術者の普遍的スキル, 技術者人材育成
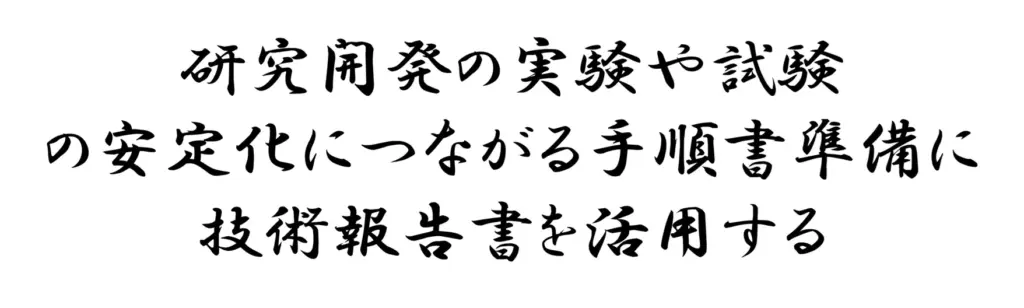
製造業企業に勤務する技術者は通常、実験や試験を業務の一環として行います。
当該業務は危険を伴う場合があり、安全性に考慮した”適切な手順”を踏むことが重要です。
しかし、いざこの手順を経験の浅い若手技術者に教育しようとした場合、
その時間が取れないという課題が生じます。
ここでリーダーや管理職は技術者育成の過程で構築した業務インフラを”二次利用する”という、
思考の変換が重要となります。
今回は若手技術者の安全な業務推進を後押しする、
実験や試験の”手順書”の整備について考えます。
研究開発の現場では手順書が整備されていないことが多い
定常的に実験や試験を行う現場では、前述の通り安全性の観点からも手順書が整備されているのが基本です。
例えば私が居た航空機業界では、
徹底した品質管理の観点からかなりの細かい手順にわたるまで記載された手順書と、
それに紐づく工程規格があり、それをさらに製造する部品図面に紐づけることで、
徹底した工程管理をするのが通常です。
私自身の工程規格の構築の経験においては、
細かいニュアンスを理解してもらうために図を多用するなど、
様々な工夫をしていました。
恐らく量産工程の品質管理に近い技術者も、
上記と類似の管理下で業務を進めていると考えられます。
一方で研究開発は様々な実験や試験を行う必要があり、
その多くが”非定常”です。
「手順には柔軟性が必要だ」
という考えから手順書のようなルールを後回しにすることが多く、
結果的に研究開発の現場では手順書があまりない、
ということになります。
若手技術者にも中堅技術者にも手順書が大きな役割を果たす
手順書の価値が認識されるのは、若手技術者が実際に試験や実験を行うようになった時です。
包括的な手順を指導するのは簡単ではない
限られた実験や試験手順の一部を説明する場合、
中堅技術者が手取り足取り教えることで普通であれば若手技術者もその内容を理解し、
作業を再現することができるでしょう。
しかし実験や試験という手順全体を理解させ、
かつ各手順におけるポイントを若手技術者に把握させることは、
中堅技術者にとって簡単なことではありません。
研究開発のような評価対象が多様で、
しかし得たいデータのばらつきを最小化したいというケースでは、
いかにして”工程を安定化させ、データのばらつきにつながるような要所を手順として理解するか”がポイントとなります。
手順の要点を理解することは作業安全性に直結する
前述の通り手順の要所を理解することは工程を安定化させ、
取得データのばらつきを抑制することにつながります。
加えて大変重要なのが、
「作業安全性の向上」
です。
研究開発において取得データのばらつきを抑制し、その質を高めることが重要なのは言うまでもありませんが、それ以上に重要なのは業務を行う”技術者の安全”です。
製造業企業において安全性は常に”最上位概念”であり、ここは絶対にぶれてはいけません。
安全性に関する要点がある場合、
手順書に必ず明記することが肝要です。
ある程度教えたら、若手技術者が手順書で自己学習することが業務理解の近道
手順を教えることは、中堅技術者にとって負担になることが多いです。
自らの業務を進めなくてはいけない一方、
当該業務を止めて若手技術者という異なる人間に実験や試験の手順を教えることは、
自分の時間をそれに”割く”感覚でしょう。
ここで手順書があれば、
最初は手取り足取り教えなくてはいけませんが、その後は
「手順書を基本に若手技術者が自己学習することが可能」
になります。
この自己学習こそが、手順理解最短の道であり技術者育成の基本です。
自己学習の間、中堅技術者は若手技術者に時間を割く必要がありません。
手順書を整備することは”中堅技術者の時間捻出”という大きな役割を果たすのです。
次に実際に手順書を整備するにあたっての取り組みについて考えます。
手順書をゼロから整備するのは重労働
仮に実験や試験に関する手順書が社内に無かったとします。
これをゼロから整備しようとするのは大変です。
既に述べた通り研究開発は様々な実験や試験を行うのが普通で、
仮に一つの実験や試験設備を例にとっても、
様々な工程として派生手順が生じることが多いのです。
よっていきなり手順書を整備しようとするとその業務量は膨大となり、
技術者の工数の大部分がとられることになります。
リーダーや管理職としてはいきなりそのような業務を現場の技術者に行わせる判断はできず、
最終的には手順書の整備という業務を後回しにすると想像します。
上記のアプローチであればマネジメントを行う方の判断としては妥当です。
一方で技術者育成の観点から言えば、異なるアプローチを検討すべきでしょう。
技術報告書は手順書の元になる情報の宝庫
これまで技術者育成に大変重要な業務インフラとして何度も取り上げてきた技術報告書。
その価値を認識される方が増えたのは、
当社の技術者育成事業を進める中で実感しつつあります。
実はこの書類が手順書作成という取り組みに大きな貢献をします。
何故ならば、技術報告書の中には既に手順書に該当する情報が盛り込まれているからです。
技術報告書の基本構成の復習
技術報告書の基本構成について改めておさらいをします。
構成要素のうち、最も重要なのが背景、目的、結論、概要という4項目です。
これらの詳細については以下の連載や拙著にて書き方の事例を含めて記載しています。
※関連連載/関連書籍
第7回 技術報告書を構成する最重要4項目 日刊工業新聞「機械設計」連載
上記の重要4項目はA4で1ページに収まるよう要点を抽出し、
かつ必要な情報をきちんと盛り込むことが肝要です。
そして2ページ目以降が内容であり、
この内容は実験/試験、結果、考察、参照文献で構成されます。
※参考連載
第8回 技術報告書の2ページ目以降を構成する「内容」 日刊工業新聞「機械設計」連載
内容を構成する主項目の一つ”実験/試験”が手順書と関係があります。
技術報告書中の”実験/試験”は手順書の原案となる
技術報告書中の実験/試験で重要なのは、
「実験/試験の作業を再現できるレベルで、詳細を記述する」
ことです。
つまり技術報告書内の実験/試験の項では、
手順の一つひとつを丁寧に記述されています。
この情報があるからこそ、技術報告書は技術の伝承にも活用できます。
※関連コラム
このように記述された実験/試験の内容は、
詳細記載を基本とする手順書の原案となります。
技術報告書中の”実験/試験”は過去形であるため現在形への修正は必要
注意点として、技術報告書中の実験/試験に関する記述は、
事実記載のため必ず過去形です。
よって、手順書に活用する場合は現在形に修正する必要があります。
ここは不可避なひと手間とお考え下さい。
手順書を一度整備すれば、技術報告書の作成にも二次利用できる
技術報告書作成は、技術者が自らの業務理解のため時間をかけてでも手を抜かず、
丁寧に作成し続けることが求められます。
”実験/試験”については作業の再現性を実現することが目的であるため、
手順を理解できているという前提ではありますが、
手順書のような適切な情報源からコピー/ペーストすることで、
技術報告書の実験/試験の項に活用し、当該書類の作成効率を高めるという考え方もできます。
このように、手順書を一度整備すれば技術報告書作成にも二次利用できます。
技術報告書を作成すれば手順書を整備することにつながり、
さらに手順書が整備されればその後の技術報告書の作成効率を高めるという、
技術者育成を実現しながら業務効率化を達成することが可能となります。
本コラムに関連する一般的な人材育成と技術者育成の違い
一般的な人材育成に関して、実験/試験の手順書に関したものはあまり多くないものと考えます。
総合職の従業員が実験や試験を行うことはあまりない、
というのが主因だと考えます。
それに対して技術者育成では、
今回主に紹介した研究開発に加え、
品質保証のような徹底した安定工程が前提となる技術業務を想定するため手順書を重視しています。
そして手順書と技術報告書に関係性を持たせることで、
書類作成に関して時間をかけてでも”質を高める”ことを徹底しつつも、
作成された情報を徹底的に二次利用、三次利用するという、
効率を考慮した取り組みとして進めることを推奨します。
技術者育成は長丁場であり、継続性が重要であるためです。
以上のような質の高い活字情報の蓄積とその活用により、
技術者育成の観点で最重要の”論理的思考力”の基礎を鍛えます。
※関連連載
第4回 技術者は論理的思考力をどう鍛えるか 日刊工業新聞「機械設計」連載
本コラムに関連する具体的な技術者育成支援の例
技術者育成コンサルティングとして対応します。
初期段階では技術報告書のテンプレート導入から始めます。
これは多くの企業において、技術報告書が適切な形態で運用されていないことが念頭にあります。
その後、実験や試験という実作業を伴う業務の中から複数を選定し、
技術報告書作成の練習をOJTで繰り返します。
技術報告書がある程度作成できるようになった段階で、
実験/試験に記載された内容を手順書に転載するための優先順位付け、
並びに具体的な記載例をご提案します。
ここでは手順書への画像活用の重要性や、
安全と技術的なポイントを各工程に加筆する、
といった手順書構成の案も説明します。
その後は管理職層と議論をしながら、
どのように現場に導入していくかを議論のうえ、
現場での運用を進めながら必要に応じた修正、改善を加えていきます。
これらの業務を通じて手順書の整備に加え、
技術報告書作成を定常化することを目指します。
まとめ
手順書は実験や試験を適切かつ安全に行うために不可欠な書類です。
特に作業安全性は製造業基調における基本中の基本であり、
ここに手を抜くことは許されません。
このような書類は研究開発を中心に多岐にわたるため、
ゼロベースから整備するには大変な労力がかかります。
ここでリーダーや管理職に必要なのが、
技術報告書の実験/試験の項目内の内容を手順書に流用する、
という技術者育成のコンセプトから延長させた柔軟な考え方です。
さらに手順書を他の技術報告書の実験/試験の項の記載に再利用し、
技術報告書作成負荷を下げることも、
技術者育成を継続的な取り組みとするのに必要なアプローチです。
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: