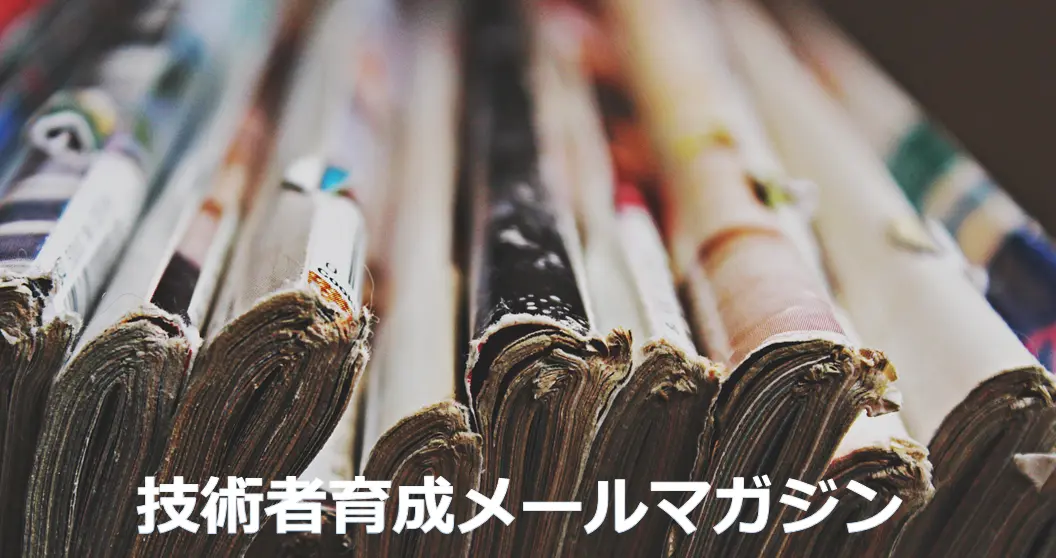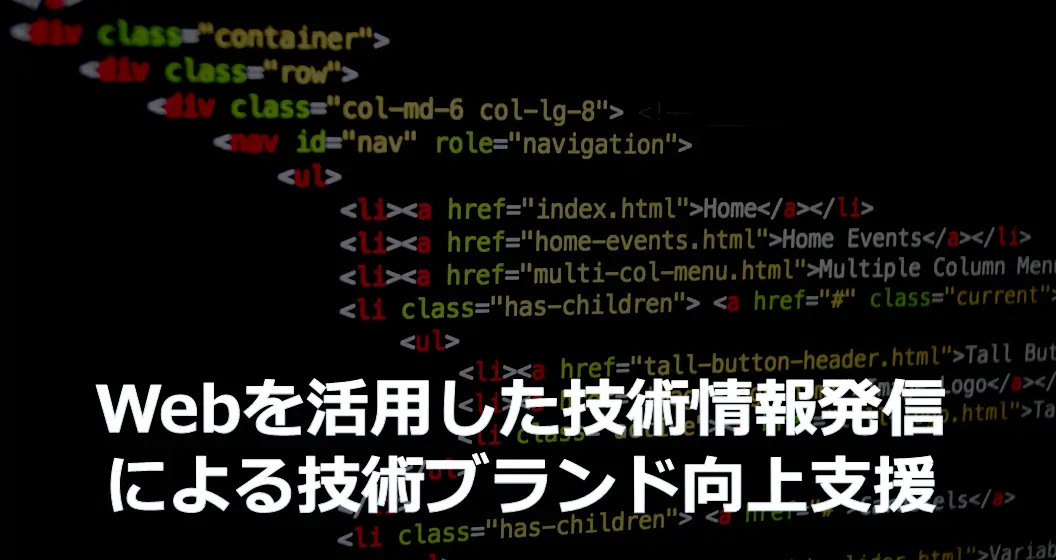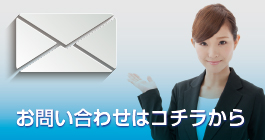若手技術者の出張報告書を読んでも次の指示を出しにくい
公開日: 2025年10月6日 | 最終更新日: 2025年10月5日
タグ: OJTの注意点, メールマガジンバックナンバー, 報告書, 打ち合わせ・出張, 技術者人材育成
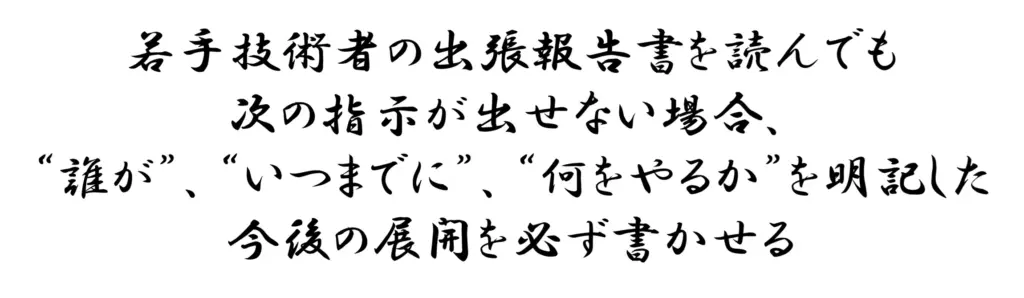
若手技術者に出張対応を任せることは、技術者育成の観点でも重要です。
出張の目的と出張先で期待する成果を明確に伝えたら、
出張対応は若手技術者に任せることで、
リーダーや管理職の業務時間捻出にも効果的であることは過去のコラムでも述べています。
※関連コラム
出張報告書は必須
前出の”出張対応を任せる”にはいくつかの条件がありますが、
大前提というべきが出張報告書の作成です。
過去のコラムでも述べている通り翌営業日までの提出が基本で、
遅れたとしても2営業日以内に提出させることが不可欠です。
情報の鮮度に関する感覚の重要性も過去のコラムで述べています。
※関連コラム
本点については、リーダーや管理職は絶対に妥協してはいけません。
出張報告書に効率を考慮した簡略化といった概念を導入した時点で、
技術者の質の低下が始まっていると認識すべきです。
若手技術者に要求する以上、リーダーや管理職も例外ではない
これは当然ですが組織として出張業務の後の出張報告書を業務のインフラにするにあたり、
作成要件に立場は無関係です。
リーダーや管理職であろうと、
自らが対応した出張に対して出張報告書を期日内に作成し、
共有しなくてはいけません。
このように自らも実行できることは、視点を変えれば
「若手技術者の作成した出張報告書の内容を理解し、
必要に応じた指摘や指導ができる」
ことになります。
今までの社内ルールがどうだったかは別として、
技術者育成を前に進めたいのであれば、
指導する側も当事者として取り組む覚悟が必須です。
出張報告書を読んでも次に何をさせるべきか指示を出しにくい
若手技術者が目的や成果物を意識して出張対応をし、
期日通りに出張報告書を作成、提出したとします。
しかし読んだ後で、
「結局のところ、次に何をさせるべきかの指示を出しにくい」
ということが起こることがあります。
出張先で決まった次のアクションが未記載
その理由の一つが、
「出張先で決まった次のアクションが未記載」
によるものです。
出張報告書も技術報告書同様テンプレートがあるのが普通です。
その中で次のアクションに関する記載要件が明確であれば問題ありませんが、当該要件が無い、または該当するテンプレートもなく出張報告について流動的な運用をしている企業の場合、出張報告書を読んだとしても次の段階で若手技術者に何をさせるかの指示に必要な情報が無いこともあります。
よって、出張先で決まった次のアクションに関する情報を出張報告書に記載することは大変重要です。
では、出張報告書に記載すべき次のアクションとは何でしょうか。
技術者が意識として抜けがちな今後の展開
出張報告書でいうと
「今後の展開」
という項目がそれに該当します。
記述方法にはいくつかのポイントがあります。
誰が、いつまでに、何をやるか、を明記
技術者は技術的な議論ばかりに目が行ってしまい、
出張時の打ち合わせを経ての次の展開まで目がいかないことが多い。
そこで、その意識を技術者に引き戻すため、
今後の展開という項目を出張報告書の必須事項として項目設定し、
それを書かせることが肝要です。
その際に重要なのは、
- ・誰が
- ・いつまでに
- ・何をやるか
の3点を”必ず”網羅することです。
”誰が”は出張対応の後、動く当事者が何者なのかを定義
技術者が良く忘れがちな観点です。
例えば協力企業先での試験の立ち合いを出張で対応したと想定してください。
立ち合い時の評価は終わったものの、残った評価項目もあるため継続になったとします。
既に評価すべきサンプルや供試体がすべて協力会社先にあるのであれば、
出張対応者は評価に関して対応は必要なく、
次のアクションである継続評価の当事者は”協力企業(の担当者)”になります。
しかし継続評価が必要であるものの、その評価対象物がまだ協力先に無く、それをこちらで準備して後日送らなければならない、ということであれば継続評価の前段階としてサンプルや供試体を送るという対応が必要であり、その際の当事者は”自社(出張者)”になります。
誰が当事者かを意識することは、技術者、特に実務経験の浅い若手技術者は意識として欠けることが多く、出張報告書という形で報告を義務付けることが効果的です。
”いつまでに”は次のアクションの締め切り
これも技術者の意識から良く抜け落ちる感覚です。
”時間軸”とも言えます。
時間は有限ですし、何かを前に進めるためには期限を決めることは、
技術者はもとより社会人の常識です。
特に技術者は大学(院)で特定テーマの研究に取り組むことが多く、
そこでは徹底的に事実を突き詰めることだけを求められるため、
時間軸に対する要求は比較的緩やかです。
これは学術界で活躍をする人材を育成するには妥当な方針です。
しかし、産業界は時間軸に縛られて業務が進むことが多く、
期日を考えずに業務を進めることは様々な業務停滞と、
それを挽回しなければならないという突発業務の発生による現場の疲弊につながってしまい、
組織としてのパフォーマンスの低下につながります。
よって技術者は出張報告書の段階で、常に”いつまでに”を意識することで計画の基本構造を決め、
そこからずれないよう複数の業務対応配分を考え、
必要に応じてリーダーや管理職からの指示を仰ぐという姿勢が必要です。
前出の出張対応の例であれば、
継続評価をいつまでには終了して速報レベルでの報告を得られるか、
または追加評価用のサンプルや供試体の発送をいつまでに行うか、
といったことが”時間軸”の明確化の一例となります。
”何をやるか”は次のアクションそのものであり、具体的でなければならない
これは次のアクションそのものになります。
本観点は出張の目的や求められている成果を明確化する中で明らかになっているはずですので、
それを意識して出張対応を行うよう若手技術者に指示をすれば、
リーダーや管理職としての対応は十分かと思います。
出張報告書としてのポイントはより具体的に記述をすることにあると思います。
同様に前出の出張対応を例にすると、
以下のような粒度での記述が必要です。
- ・サンプルAに対する、高温環境(150℃)での150N加振試験を3000サイクル実施する
- ・高温環境(150℃)での150N加振試験用のサンプルAを3個○○氏宛に送付する
ここに主担当が誰なのか、そしてそれはいつまでかという情報を追加することが、
若手技術者の作成する出張報告書で”今後の展開”として明記させたい内容となります。
出張報告書作成にAIを使用することには懸念がある
これは追加として述べておきたい点となります。
昨今は生成AIの進化により、出張報告の元となる動画や音声から議事録を自動で作成し、
それをベースに出張報告書を作成することも可能な時代です。
私自身も生成AIをLLM(Large Language Models、大規模言語モデル)の部品として活用し、
上記のような業務フローを様々な情報を参照しながら構築し、
実際に作成される書類の質を検証することを継続しています。
業務効率だけを考えれば、抜け漏れが少なくなるという意味で妥当な側面もあります。
一方で懸念点があります。
入力した時点で情報が流出するリスクがある
生成AIと切っても切れないのが情報流出のリスクです。
出張対応が顧客情報や技術的な機密と無関係ならば問題ありませんが、
研究開発など、これからのことをやろうとしている際に生成AIを使用するのは、
個人的には当該リスクがある以上、推奨できないという立場です。
クローズした環境(サーバ)での情報のやり取りが可能な企業であれば、
そのリスクが低減できる可能性もあります。
ただ入力したものが外に流出しているかもしれない、
という意識を持つことがこの手の技術を使用する際に必要なことだと思います。
※関連コラム
技術者として本質的な力量が上がらない
技術者育成の観点から言うと、ここが最も大きな懸念です。
生成AIはもっともらしい回答を、
しかも場合によっては技術的専門用語も用いながら生成することができます。
仮に経験の浅い若手技術者であっても、出張先で見聞きしたものをそれ相応に情報を生成AIにインプットすれば、あたかもある程度、経験のある技術者の知識レベルで出張報告書として仕上げることができるでしょう。
しかしこれはあくまで書面上、さらに言えば表面上の話です。
本当の意味で技術者に求められるのは”知恵”であり、
周りに支援なく、何が起こっているかもわからない中で、
技術的課題を乗り越える、または乗り越えようとする経験の蓄積でしか身につきません。
”知恵”は知っているというレベルの”知識”とは階層の違うスキルで全くの別物であり、
一番の特徴は具体的な道筋を含む提案ができ、
必要に応じて当事者として実行できることにあります。
※関連連載
第6回 新人技術者の“知っている”ことが実務で使えない 日刊工業新聞「機械設計」連載
生成AIばかり使っていると技術業務という実務を通じた経験値は上がらず、
言ってしまえば中途半端な専門知識はある一方で、
それを活かしてどのような行動を起こすべきかという
「技術業務の遂行」
まで到達できない評論家止まりになります。
しかも、自分の力量がどのレベルかを見失ってしまいます。
実は知恵を有する技術者にとって、
国籍や性別、技術業界問わず、
出張報告書の類の書類を見るだけでその力量が本物かどうかを見極めることはそれほど難しくありません。
少なくとも現段階では、知恵を有する技術者の作成した報告書のような書類と、
生成AIの作成した当該書類には雲泥の差があります。
私も時折生成AIが作成したであろう文書や、
それに該当する知見をベースとした議論に直面しますが、
その技術的な土台の弱さは一目瞭然です。
近年、生成AIの質の低いアウトプットは受け手の労力を強いることが問題となっており、
そのような低質なアウトプットのことをワークスロップ(Workslop)というようです。
上記の基本の無い生成AIのアウトプットは、それを相手にしなくてはならない、
例えばリーダーや管理職の時間とモチベーションを奪うことになるのです。
※関連情報
ついに、AIが生成する質の悪いコンテンツに名前がついた。その名は「ワークスロップ」/GIZMOOD
生成AIに依存した表面上のスキルはその中身の技術者を変質させる
生成AIに依存し続けた結果、
知ったかぶりの知識依存者という印象を与え続け、
周りからも信頼を得られず、組織の荷物へと変質していくことになります。
労せずして獲得したスキルは、本質的なものではないことを今一度認識すべきでしょう。
※関連コラム
やらなくてはいけないでしょうかと発言する若手技術者は組織の荷物となる
本コラムに関連する具体的な技術者育成支援の例
今回ご紹介したような内容を企業に対して業務支援する場合、
技術者育成コンサルティングとして対応します。
具体的な支援として、まずは出張報告書の基本構成となるテンプレートの設計を行います。
当社から提案を行い、実情と合わせこみながら基本構成を変えずに、
各社に合わせた表現方法などを必要に応じて取り入れます。
その後は、添削・承認・保存ルートを含めた出張報告書運用に関する合意形成を行った後、
技術チームに情報を共有し、運用を開始します。
その後は適宜添削の指導や支援を行いながら、
まずは添削するリーダーや管理職の指導を行います。
平行して若手技術者を中心とした技術系社員向けに出張報告書に関する研修を複数回行い、
底上げと天井の引き上げの両方を行っていきます。
まとめ
若手技術者にとって出張業務は実務経験を積むために重要です。
前提となる出張報告書を通じ、遠隔地で見聞きしたこと、議論したことをリーダーや管理職に報告し、
次の展開に関する指示を受けることは、若手技術者のルーチンにすべきことでしょう。
しかし技術報告書に今後の展開が無いと、
出張対応による業務成果の質が低下してしまいます。
誰が、いつまでに、何をやるかを強く意識して出張業務を推進し、
それを出張報告書に明記することを繰り返すことが、
出張中に技術的な議論に陶酔して出張の目的や求められている成果を見失うことの回避につながります。
技術者の出張報告書の必須報告項目に取り入れていただきたい内容です。
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: