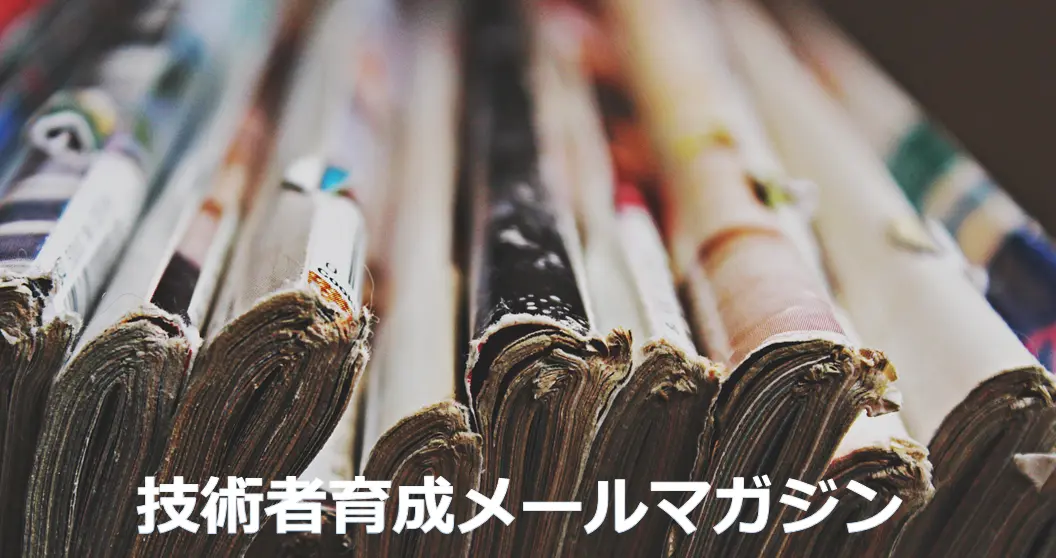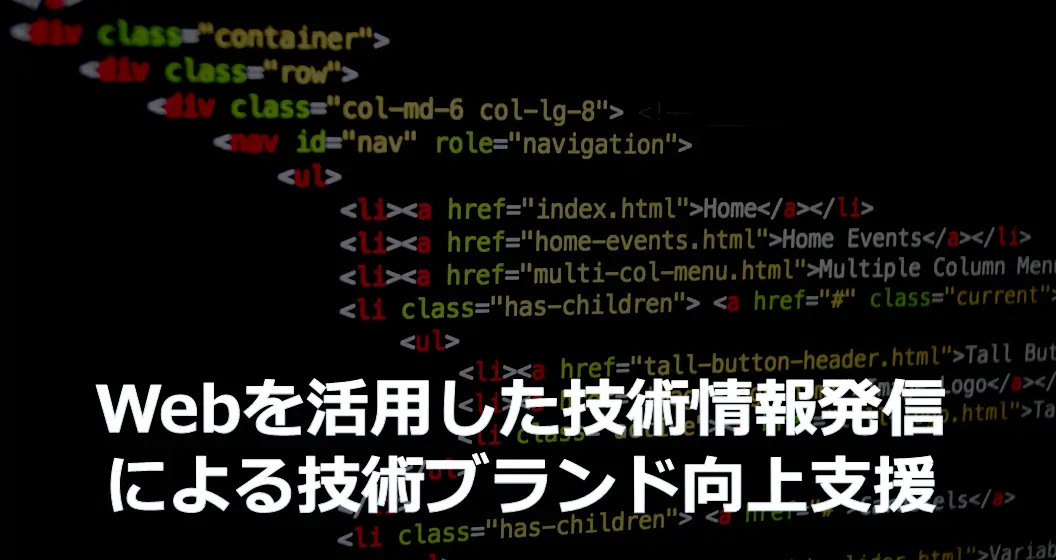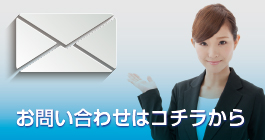出張同行の若手技術者に必須の出張報告書(技術情報入手の場合)とは
公開日: 2025年5月19日 | 最終更新日: 2025年5月18日
タグ: OJTの注意点, メールマガジンバックナンバー, 報告書, 打ち合わせ・出張, 技術者人材育成
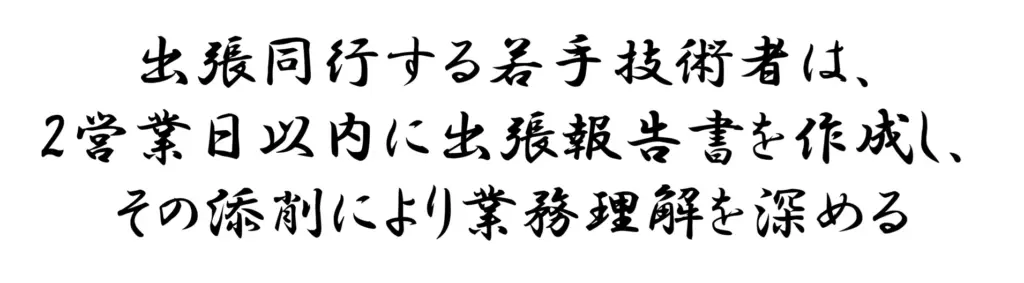
今回は若手技術者に出張同行させて対外業務の経験を積ませたい場合、
リーダーや管理職がどのような指示を若手技術者に行うべきかを考えます。
出張の同行は若手技術者にとって経験を積む重要な機会
同じ若手技術者であっても担当業務によって頻度は異なりますが、
社外、もしくは社内であっても他事業所への出張は、
近視的になりがちな若手技術者の視野を広げるにあたり、
貴重な機会といえるでしょう。
普段接することのない主として技術系社員との対話は、
若手技術者にとって聴いているだけでも知らないことも多く、
新鮮に映るに違いありません。
加えて、技術者の普遍的スキルの一つとして”異業種技術への好奇心”を挙げる等、
異業種協業が不可欠な昨今、
若手技術者が自らの安全地帯に引きこもることは許されなくなっているという意味でも、
ある程度、若手技術者は早い段階で外に出ていくことが求められています。
※関連連載
第11回 技術的な飛躍に不可欠な異業種技術への好奇心 日刊工業新聞「機械設計」連載
単に同行させるだけでなく必ず”出張報告書”を作成させる
多くの企業では常識になっていると思いますが、
出張業務を完遂させるには、
「出張報告書は必須」
です。
ここに例外を認めてはいけません。
パワーポイントや口頭での報告など、
文書以外での報告も技術者育成の観点でいえばNGです。
出張報告書を文書形式で記載できない技術者は、
恐らく様々な情報を整理して進める力に課題があるため、
その力量を出張報告書作成を通じて鍛錬する観点が若手技術者育成に重要です。
そして盲点かもしれませんが、
自らの手間を惜しんで後述する若手技術者の出張報告書の確認や指導を行わない、
というのは技術者育成業務の放棄とも言えます。
ましてや、若手技術者を出張に同行させないというのは、
技術チームという組織運営の観点から見て看過できません。
人に任せられず、自分で技術業務を完遂させたいリーダーを含む中堅技術者は若手技術者育成に関与せず、より厳しいジョブ型雇用を基本としたエキスパートを目指すべきでしょう。
若手技術者育成という組織貢献ができないのであれば、
今以上に自らを追い込む覚悟が必要です。
※関連コラム
優秀な中堅技術者が若手技術者に仕事を振り分けず抱え込んでしまう
出張報告書には対外業務の記録蓄積だけでなく、若手技術者の業務理解を確認するという重要な役割がある
出張報告書を作成することは手間である、
業務効率を下げるといった印象を持っている方は、
若手技術者だけでなく、リーダーや管理職の中にも一定数いるようです。
もしかするとその方々に共通しているのは、
出張報告書の役割を明確に理解してことが一因であるかもしれません。
出張報告書の役割について改めて確認します。
対外業務記録蓄積
これはわかりやすいかもしれません。
誰と、いつ、何を話したか。
どこで、何を行って、どうなったか。
このような対外業務の記録は、活字化しないと時間経過に伴い、消えていきます。
良くある話が、その数か月後、場合によっては数年後、
「あの話はどうなった」
「あの時の議論は何だった」
といった過去を振り返るタイミングになって記録が無いためわからず、
全く同じことのやり直しや、不必要な業務の発生につながるのです。
記録の重要性は、技術報告書のそれと全く同じです。
若手技術者の対外業務理解の把握
もう一つは技術者育成の観点が主となります。
出張中、一見すると色々と理解できていたと感じた若手技術者に、
出張報告書を作成させたところ内容を全く理解しておらず、
誤解も多かった、ということは珍しくありません。
活字化は技術業務の理解に加え、
それを自分の頭の中で整理できている必要があります。
出張報告書という業務書類媒体を通じ、若手技術者の対外業務理解度を確認できるのは、
リーダーや管理職が若手技術者育成に取り組むにあたって大変有意義です。
出張報告書内の記載内容間違えや抜け漏れに対する修正指摘は、
それだけで立派な若手技術者育成になります。
そしてプレゼンや口頭での報告ではなく、
あえて文書にこだわるのも、
文章形式での活字化は若手技術者の理解力を把握するのにあたり、
最も精度の良い回答を出してくれることによります。
出張報告書提出は出張終了後1営業日以内が基本、2営業日以内は”必須”
ここは若手技術者の弱いところです。
スピード感をもって文書を作成して提出するということが苦手な方が多いのです。
”技術的事実を突き詰めること”を求める技術報告書と異なり、出張報告書に求められるのは、
「情報の鮮度」
です。
どれだけ丁寧に書かれていても、その提出が1週間も後となれば出張報告書内の情報鮮度は大きく低下します。
出張報告書内で記載されるであろう決定事項や今後の展開も古新聞となってしまい、
例えばその出張報告書を業務決裁権のある管理職が読むころには、
すべてが周回遅れという可能性もゼロではありません。
同じ報告書でも、出張報告書と技術報告書では主目的が違うことを、
リーダーや管理職はよく理解し、
その事実を若手技術者にきちんと伝えることが求められます。
※関連コラム/連載
第5回 普遍的スキルの鍛錬に最適な技術報告書とは何か 日刊工業新聞「機械設計」連載
出張報告書に記載したい技術的内容
これはリーダーや管理職から予め若手技術者に伝えていただきたい点になります。
技術者が作成する以上、出張報告書も技術的観点が含まれるのが通常です。
代表的なものを1つご紹介します。
技術に関する情報の入手
相手企業や組織がこちらの求める技術を有している、
といったことが一例です。
この場合、技術的な討議を通じて情報を交換し、
こちらからは相手に要望や状況を伝え、
相手から必要な技術情報を入手するのが狙いとなります。
当該ケースで若手技術者に出張報告書内で記載させるべき内容は、
入手した技術情報の概要です。
技術的なポイントをおさえつつも”深入りしすぎない”のが重要です。
以下に
「新しい技術が、自社製品の分析に使用できるかを確認するため、出張対応した例」
について、出張報告書の記載方法を考えます。
ここでいう新しい技術は架空で事例を示すのは難しいので、
以下の産総研の情報を参照します。
※参照情報
光の力で神経細胞の活動を簡単に評価する新技術を開発 / 産総研
出張報告書内で記述してほしい技術情報の概要は以下のイメージになります。
技術報告書の記載したい表記内容例
今回の例の出張目的は、
「光でどのように神経細胞活動を評価するのか、その概要に関する技術情報を入手し、当社製品への応用の可能性について判断基準となる要点を理解する。」
だとします。
このように目的を最初におさえるのは、
技術業務の基本中の基本です。
1ページ目は出張報告書のテンプレートに則り、
背景、目的、結論、決定事項、今後の展開を記載し、
以下の”A. 技術情報の概要”の記載は2ページ目の冒頭に記載するといいかもしれません。
”B. 当社技術への応用の可能性について”はそれに次いで記載されるイメージです。
実際に産総研の研究者の方を訪問して議事を残したということを想定しているため、
伝聞表現となっていることにご注意ください。
また、報告書なので「です、ます調」は使わず、「である調」で記載しています。
※お断り※
想定しているのは架空の企業の若手技術者が作成する出張報告書です。
本技術について、直接研究者の方から私が話を聞いたわけではありませんが、
自分がもし打合せするのであればこのような点を網羅するであろう、
という予想も含めて記載を行っています。そのため、技術的妥当性を考慮していないことを予めご了承ください。
<出張報告書の例:ここから>
A. 技術情報の概要
1. 技術の概要
ラマン分光法と機械学習を組み合わせ、
神経細胞、並びに当該細胞の凝集体の活動を、
従来の蛍光プローブや電極を用いずに、
より容易に、かつ細胞の損傷リスクなく評価できる技術であるとのこと。
2. 技術の強み
蛍光プローブや電極を用いず、ラマンスペクトルの変化という、
非破壊手法による計測を可能にしたことが強みである。
また、研究段階ではヒトiPS細胞から作製したグルタミン酸作動性神経細胞のグルタミン酸に対する細胞単体の反応に加え、
同様に作製した神経細胞の凝集体である自律神経細胞のニコチン溶液への反応についても、
その活動評価を行うことが可能であるとのことであった。
3. 使用する評価機器
活動評価に用いるのはラマン分光分析装置のみである。
ただし、神経細胞の活動有無評価には主成分分析を基本に機械学習を導入しているとのこと。
4. 機械学習の種類
主にサポートベクターマシン(SVM)を用いているとのこと。
活動有無による分類が主であるため、教師無し学習によるセグメンテーションを行っているとのことであった。
5. 活動領域と測定波長の選定が重要
機械学習を用いる理由としては、
神経細胞のどの領域に変化が生じるのか、
そしてその際のラマンスペクトルのどの波長帯に着眼すべきかという選定にあるとのこと。
6. 今後の方向性について
培養細胞や微生物集団の評価に応用し、
機能性食品の開発や有用物質の生産性評価に用いたいとのこと。
生体外の評価は動物実験の削減にもつながるとのコメントがあった。
そして多検体の自動計測を可能にする周辺技術の開発や実装を通じて計測精度向上と計測時間削減を実現し、新薬開発やその毒性評価、生殖医療における非破壊の胚評価に応用したい、という計画を有しているとのことであった。
B. 当社技術への応用の可能性について
技術の概要に関する情報を入手後、当社製品評価への応用可否について議論を行った。
1. 当社製品への応用の可能性について
当社が製造販売する機能性食品は、
○○という培養細胞を用いていることを説明した。
この細胞の特徴を説明の上で、今回紹介してもらった評価技術が応用できる可能性があるか、
について討議を行った。
その結果、
- ・どのような評価が最重要かの優先順位の明確化
- ・評価が妥当であるか否かの確認方法の構築
- ・ばらつきにつながる可能性のあるものを考慮した複数サンプルでの評価
という3点を念頭に評価を継続することにより、
本技術応用可否の判断ができるのではないか、
という返答を得た。
以下、本3点のポイントについて、質疑の詳細を示す。
1-1. 評価結果の優先順位の明確化
教師無し学習においては、何をもって正解、または不正解とするかという判断基準を抽出することが、
大変重要であるとのこと。そのため、やみくもにセグメンテーションを実施しても、
本技術が活用可能かの判断が困難であろう、というコメントが得られた。
….(以下省略)…..
<出張報告書の例:ここまで>
技術者が行う討議ですので、”単なる情報収集になってはいけません”。
自らの意思を伝え、それに対してどのような応答が得られたのか。
リーダーや管理職はこのような討議を行うはずですので、
そのポイントを若手技術者が理解し、記録作成ができるレベルで追従できることが肝要です。
次に本例を踏まえ、技術者育成の観点からポイントを説明します。
技術報告書を念頭に置いた出張報告書作成のポイント
最初に理解すべきは、
「技術的な議論に溺れることなく、出張目的を見失わない」
という点でしょう。
私自身は今回ご紹介したような技術は全くの専門外ですが、
議論内容の技術に知見のある若手技術者は、
「自分はこの辺りの技術はわかる」
という専門性至上主義を発揮し、細かい議論に思考が入り込んでいってしまう可能性があります。
専門性至上主義を発揮した若手技術者の思考は技術に深入りしてしまう
こうなってしまうとリーダーや管理職と相手技術者との議論が耳に入らず、
- ・何故、あの技術をもっと深掘りしないのだろう
- ・自分ならこの技術を知っていると伝え、相手と議論するだろう
といった、出張目的から見ると見当違いの方向に頭(思考)が向いてしまうのです。
さらにリーダーや管理職が話している事実を、正確にかつタイムリーに伝えるという、
出張報告書の基本も忘れると、
技術的な裏付けを調べることに時間を費やして提出が遅れるうえ、
作成された出張報告書は技術的な解説書のようなものになってしまうはずです。
これでは若手技術者の作成した出張報告書は、
絶対に外れてはいけない”出張目的”から遠い内容になってしまうでしょう。
出張報告書の確認を通じ、若手技術者の業務理解を助け、思考の癖を修正する
自分は技術的専門性が高いのだという、自尊心の低い若手技術者が陥りがちな心理状況になっているかは、出張報告書の中身を見ればすぐに判断できます。
出張報告書の確認時に軸ブレが起こっているようでしたら、
リーダーや管理職は丁寧に修正を行いながら説明を加え、
若手技術者がより俯瞰的な視点から物事をとらえるよう導いてあげてください。
これこそが、技術者の普遍的スキルで最も重要な”論理的思考力”の鍛錬に直結します。
本コラムに関連する一般的な人材育成と技術者育成の違い
出張報告書というのは、技術者に限らず総合職でも必要な業務媒体です。
ただ、一般的な人材育成において出張報告書の作成方法について取り上げることはあまり多くなく、
Web上などでテンプレートが見られる程度です。
最近だと生成AIを用いて、議事内容をまとめることに加え、
出張内容を声で入力し、出張報告書の作成に該当するまとめを行う、
という業務効率を最大化することも行われているようです。
これに対して技術者育成においてはまず出張報告書のテンプレートを設定します。
前出のAIやパワーポイントではなく、必ず文書データ形式で作成者が記述を行う形とします。
出張報告書について、技術領域に関わらずどの企業においても基本的には全く同じ構成にするのが重要です。
何故ならば、技術者が作成する報告書ではどの内容がぶれやすいか、
または抜けやすいかが決まっており、
それらをあえて大項目として設定しているからです。
その後はひたすら報告書を記述する練習を行います。
研修ではなく、OJTが基本です。
生成AIを使うといった効率に関する議論は一切しません。
そもそも生成AIに適切な情報を口頭でインプットできるのであれば、
出張報告書を作成することはそれほど難しくありません。
効率の話ができるようになるのは、出張報告書はもちろん、
技術報告書も難なく作成できるレベルになっている技術者だけです。
ただ、このレベルの技術者は各種書類作成業務効率は非常に高く、
日常業務で苦にしないのが通常であることは加筆しておきます。
若手技術者育成はこのレベルに若手技術者を育てることが狙いにあります。
業務効率という概念と一線を画し、
本当の意味での論理的思考力を鍛錬することで、
その土台の上に載せる技術専門性の伸長を支援する、
というのが技術者育成の基本理念です。
本コラムに関連する具体的な技術者育成支援の例
技術者育成コンサルティングとして対応します。
実際に技術チームの顧問として技術ミーティングに参加しながら技術内容を把握します。
そのうえで、出張報告書のテンプレートを研修を通じて導入し、
承認ルートと管理方法を確立いただいた後は、
OJTを基本に出張報告書の”添削指導”を行います。
若手技術者の出張報告書作成スキルを高めるには、その確認者、承認者であるリーダーや管理職のスキルを高めるのが大変重要であるのがこの狙いにあります。
中長期にわたって様々な場面で作成される出張報告書を一つひとつ添削の指導を行い、
それを通じて、ぶれない添削をできる状態になるよう継続支援してまいります。
まとめ
出張報告書を2営業日以内に提出することは、
若手技術者にとって、特に初期のころは大変だと思います。
しかしそれ以上に大変なのは、それを添削するリーダーや管理職なのです。
他人の作成した文章を確認、修正することは、
自分とは異なる慣れない文章表現が含まれることも多く、
作成者である若手技術者が言わんとしていることに歩み寄る必要があります。
それでも出張報告書の添削を行う必要性は、
若手技術者の状況を正確に把握し、
業務に対する理解を深める手助けになることに他なりません。
異業種技術協業を行う技術チームをはじめ、
出張報告書作成の機会の多い技術チームで是非とも取り入れていただきたい考え方です。
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: