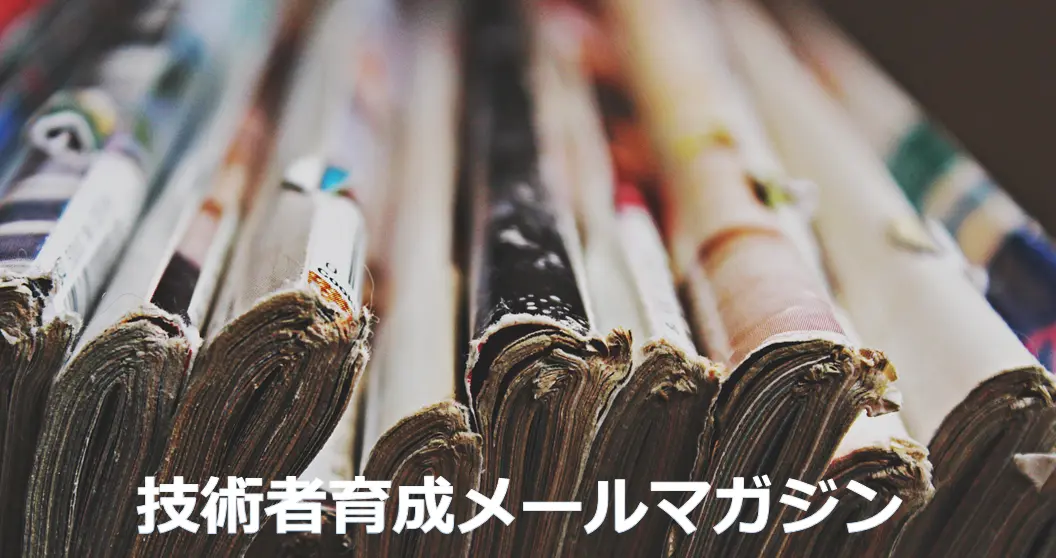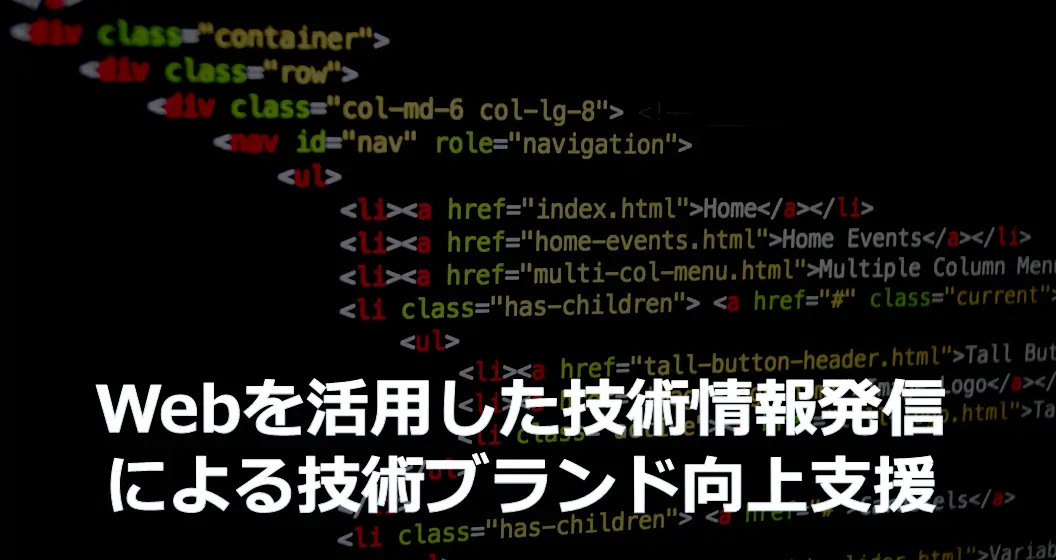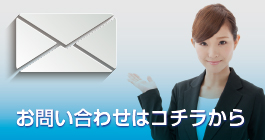第28回 パワハラが怖くて若手技術者育成に取り組めない 日刊工業新聞「機械設計」連載
公開日: 2025年11月10日 | 最終更新日: 2025年11月10日

Image above was referred from 日刊工業新聞社「機械設計」HP
日刊工業新聞社の月刊誌である機械設計で、
若手技術者戦力化のワンポイント
という題目の連載の記事が2025年12月号に掲載されました。
題目は、
パワハラが怖くて若手技術者育成に取り組めない
です。
パワハラに関する定義は若手技術者とリーダー・管理職で異なることが多い
power harassmentという単語が使われるのは、意外にも日本と韓国が主のようです。
しかしながら世界どこの国でも同等の問題は存在しています。
議論になりやすいのが、何がパワハラで、何がパワハラでないのかという定義です。
リーダーや管理職など、パワハラを行う可能性のある側にいる方々は、
どのような言動が該当する可能性があるのか、
ということを研修などを通じてある程度理解しています。
例えば業務に必要なことであれば、ある程度の厳しい言い方などはパワハラには通常該当しません。
一方で若手技術者は、リーダーや管理職とは異なる感覚を持っています。
その一つが、
「自分のプライドを傷つけられたらそれはパワハラである」
という感覚です。
これは専門性至上主義を抱えなければならないほど自尊心が低い状態が一因であり、
若手技術者全員とまでは言いませんが、程度の差や表に出る出ないの差はあれ、
殆どの若手技術者が有している思考パターンです。
この定義づけ時点での認識誤差が、多くの場合パワハラという形で問題がその輪郭を表すと私は考えています。
リーダーや管理職があることをやめればパワハラと認識されるリスクが低減する
前述のパワハラに関する定義の違いは、簡単には埋まりません。
これを埋めるにはある程度の時間をかけた信頼関係の構築が前提になるためです。
では、リーダーや管理職がパワハラリスクを低減するため、
まずどのような言動をとるべきか。
今回の連載では、パワハラを助長するリーダーや管理職の思考の癖を具体例を用いて解説し、
それを修正するための習慣も提案しています。
当然ながら若手技術者側も認識を改めるべき点はありますが、
まずは年長者であるリーダーや管理職から言動を変える必要があります。
今回の連載内容を実践し、パワハラの無い、
より正確には若手技術者からパワハラと認識されない形で、
技術者育成を推進いただければと思います。
日刊工業新聞社「機械設計」はこちらのページから購入することが可能です。
※関連コラム/関連ページ
| 海外出張 の難しさ |
| 技術者育成における若手の 叱り方 |
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: