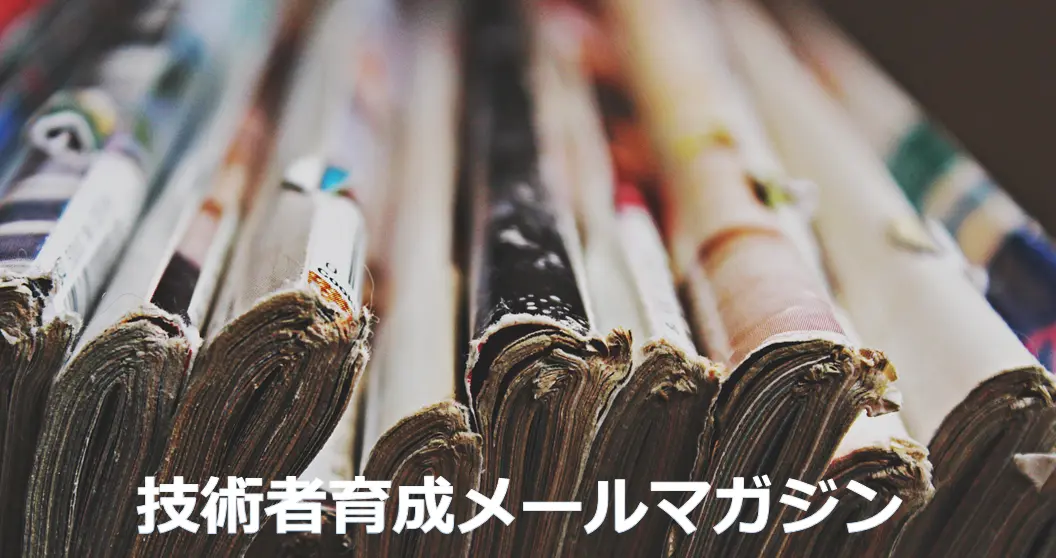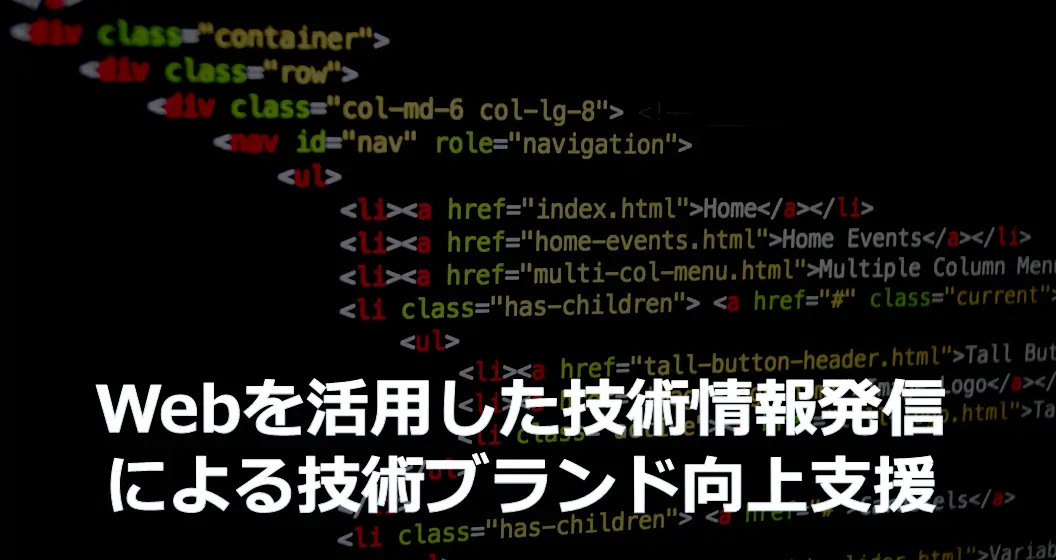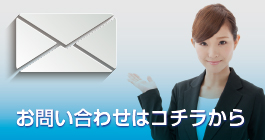従来型の研究開発手法だと若手技術者のモチベーション低下が止まらない
公開日: 2024年12月16日 | 最終更新日: 2024年12月15日
タグ: メールマガジンバックナンバー, 打ち合わせ・出張, 技術者のモチベーション, 技術者人材育成
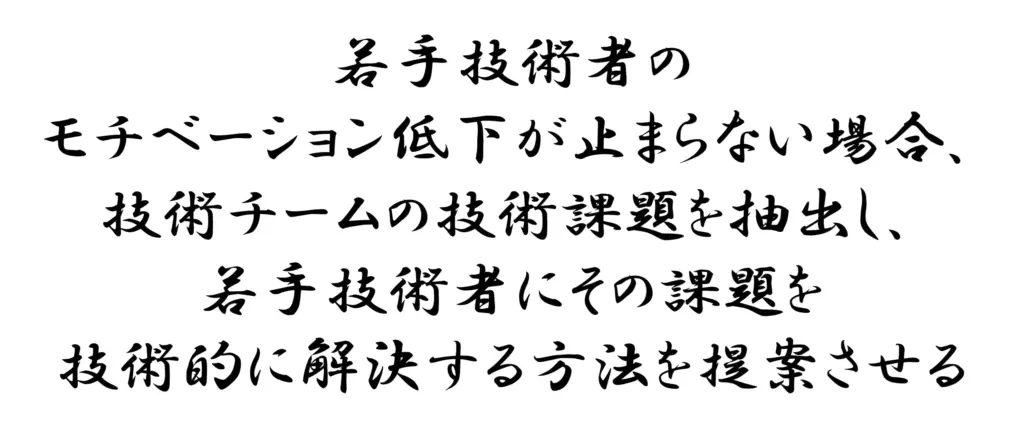
今回は技術者育成において必要最低条件であり、
かつ最重要の若手技術者のモチベーションが低下している、
という課題への取り組みについて考えます。
従来のやり方だけでは行き詰まる時代
社会ニーズの変化、働き方改革を含む労働環境の変化、
ベテラン技術者と若手技術者の減少、
情報技術の進化や新興企業の台頭など、
製造業を生業とする企業にとって今は過渡期にあります。
このような環境下では、今までのやり方だけでは行き詰まるリスクが高くなります。
一方で、トレンドだけを追って本質を見失えば足元が崩れるため、
リーダーや管理職は難しい舵取りを求められます。
過去の成功事例の”具体的手法”にこだわり過ぎる
製造業企業が過去に大きなヒット商品を出した、
または時代ニーズに合致した部品製造の大型受注を得られた、
といった開発の記憶があるとします。
そしてこれら成功には何かしらの流れがあるでしょう。
過去の成功事例にこだわるのはよくないという論調もありますが、
問題は事例へのこだわりではなく、
「”具体的手法”にこだわる」
ことが問題だと思います。
具体的手法といっても様々ですが、
例を示すと以下のようになります。
顧客との助走を前提とする”密着型開発”
顧客からのニーズを獲得するため伴走しながら開発案件を詰め、
抜き差しならない関係を構築したうえで特定顧客向けの製品を開発した。
海外製品や他社製品の模倣品に近い製品開発を協力企業に委託する”丸投げ型開発”
主として北米や欧州の製品を模倣し、
それを迅速に対応してくれるであろう複数社に丸投げし、
相見積もりをしたうえで一番安い企業に委託をして新しい(類似)製品を開発した。
どちらも一見正しいようで、
技術的観点から見ると様々な課題があります。
過去の具体的手法にこだわる最大の課題は能動的な技術成長の観点の欠落
前述の例でどちらにも共通するのが、
「自社の基礎技術を高め続けるという観点がほとんどない」
ことです。
顧客依存型も丸投げ型であり、
どちらも自主性に欠けているのです。
過去はそのようなやり方でうまくいったかもしれませんが、
このやり方には大きな問題があります。
最大の問題は若手技術者から”ここにいても技術的に成長できない”と思われること
一言でいえば、若手技術者から”技術的な観点で見切られてしまう”ことが最大の問題です。
密着型や伴走型はビジネス的にうまくいくのかもしれませんが、
技術者は売上利益だけで仕事はできないのです。
※関連コラム
常に技術的な進歩の実感を得られるのは、
今回の主題である”若手技術者のモチベーション”の向上に直結します。
密着型も丸投げ型も向上心のある若手技術者から見ると、
「誰でもできる仕事」
に映るでしょう。担当する技術者が、技術的な専門性を高める要素がほとんどないからです。
- 何のために今まで技術的な勉強してきたのか
- このまま主体性のない仕事をしていて自分の将来はどうなるのか
- 同年代の若手技術者との差がこれからどんどん大きくなる
上記のような不安が若手技術者の中で増大することは容易に想像できます。
結果として若手技術者が到達するであろう出口は言うまでもありません。
この出口の意味を、もしリーダーや管理職の方がイメージできないのであれば、
その職場に居る若手技術者、
場合によっては中堅技術者のモチベーション低下がかなり進行していることは間違いないでしょう。
では既述のような若手技術者のモチベーション低下状態を打破するために、
どうすればいいのでしょうか。
一度立ち止まり技術チームの技術的課題を抽出する
若手技術者のモチベーション低下に歯止めをかけるため、
リーダーや管理職がまず取り組むべきは、
「技術チームの今抱える技術的課題を抽出する」
ことです。
ここでいう技術チームは、若手技術者だけでなく中堅、ベテラン技術者を含む組織のイメージです。
ただし、具体的なやり方についてはいくつかの注意が必要です。
議事を進行する議長と記録をとる書記を用意する
議長は発言を適宜切ることのできるバランスを有する人物、
書記は発言の”事実”を丁寧に記載できる人物が望ましいです。
技術チーム内にこだわる必要はなく、
例えば総務部や人事部をはじめとした他の部署の人間に依頼することも可能です。
特に議長は最終的に取りまとめの役割もあるため、
第三者目線を有していることが不可欠です。
よって、議長については他部署の人間が担当するのが基本として、
場合によっては社外から召喚することも考えるべきです。
発言者に対して一切の批判や否定をしない
発言する技術者の立場やキャリア何であっても、
他の出席者が批判する、否定する発言は絶対NGです。
特に若手技術者が何か発言することに対し、
「経験が浅い人間に何が分かるのだ」
といった言葉をかけるのは言語道断です。
仮に的外れだったとしても、それは受け取る側がそう思っただけで、
発言者本人から見ると本音の可能性もあります。
周りは必ず聞き役に徹してください。
感情を完全排除した”事実”だけを丁寧に記録する
書記は発言の事実を丁寧に記述してください。
感情や考察は不要です。
これらのデータは後からまとめに使います。
必ず取りまとめる第三者目線を入れる
技術チームの課題抽出には”痛み”を伴います。
発言者の受け取り方によっては人格否定ととられるような内容が含まれるかもしれません。
そのため、身内だけでやっていると立場による上下が大きな要因となり、
技術チームの技術的課題の抽出という本来の目的に到達できません。
話が発散するだけでは、課題抽出はできないのです。
単なるガス抜きで終わってしまいます。
そのため、第三者目線を有する人を迎え入れ、取りまとめを依頼するようにしてください。
社内の他部署、または社外の専門家が一案です。
そしてこのとりまとめ役を議長にすることが肝要です。
議論するのはあくまで技術的課題
単なる課題という表現だけではかなり抽象的になり、
人により考えることが異なる可能性があります。
人事体制や指示系統の問題、
はたまた人間関係という組織では手を出しにくい内容も課題として取り上げられやすいです。
技術者が集まって議論する内容ですので、
あくまで話をするのは技術的課題に終始するよう、
リーダーや管理職は注意し、
また議長をやる方に依頼するようにしてください。
最も望ましい技術的課題は、
「自社技術の強みを高める、またはその強みを対外的に示すために足りない技術」
という題目です。
技術的課題というと、後ろ向き、または新しい技術に目が行きがちですが、
既存の自社技術の強みを高め、それを対外的に示すのに必要な技術は何か、
という議論を中心に技術チーム内での議論できることが望まれます。
技術的課題の抽出が終わったらその解決方法を若手技術者に提案させる
課題抽出が終わってまとめた後、
ある程度の期間を決めたうえで、
「その技術的課題を解決するために何をすべきか、何が必要なのか」
について若手技術者に具体的な提案をさせます。
提案の発表は技術チーム内で口頭にて行う
リーダーや管理職を含め、
技術者全体で若手技術者の提案に耳を傾ける場を設定してください。
提案の共有方法は口頭が望ましいです。
提案の発表まであまり時間をかけない
概ね数週間程度の期間で発表まで完結させるのが理想的です。
あまり長くすると記憶が薄れるためです。
理想的には1週間程度で提案をまとめさせ、
2週間以内に技術チーム内で提案を発表させるのが理想です。
リーダーや管理職は若手技術者の業務負荷調整をしながら、
短期間での提案ができるよう支援をしてください。
提案内容について、技術チーム内では何ができるか”だけ”をチームとして考える
提案については、
- ・無理
- ・困難
- ・無駄
といった提案内容を後戻りさせかねない議論をする必要はありません。
技術チームとして出してほしい答えはただ一つ。
「提案内容について、何であれば今でも実行に移せるか」
です。
提案内容を実行するにあたっては若手技術者だけでは難しく、
技術チームとして推進する必要があるかもしれません。
いずれにしてもリーダーや管理職は、
若手技術者の提案内容を推進する業務を技術テーマとしてプロジェクト化し、
提案者である若手技術者を筆頭としたチーム編成をしてください。
自らの提案で技術チームに貢献できたという実感は若手技術者のモチベーションの大きな向上につながる
ここまで述べてきた内容において、
どこが若手技術者のモチベーション向上につながるのか、
と感じた方がいるかもしれません。
この一連の工程を通じて
「技術チームに貢献できた」
という実感こそが、若手技術者のモチベーションを大きく向上させることになります。
自らの提案という要素が含まれることで自分の実績と認識させる
チームの技術的課題を経験の浅い若手技術者に抽出させるのは無理でしょう。
しかし取り組むべき技術的課題という予備情報があれば、
それについてどのようなやり方や技術で課題を解決できるのか、
という検討をすることは若手技術者でも十分可能です。
最も難しい技術的課題抽出において、
若手技術者がどこまで直接的に貢献できるかは未知数ですが、
与えられた課題に対して提案することは若手技術者でも何かしらの結果を示すことは可能です。
そして、このような結果が若手技術者自身の成果であることは明確です。
このように自分の実績であると実感させることが、
若手技術者のモチベーションを向上させる基本戦略です。
技術チームという組織に貢献したことを伝える
これもリーダーや管理職の方にとって意外かもしれませんが、
若手技術者の多くは、心のどこかで組織に貢献したいという意識を持っています。
今回紹介したような技術チームの抱える技術的課題解決に向け、
具体的な提案をさせることは誰の目から見ても組織への貢献です。
よって個別面談などの際、リーダーや管理職から
「本点において技術チームへの課題解決に貢献をしたことを評価する」
と若手技術者に伝えることもモチベーション向上に高い効果があります。
本コラムに関連する一般的な人材育成と技術者育成の違い
チームの課題を抽出するという、
ブレインストーミングのような会議体の推進方法については、
一般的な人材育成でも取り入れられ、該当する支援や研修等も存在します。
技術者育成において課題抽出の際にブレインストーミングを活用することについて大きな違いはありませんが、抽出すべき対象を
「技術的課題」
に絞っているのは大きな違いといえます。
技術的課題を抽出するには、
議長を行う人物が技術的概要をある程度理解でき、
かつそれを基軸に議論を深める投げかけができる必要があります。
その議論の広げ方も一気に細かい手段に陥らないよう、
少しずつ技術的領域を広げながら俯瞰的に捉える視点が必要で、
このような議長を設置し、適切な発言を若手技術者にも促すには、
技術者育成に基づいた議論展開のテクニックが求められます。
さらに議論を抽象的な部分で終わらせないよう、
類似技術や関連技術に関する情報のインプットも必要で、
この辺りは一般的な人材育成では網羅されていない部分となります。
本コラムに関連する具体的な技術者育成支援の例
当社の技術者育成コンサルティングでの対応となります。
当社として最も多いのは、
「技術的課題抽出を行う会議の推進とまとめの支援を行う」
ことです。
技術チームの今後の展開を考えるにあたり八方ふさがりのような状態になった際、
当社が第三者として打ち合わせに参加の上、
会議の推進とまとめの支援を中心とした議長の方の支援を行います。
このような打ち合わせに先立ち、
- ・技術チームの技術概要に関する情報
についてクライアント企業からのヒアリングの上で、
- ・技術的課題抽出を進めるにあたっての議事進行と記録の注意点
- ・若手技術者への指示の出し方の留意点
といった内容について情報提供を行います。
その後は若手技術者のフォローの方法や、
必要に応じた指示や指導の方法についても相談に応じながら業務を推進し、
若手技術者のモチベーション向上を目指します。
まとめ
技術的課題抽出は技術チームとして常に取り組むべき業務であると同時に、
モチベーションが下がった若手技術者の気持ちを引き上げるためにも必要です。
若手技術者のモチベーション低下は技術者育成において最も避けなければなりません。
何故ならばこのような状態が続くようでは、
どのような育成を行ったとしても育成効果が出にくいからです。
技術的課題という概ねの方向性を示した後は、
若手技術者にその課題解決に向けた取り組みを考えさせて提案まで行わせることで、
自らの組織への貢献という帰属意識を高め、
モチベーション向上につなげていただければと思います。
※関連コラム
モチベーションが下がり立ち止まっているように見える若手技術者
若手技術者の専門性に関する 執着心 をモチベーションの原動力に
技術の基礎知見 を高めるための調査をどのようにやらせればいいかわからない
技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら
技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: